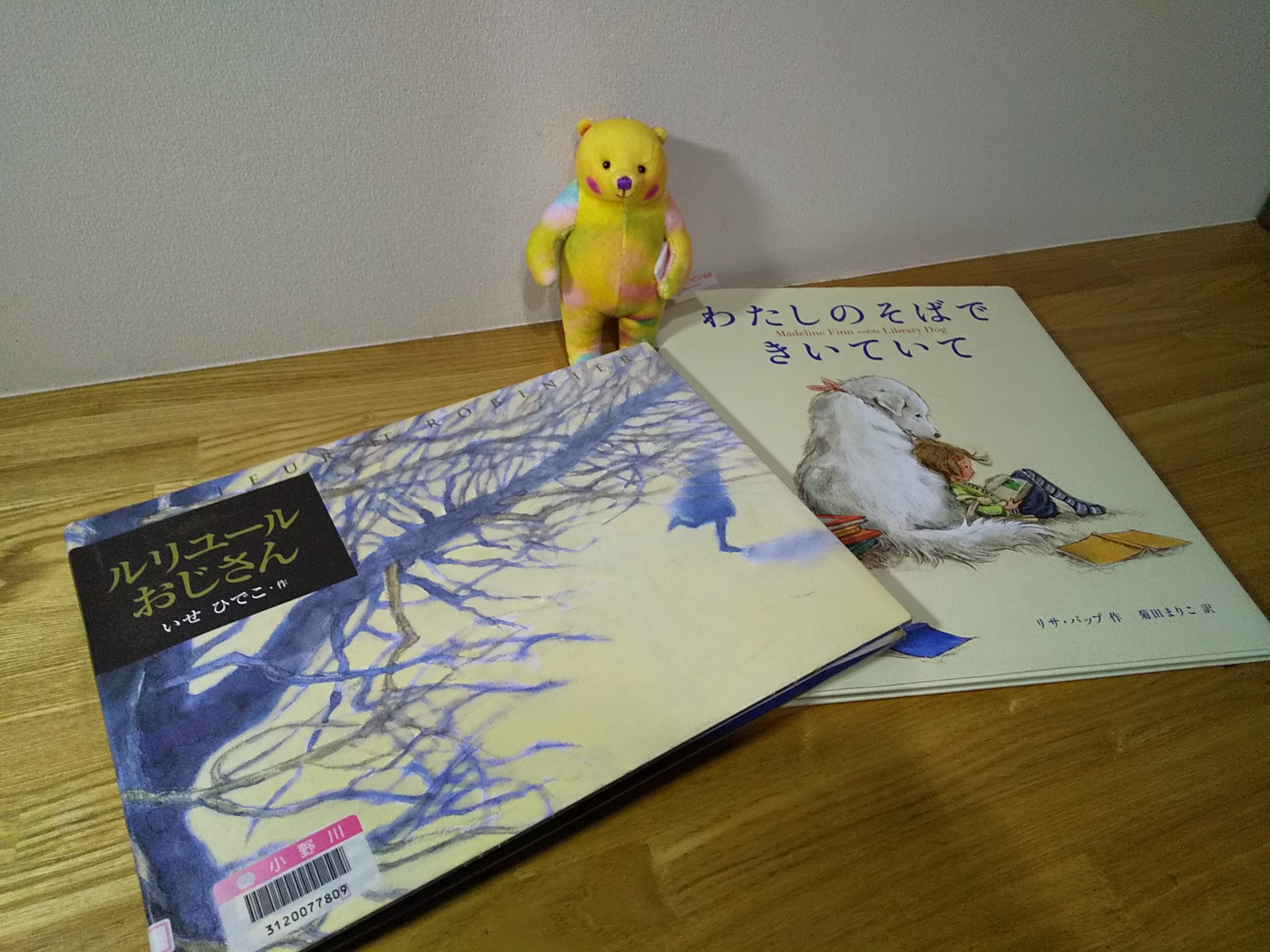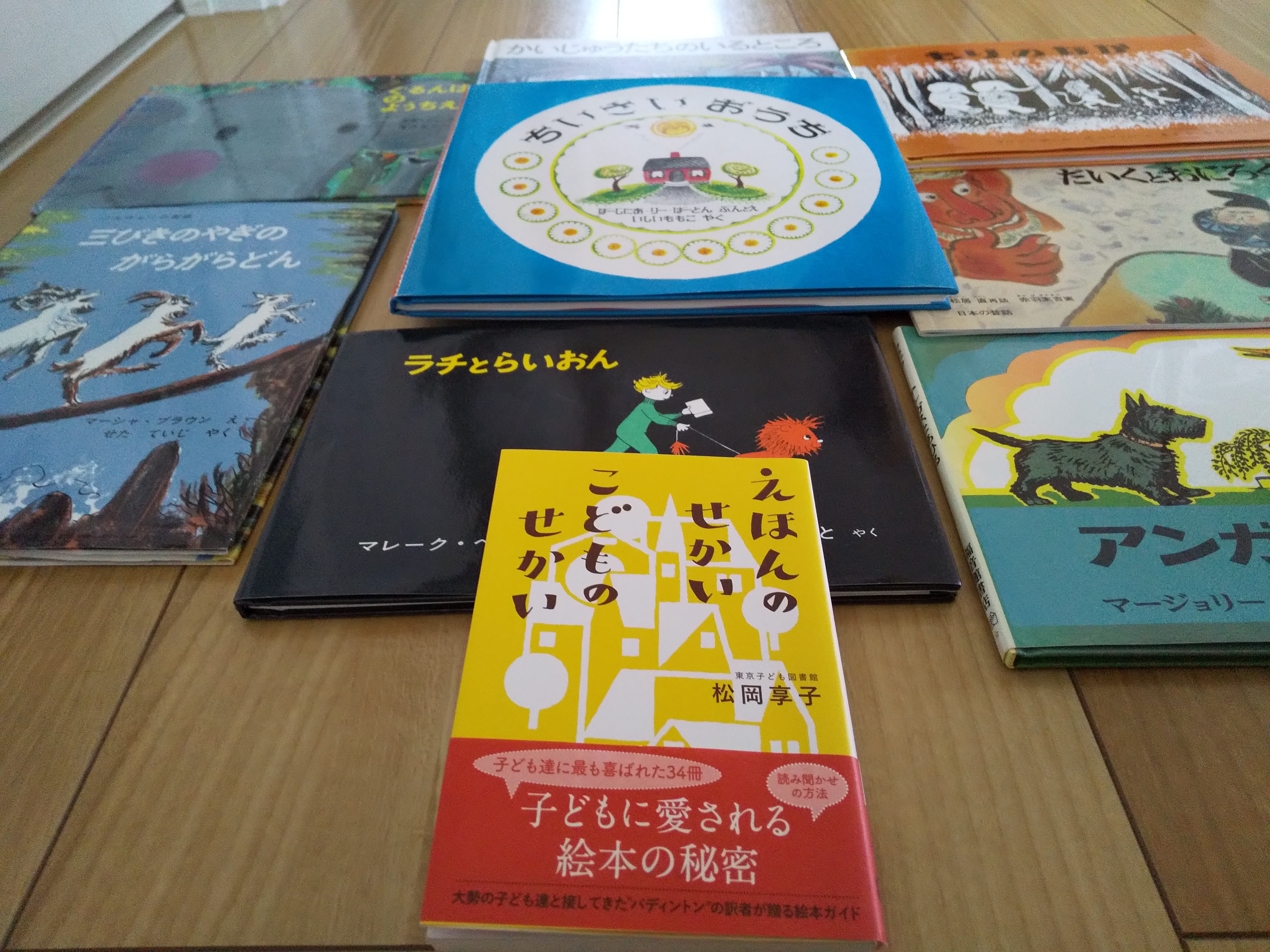花まる学習会平沼先生の「旅する読書 ~大人のための読書講座~」第9回に行ってきました
大好きな平沼純先生の連続読書講座に行ってきました。
今回は、わざわざ北浦和まで。
いつもは御茶ノ水ソラシティなのですが、今月はどうしてもその日が都合がつかず、でもどうしても行きたくて、北浦和会場の日に行きました。
まぁ、つくばからだと、どちらも遠出なのは変わりませんから。
会場は、花まる学習会スクールFC北浦和教室。
駅から徒歩1分のところに、どど~んと、こんな感じであります。

息子たちがずっとお世話になってきたつくば教室とは、だいぶ趣が違いますね。

今回のテーマは、「児童文学で描かれる『時』 ~とびらを開ければ秘密の時間~」。
まずは、平沼先生が旅した文学にゆかりの土地をスライドでご紹介。
今月は、「長くつ下のピッピ」で有名なリンドグレーンが生まれ育ったスウェーデン。
観光地にもなっていない、のどかな北欧の田舎町は、まさに物語の舞台そのままです。
リンドグレーンのテーマパークなどもあり、ファンは必見ではないでしょうか。
私もいつか、時間をとってゆっくり訪れてみたくなりました。
次に、平沼先生による朗読。
森絵都作の「竜宮」という短編を読んでくださいました。
子供の感覚と老婦人の感情が織り成す世界。
若いライターの思い込みと勘違い、そして激しい後悔…
なんとも切なく、心に沁みるお話でした。
今回、「子どもの時間」、「子どもが生きている神話的時間」という視点で様々な児童文学や詩に触れ、考えてみました。
まだ言葉を獲得する前の子どもは、世界のあらゆる境界があいまいです。
世界は、言葉によって明確に切り分けられると考えられます。
境界があいまいということは、あらゆるものがゆる~くつながっているということ。
幼い子どもは動植物や石ころ、道具などとも会話をしたり、仲間として認識していたりします。
それはただのメルヘン、幼稚な嘘、作り話と切り捨ててしまう大人もいますが、子どもたちがまだ神話的時間を生きているのだと思うと、それはとても素敵なことではないですか。
そういえば、うちの次男も、幼稚園くらいの頃、自分で折り紙で作ったよくわからないものに「かかしくん」という名前をつけて、大事にしていたことがあります。
それこそ、毎晩寝る時も枕元に置いて寝るくらい。
きっとあの時、彼は「かかしくん」と仲間だったのでしょうね。
子どもの年齢に「つ」がつく間、つまり1~9歳(ひとつ~ここのつ)は神の子だと聞いたことがあります。
子どもの世界観、時間感覚、物事の捉え方を、ただ幼い、未熟と思うのではなく、神の世界と自由に行き来しているからこその言動と思うこともできます。
母として、子どもと一緒に過ごす中で、神の時間やものごとがまだ混とんとしている世界の一端を垣間見れたと思うと、なんとも素敵な宝物のような時間だったなと思います。
ブログランキング参加中です!クリックで応援よろしくお願いします♪