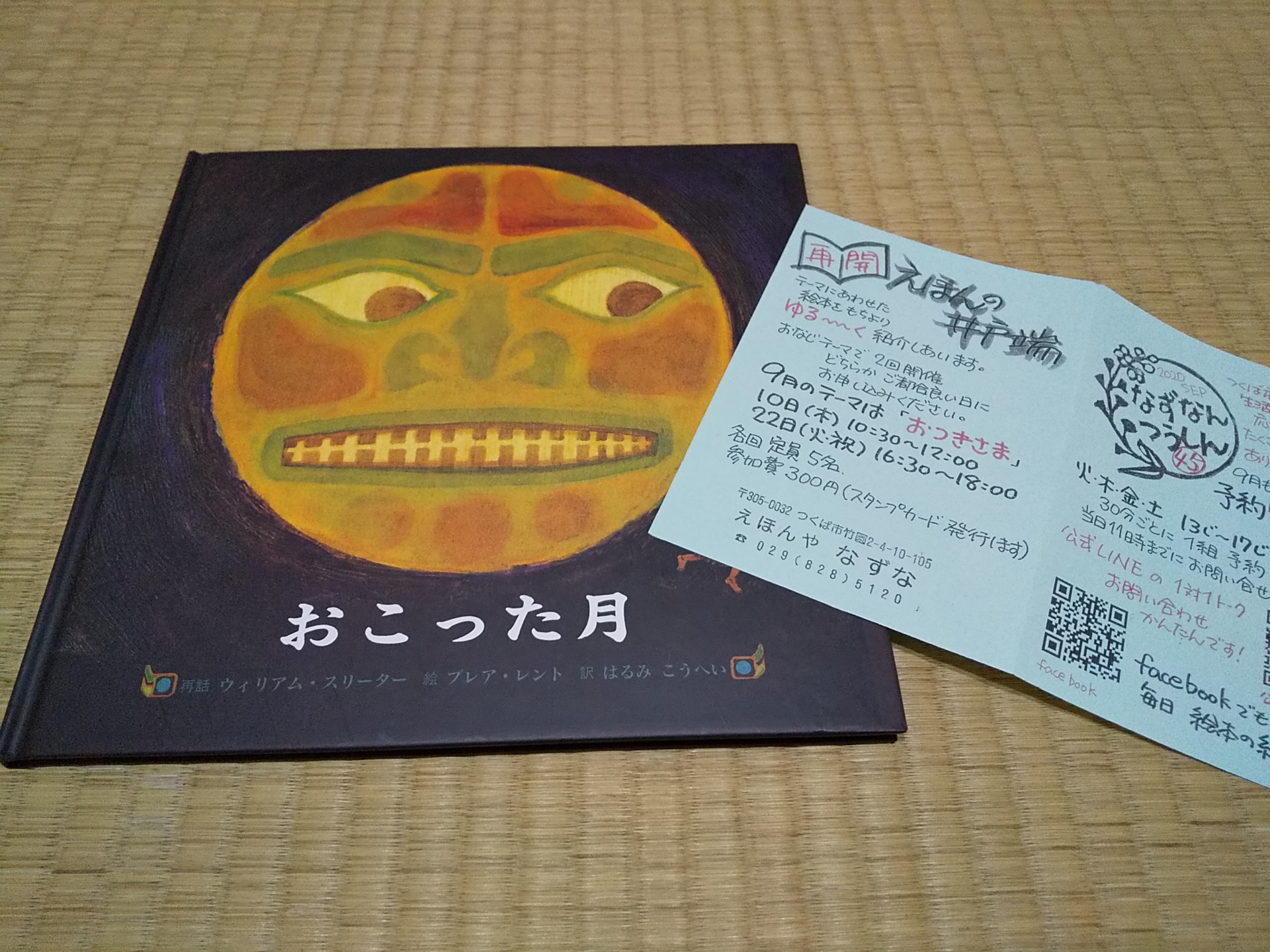『宮沢賢治 絵本の世界』を見て、絵本は情熱とこだわりの結晶だと知りました
こんにちは!
大人に絵本を読んでいる、絵本セラピストらくちゃんです。(プロフィールはこちら)
先日、千葉県市川市にある芳澤ガーデンギャラリーで開催されている「宮沢賢治生誕125年・没後88年記念 宮沢賢治 絵本の世界」という展覧会を見てきました。(2021年10月31日まで)
宮沢賢治の作品を、ミキハウスが絵本のシリーズとして長年刊行しています。
その全36作品の原画や、制作段階の貴重な資料が展示されていました。
原画の迫力はもちろん、制作にかかわる人たちの情熱とこだわりに深く感銘を受けました。
その内容を、ご紹介していきたいと思います。
展覧会の概要
「宮沢賢治生誕125年・没後88年記念 宮沢賢治 絵本の世界」が、千葉県市川市にある市川市芳澤ガーデンギャラリーで開催されていました。(2021年9月17日~10月31日 公式サイトはこちら)

名前のとおり、素敵なガーデンがあるギャラリーですが、この日(2021年10月27日訪問)はあいにくの雨。
柿の実が秋の風情を演出していてなかなか素敵でしたが、庭園散策はあきらめて、展示の鑑賞を楽しむことにしました。

日本を代表する作家、宮沢賢治の作品を、「宮沢賢治の絵本シリーズ」として、1987年からミキハウスが刊行を始めました。その数は、今年刊行の2タイトルを含め、36タイトルとなり、現在も刊行が続いています。
この展示は、宮沢賢治生誕125年・没後88年にあたる記念すべき年に、「宮沢賢治の絵本シリーズ」全絵本作品の原画(1タイトルのみ複製画)を一堂に会した初の展覧会です。
現代の第一線で活躍する画家、絵本作家たちが描き出した賢治の物語。その渾身の原画ととともに、絵本に至るまでの過程、ラフや編集者によるメモ、製本の試作や場面設定の模型なども公開されていて、絵本作りにたずさわる人たちの情熱とこだわりが感じられる内容でした。
絵本制作者のこだわりに感動!
宮沢賢治は、その37年の生涯の中で、童話や詩の作品を多く残しています。
賢治の生み出した独特の世界観を、大人も子どもも楽しめる絵本の形で、ミキハウスがシリーズ化しています。
現代の名だたる画家、絵本作家を起用し、妥協のない作品作りを30年以上に渡って続け、現時点で36作。
まだ続きます。
この36作品の原画が一堂に会したのですから、まさに圧巻。見ごたえがあります。
絵の迫力、美しさ、魅力はもちろんのこと、その作品を生み出すまでの情熱とこだわりの強さに衝撃を受けました。
通常、今の絵本制作では、文を書く作家と、絵を描く画家、イラストレーターは、一緒に作品作りをしていきます。
どこにどんな配置でテキスト(文字)が入り、どんな絵にしたいのか、作家と画家の考えをすり合わせながら作っていくと聞いたことがあります。
絵本は、けっして「お話に挿絵がついたもの」ではありません。
絵と言葉が、お互いを引き立て合い、切り離せない、独自の世界を作っているものです。
しかし、宮沢賢治はもうこの世にいません。
作者と打ち合わせることはできません。
では、絵本画家たちはどうしたのか?
絵筆をとる前に、その作品をとことん理解し、賢治の世界、賢治の思いに限りなく迫ろうとしています。
例えば、作品の中に描かれている情景、風の又三郎がいた学校の教室だったり、林だったり。
それらのジオラマ模型を作り、立体の空間として把握してから、絵にしていた方がいました。
また、「猫の事務所」という作品では、3匹の猫の性格を考え、事務所の机の上がそれぞれどんな感じか、描き起こしています。
その場面は、絵本の中に出てこないのに、です。
登場人物を、性格も含めて生き生きと自分のイメージの中で動かすために、必要な作業だったようです。
「月夜のでんしんばしら」という作品の中には、「9日の月」が出てきます。
画家は、月齢表を調べて、賢治がこの作品を書いた時の9月9日、彼がいた岩手県の月はどのような状態だったかを調べたそうです。
ファンタジーの中で、妥協のないリアリティの追求。すごいですね!

物語の中に出てくる石碑の絵を描くのに、編集者が岩手県の花巻からその鉱石を持ち帰り、画家に渡したそうです。
画家は、その石の質感、手触りを確かめながら、石碑の絵を描きました。
画家も編集者も、妥協がありません。
今回の展示の中には、編集者が印刷所に出した指示のメモなどもありました。
絵の中の前景、後景の遠近の距離感が出るように、黒の強さや明暗について、細かく指示されています。
きっと、印刷の校正なども厳しく、何度もやり直しがあったのではないでしょうか。
今は亡き作家の童話を絵本にする。
そのために、これほどまでに情熱とこだわりを注ぎ込む人たちがいるということに、感動せずにはいられませんでした。
「翳り絵」で描く銀河鉄道の夜
ミキハウスの絵本シリーズ、会場で販売もしていました。
今までこのシリーズは一冊も持っていなかったので、どれも連れて帰りたい絵本ばかり!
しかし、そういうわけにもいかないので、「これぞ!」という一冊を購入しました。
それが、これ。「銀河鉄道の夜」です。

言わずと知れた宮沢賢治の代表作。
もちろん読んだことはありますし、文庫本では持っています。
それでも、この「絵本」というにはあまりにも荘厳で幻想的な美しい本を連れて帰ることにしました。
今回の会場で、たくさんの原画が展示されている部屋の横に、「暗室」と書かれた部屋がありました。
黒いカーテンをくぐって入ると、中は真っ暗。
暗闇の中に並んだライトボックスをのぞくと、そこには「翳り絵」で作り出された、幻想的な世界が広がっていました。
思わず、息をのみました。
「翳り絵」とは、金井一郎氏が編み出し、名付けた技法だそうです。
黒いラシャ紙に針で孔をあけていき、その後ろから光をあてて浮かびあがる、光の粒の集積によって表現されます。
紙は1枚ではなく、基本的に2枚の紙を使います。
それぞれの紙に別々の孔をあけ、それぞれアクリル板の間に挟んで、重ね合わせ、光を透過させます。
その結果、不思議な奥行きと幻想性のある画面が生まれます。
なんと、金井一郎氏は、ほとんど下書きをすることなしに、ひたすら孔を打っていくそうです。
つまり、「翳り絵」は、いわゆる「絵」ではありません。
複数の階層に分かれ、下から光をあてることで見えるものなので、紙に描いた絵のように、すぐに印刷できるわけではないのです。
10代で「銀河鉄道の夜」に出会い、魅了され、10代の終わりごろから影絵、そして翳り絵の制作を始めた金井氏。その後、50年の年月をかけて作品を作り続けてきたというのです。
もちろんそこに「絵本にする」という発想はありませんでした。
それが絵本になったのは、一人の編集者の強い思いがあったから。
金井氏の翳り絵に出会い、感動のあまり直感的に「これを本にする!」と口にしていたそうです。
それから20年、企画を温め、数々の困難を乗り越えました。
翳り絵をどのように印刷するか?
「銀河鉄道の夜」は、絵本にするには長いお話で、ページ数が増えてしまい、費用もかさむ。
もともと絵本を想定していないので、制作されていない場面がある。
それらを新たに制作してもらい、ひとつずつ問題をクリアし、やっと絵本として出版されました。
50年、作品を作り続けた作家。
20年、企画を温め、実現させた編集者。
効率とか、スピードとか、生産性とか、無縁の世界です。
こういうことに、命をかけられる人がいることに、ただただ感動します。
この絵本の価格は、税抜き2,300円。
はたして、高いと思いますか?

まとめ
宮沢賢治は、好きな作家ではありますが、すべての作品を読破しているというほど熱烈なファンではありません。
でも、彼の作品に触れたり、彼に関する企画展に行ったり、彼の愛した場所を訪れたりすると、いつも心がふるえます。
37歳という生涯の中で生み出した作品をとおして、彼が後世に伝えたかったメッセージに、共鳴するのだと思います。
同じように、そのメッセージに共鳴した人が、今回は絵本という形でこの世に示してくれました。

昨年は、地元の茨城県内のミュージアムパークで、自然科学の観点で宮沢賢治作品を読む企画展がありました。
賢治は、作家であると同時に、サイエンティストでもあり、教育者でもありました。

ここでも、賢治が見た宇宙と自然と一体となった、厳かな気持ちを味わいました。
アニメや朗読に触れたときも、やはり独特の賢治の世界、自然や生き物への優しいまなざしを感じます。

今回の会場は、うちから遠く、行きづらいところでした。
長引く緊急事態で、すっかり出不精になっていて、見に行く予定はありませんでした。
ところが、会期終了まぎわにふと思い立ち、思い切って行ってみてよかったです。
これからまた、ゆっくりと翳り絵を楽しみながら、銀河鉄道の夜を読み直してみようと思います。