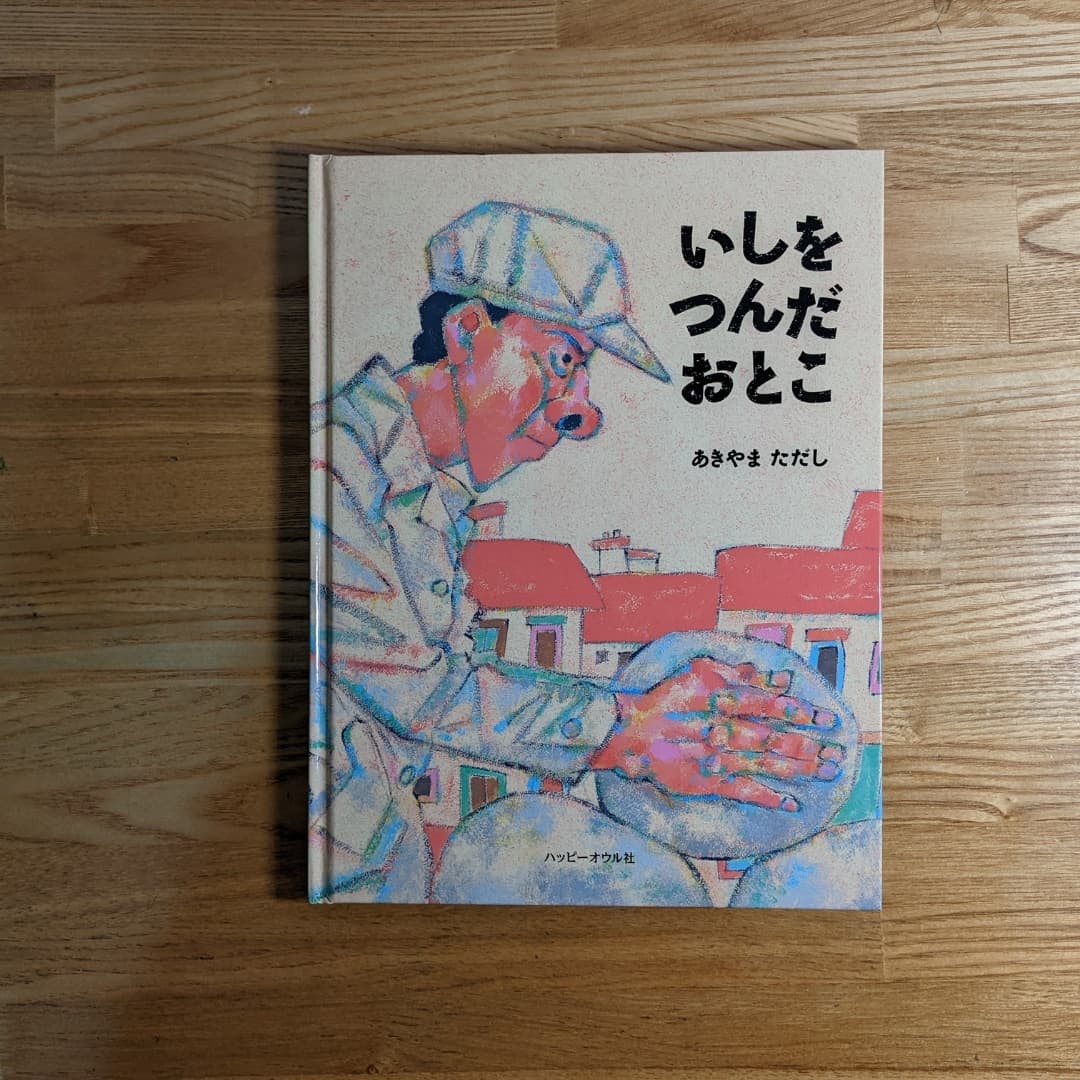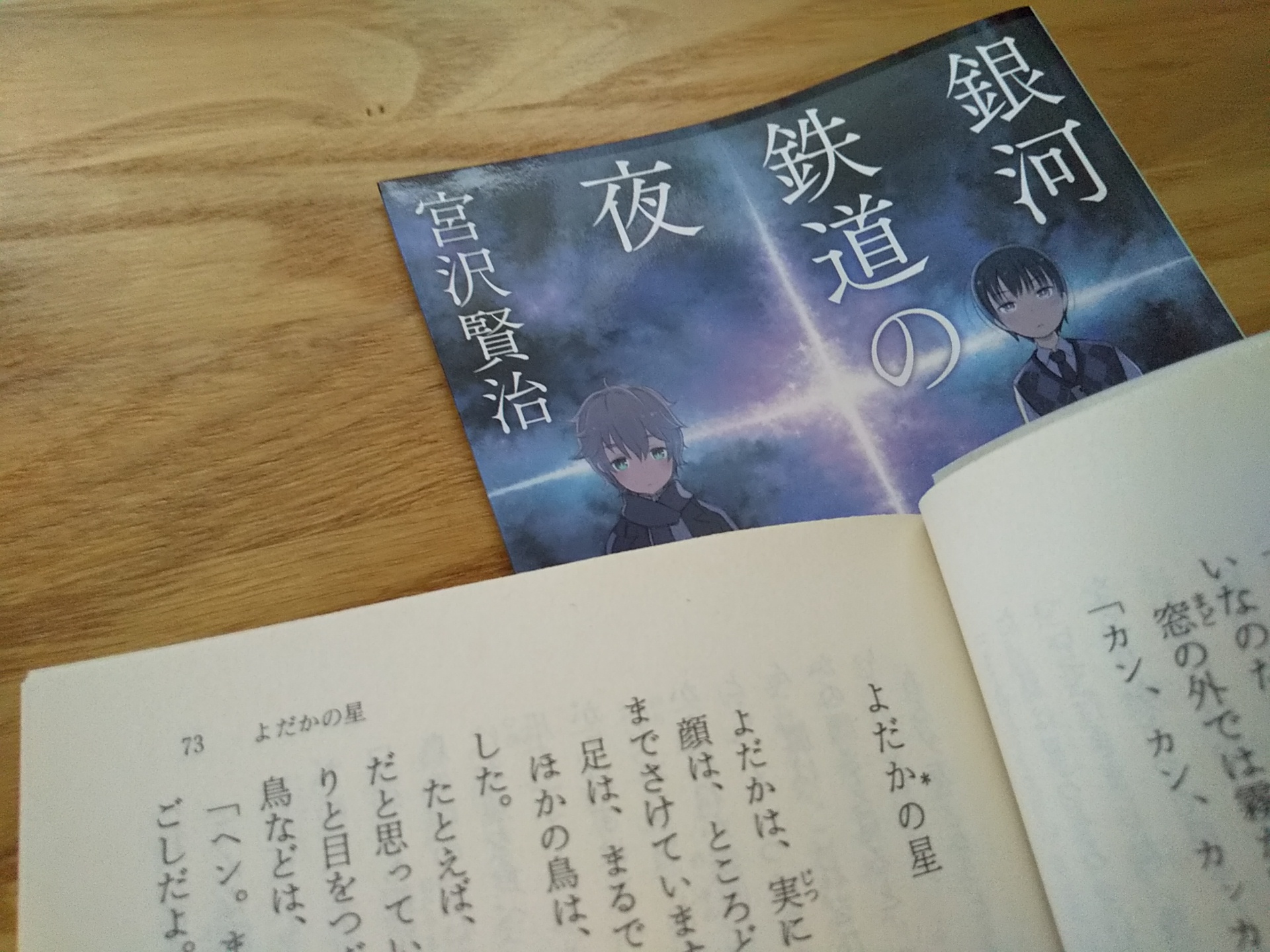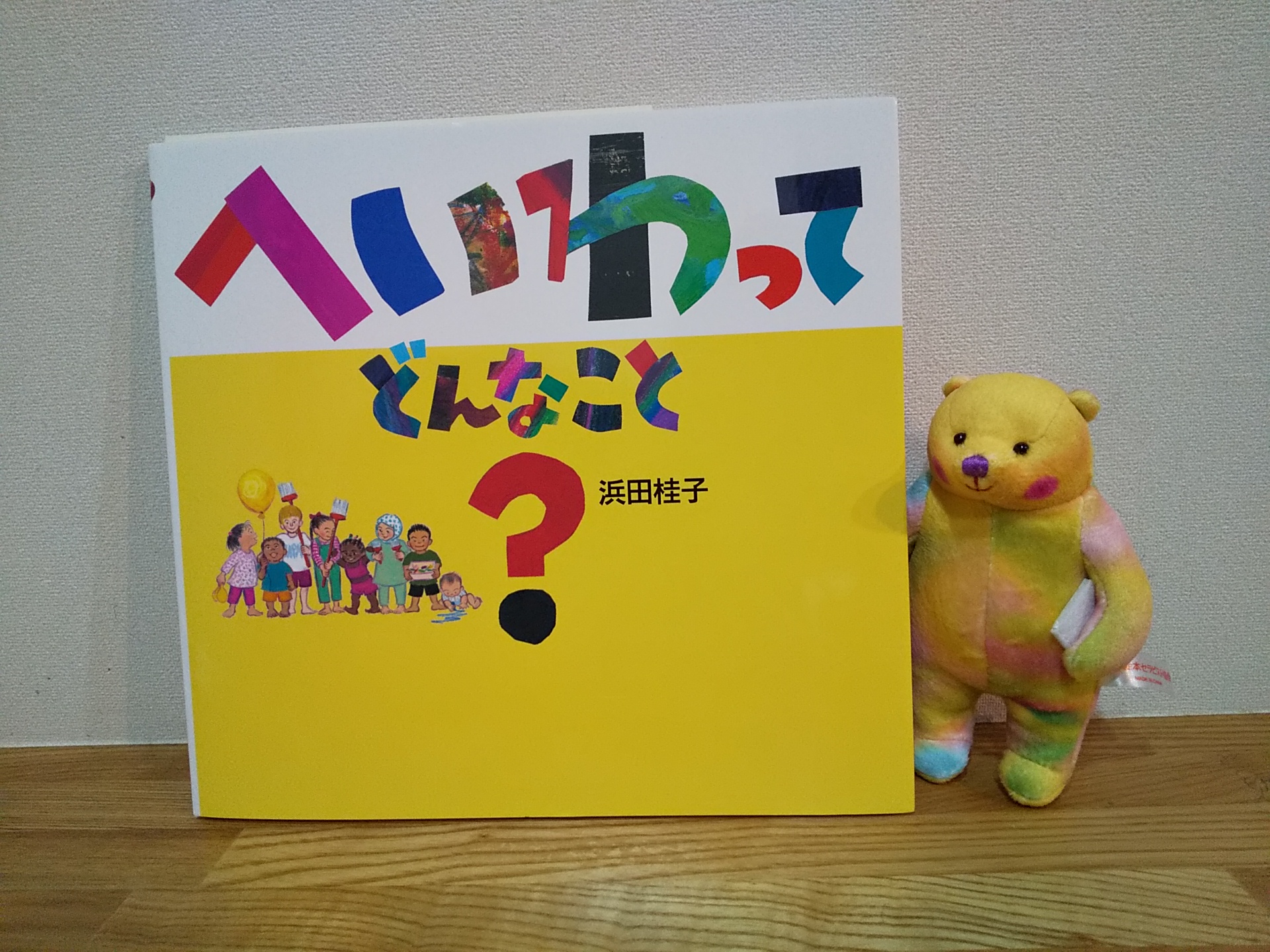母の日、わが家はコートダジュールの半熟ぷりん
こんにちは!
つくば市在住の主婦で、大人に絵本を読んでいる、絵本セラピストらくちゃんです。(プロフィールはこちら)
今日は母の日。
私も一応「母」ですが、不思議と家族に何かを期待したり、ねぎらってもらいたいと思う気持ちがありません。
母の自覚がない、母です。
でも、隣に住む自分の母には何かしてあげたいな、と思います。
2022年の母の日、プレゼントは半熟ぷりん
私の母、入れ歯の噛み合わせが悪く、歯茎が腫れて、痛くてあまり食べられないとのこと。
なので、噛まずに食べられて、滋養のある半熟ぷりんと、フルーツゼリーをプレゼントしました。


つくばでは、誰でも知ってる洋菓子屋さん、コート・ダジュールのものです。
世間話をしながら、一緒にプリンを食べ、穏やかな母の日のひと時を過ごしました。
このプリンは、うちの子が幼かった頃に、母がおやつによく買ってくれたもの。
今は、母に買ってあげるようになりました。
高校生と中学生になった息子たちの、今のお気に入りは「生チョコサンド」。
ちょっぴり大人の味わいかな?

半熟ぷりんで思い出す、「とっときのとっかえっこ」
息子たちの幼かったときに、買ってもらっていた「半熟ぷりん」。
今は、歯の悪い母に買ってあげています。
そこで、ふと思い出したのが、この絵本。
「とっときのとっかえっこ」(サリー・ウィットマン:文 カレン・ガンダーシーマー:絵 谷川俊太郎:訳 童話館出版)

バーソロミューは、ネリーのお隣にすむおじいさん。
ネリーが赤ちゃんだったころ、毎日ネリーをカートに乗せて散歩に連れていき、歩きはじめるようになると必要なときだけ手をかしてくれました。
ネリーの成長にともない、バーソロミューは老い、衰えていきます。
そのうち、ネリーがバーソロミューの車いすを押して散歩に行くようになります。
「とっときのとっかえっこ」は、そういう意味。
まるで、季節が自然にうつり変わるように、人々の状態や役割もうつろいます。
息子たちが小さかった頃に、一緒に読んだ絵本ですが、今あらためて読むと、またしみじみとこみあげてくるものがありますね。
日本の作品にも、同じようなテーマの絵本があります。
「だいじょうぶ だいじょうぶ」(いとうひろし:作・絵 講談社)

これは、「ぼく」と「おじいちゃん」のお話。
一緒にお散歩している時、「ぼく」が怖いこと、心配なこと、困ったことに遭遇すると、いつもやさしく「だいじょうぶ だいじょうぶ」と言ってくれたおじいちゃん。
「ぼく」は次第に成長し、怖いことも、心配なことも少なくなっていきます。
一方、おじいちゃんは年をとり、とうとう病院のベッドの上に。
「ぼく」は、おじいちゃんの手をにぎり、なんどでも、なんどでも、くりかえします。
「だいじょうぶ だいじょうぶ。」
だいじょうぶだよ、おじいちゃん。
母の日に、ぜひ読みたい絵本
お母さんのことを描いた絵本は、ちまたにたくさんありますが、今日ご紹介したいのはこれ。
つい先日購入し、作者のくすのきしげのり先生に、サインをいただいたばかりの作品です。

「おかあしゃん。はぁい。」(くすのきしげのり:作 岡田千晶:絵 佼成出版社)
なんと本文は、「おかあしゃん。」「はぁい。」という、親子の会話だけ。
(一か所だけ、「おとうしゃん。」がありますが)
くり返されるいつもの一日の中に、何度も交わされる「おかあしゃん。」「はぁい。」の会話。
そこには、いろんな思いが込められています。
がんばって、できたときの、得意げな「おかあしゃん。」
嬉しくて、話を聞いてもらいたい時の「おかあしゃん。」
不安な時、怖い時に、すがるような「おかあしゃん。」
眠りにつくとき、そばにいることの温かさ、安心感を確認する「おかあしゃん。」
この絵本を読みながら、わが子がこれぐらいの時の、温かさ、匂い、愛しい気持ちがよみがえってきます。
あとがきを引用します。
羽田から徳島へ帰ってくる夜の飛行機の中でした。
私の後ろのシートに、幼い女の子とお母さんが座りました。
少しねむそうな女の子が、小さな声で「おかあしゃん」というと、 お母さんは、やさしく「はぁい」とこたえます。
この小さく聞こえてくる「おかあしゃん」「はぁい」に、私まで幸せな気持ちになりました。
女の子がすっかり寝入ってしまうまで静かにくりかえされた「おかあしゃん」「はぁい。」
それは、無垢の信頼と深い愛情、そして幸せに満ちた、とびきりすてきな会話でした。
どうか、いつの時代のどの国にも、 幸せに満ちた 「おかあしゃん」 「はぁい」が、たくさんありますように。
くすのきしげのり
うちの息子たちは、今日が「母の日」だという意識もなく、当然プレゼントや感謝の言葉もありません。
でも、それでいいと思っています。
私を「母」にしてくれた。
それだけで、充分すぎるくらい、ありがたいと思います。