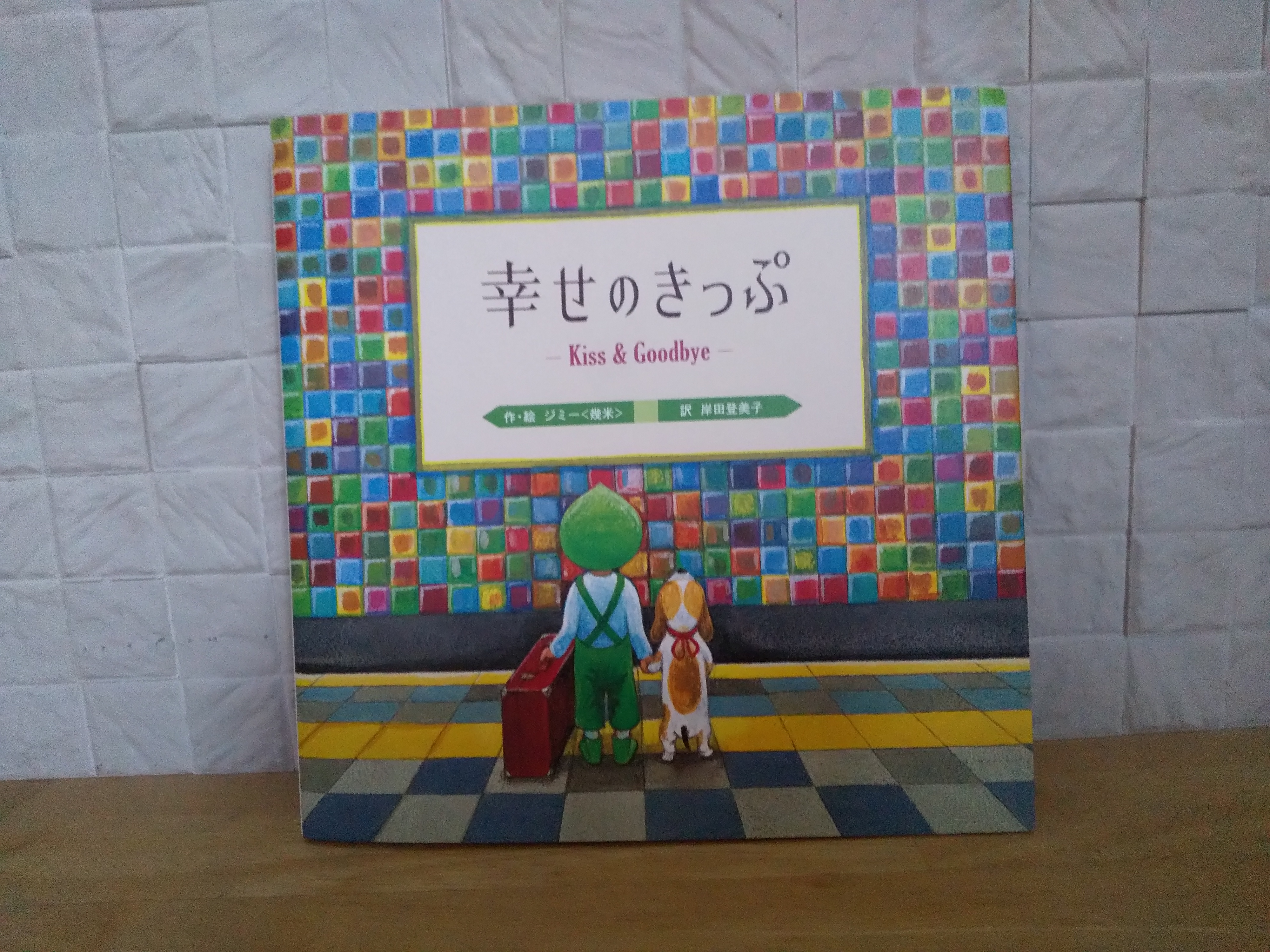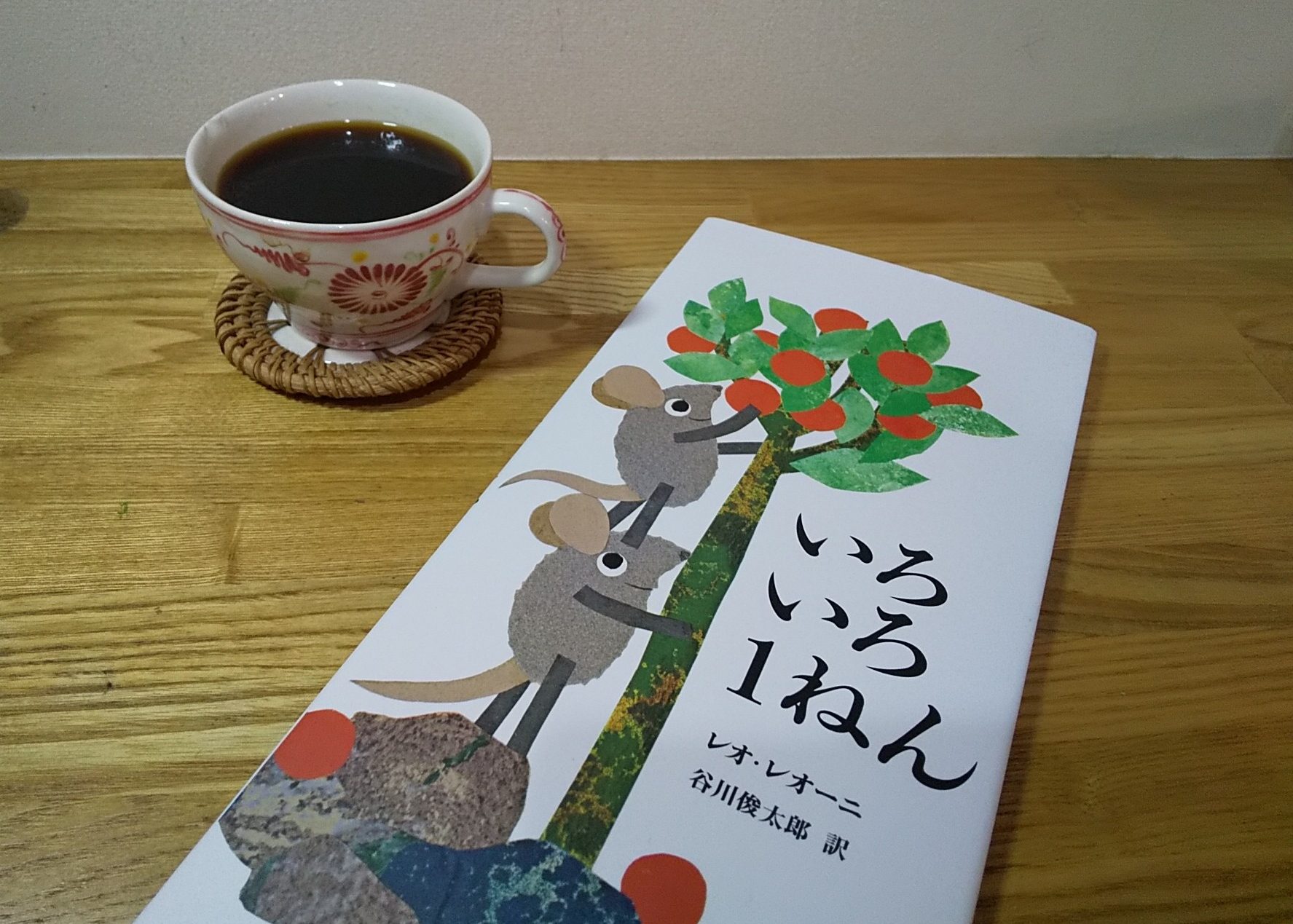「あふれでたのは やさしさだった」寮美千子著📖受容の力、言葉の可能性を思い知りました
この本は、絵本セラピスト協会代表のたっちゃんこと岡田達信さんがFacebookで紹介していたものです。
とても気になったので読んでみましたが、衝撃的でした。
ところどころ涙をぬぐい、鼻をかみ、嗚咽しながら一読して、思わずまた読み返していたほど、大きく心が揺さぶられました。
奈良少年刑務所で行われた、社会性涵養プログラムの一つ、「絵本と詩の教室」。
絵本を読み合い、演じてみる。
詩を書いて、声に出して読んでみて、感じたことを伝え合う。
たった半年、全部で6回のこの教室で、殺人などの凶悪な犯罪を起こし、心の鎧に閉じこもった少年たちが一人残らず変わっていったという事実。
奇跡のような体験を綴ったノンフィクションであり、これからの社会、人間に大切な気付きを与える一冊です。
寮美千子著 西日本出版社
作家であり童話作家でもある寮美千子さんが、奈良少年刑務所から依頼を受けて、受刑者の社会性涵養プログラムの一つとして「絵本と詩の教室」を受け持つことになります。
最初彼女は、「刑務所に入るような人は、がさつで凶暴な人だろう。何を考えているのかわからない、恐ろしい人に違いない。」と思っていたと言います。
多くの人は、漠然とそう思っているのではないでしょうか。
私もそう思っていました。恐ろしい、モンスターのような人たちだと。
しかし、生まれつきモンスターの心根を持った人はいないのです。
親からひどい虐待を受けていたり、劣悪な貧困の中、コンビニの廃棄弁当で命をつないでいたり、ネグレクト(育児放棄)で学校に行ったこともなかったり・・・
加害者になる前に、被害者だったような人ばかりだそうです。
しかし、想像を絶する悲惨な環境で育ち、殺人などの凶悪犯罪を犯すまでに良識も共感力も欠如し、心を閉ざし、捻じ曲げてしまっている人間に、たった6回、ほんの半年、絵本を読んだり詩を書いたりして、どれほどのことがあるだろう。
正直、そう思ってしまいました。
プログラムを始める前、筆者自身も「作家として言葉をなりわいにしているのに、言葉の力をそこまで信じていなかった」と言っています。
ところが結果は、一人残らず変化を起こしたのです。
中には、目の前で、さなぎが蝶になるようにみるみるうちに変わった子もいたといいます。
それはなぜか?
絵本の物語や、すぐれた詩人による名作の力ではありません。
絵本を朗読したり、演じたり、思ったことを伝えること=自己表現。
人の感想をただ聞く。共感してもよし、違う意見を言ってもよし。でもまずは聞く=受け止め。受容。
グループワーク=違い、多様性を知る、受け入れる。
そういうことで、彼らの心が癒され、固く閉ざした心の扉が少しずつ開いてきたのです。
ほんの一言二言、自分の感じたことだけを書いた素朴な、なんの技巧もこらしていない詩ともいえないような詩に、「そうそう」「まったくだよなぁ」と仲間が共感してくれただけで、体がひきつるほどのひどいチックと貧乏ゆすりがピタッと止まった子もいます。
えらそうにふんぞり帰って、生気のない目をし、すべてを拒絶する「おれさまポーズ」をとっていた子は、父親からのひどい虐待を受けたトラウマで、言葉が発せられなくなっていました。
それが、自作の詩を読んでもらい、「わかる、わかる」「ぼくも同じこと思ったことあります」という仲間の感想を聞いているうちに、誰が注意したわけでもないのに「おれさまポーズ」をやめて、おとなしくちんまりと、両膝を揃えて座っていたといいます。
この日を境に、この子は二度と「おれさまポーズ」を取ることはなく、少しずつ発語もスムーズにできるようになったとのこと。
職業訓練のための実習室でのトラブルや問題行動なども、明らかに減少してきたと言います。
また、このプログラムでは、「安心、安全な場づくり」を徹底しています。
この教室だけは、刑務所の中で唯一冷暖房がきいていて快適です。
絶対に評価や否定、強要、指示、命令はされません。
どんな態度で座っていてもOK。
読みたくなければ読まなくても、詩が書けなければ「書けません」でもいいのです。
どんなに発言に時間がかかっても催促されず、打ち切られず、待ってもらえます。
こういう場だからこそ、受け止めてもらえるという安心感ができたからこそ、彼らは心の扉を開き始めたのでしょう。
これらのこと、「安心・安全な場づくり」「感じたことを聞いてもらうこと」「人の意見をただ聞くこと」「否定や批評はしない」「違う意見もOK、正解はない」・・・絵本セラピーの講座の中で、度々強調されていたことでした。
あまりにも絵本セラピーと内容が似通っていて、ぞくぞくしました。
あぁ、人はこういうことで心が癒され、潤うのだな、とあらためて深く納得。
受刑者の中には、知的障害、発達障害が疑われる人も少なからずいます。
人の言葉や感情がうまく理解できない。落ち着きがない、情緒不安定、潔癖症や無頓着の度が過ぎる・・・
目が見えないとか、歩けないとか、体の障害は見てわかるので理解され、支援もされますが、心の障害や知的障害は一見してわからないことが多いのです。
だから、叱られる、嫌われる、いじめられる、親のしつけが悪いと言われ、親も困惑してひどく叱る、時には虐待の域まで行ってしまう、自己肯定感が育たず自暴自棄になり、怒りが蓄積し、犯罪に走る・・・
先日読んでご紹介した「ケーキの切れない非行少年たち」という本の内容と、あまりにもリンクしていて驚きました。
犯罪被害者の視点から見れば、のんきに絵本を読んだり詩を書いたりしてる身分じゃないだろう!と怒りを覚えるかもしれません。
犯罪者には厳罰を。
貧困や虐待にあっても、ちゃんと社会でまじめに生きている人もいる。
犯罪者になってしまったのは、その人間の弱さであり、自己責任。
そういう風潮に流れがちな、今の社会にはうすら寒いものを感じます。
犯罪者になる前に、何とかできなかったのか、何もしてあげることはないのか?と思わずにはいられません。
本書の中で、まるで人を拒絶するような態度で、言葉もあまりない子の書いた詩が紹介されていました。
「うれしかったこと
ぼくがいままでに 一番うれしかったことは
友だちがいたことです」
筆者も、「ごめん、知らなかった。ほんとうは友だちがほしかったんだね。全然気がつかなかった。人が嫌いなんだと思ってた。」と言って涙します。
詩を使って、彼は本心を表現することができました。
周囲も彼の本心を知ることで、不器用な彼と交流の道が開けていくことでしょう。
もっと早くにこういう交流が持てていたら、彼は道を踏み外さなくてもすんだかもしれません。
言葉の力は、けっして名作や美しく上手な文章ばかりに宿るわけではありません。
素直な気持ちを言葉にのせて表現すること、それをただ受け止めてもらうこと、そこに癒しがあり、前を向く力を生むのだと感じます。
絵本セラピーの奥深さと無限の可能性にも、あらためて気づかされた一冊でした。