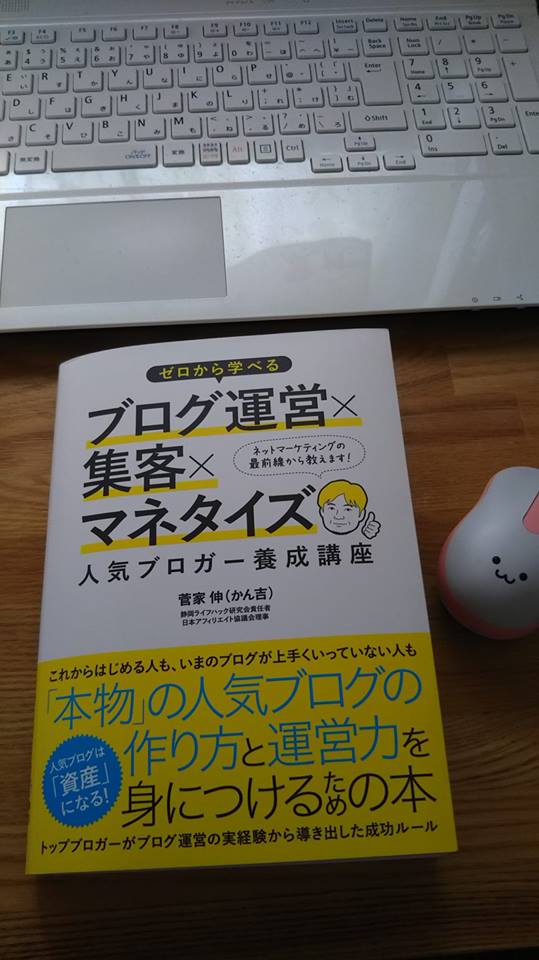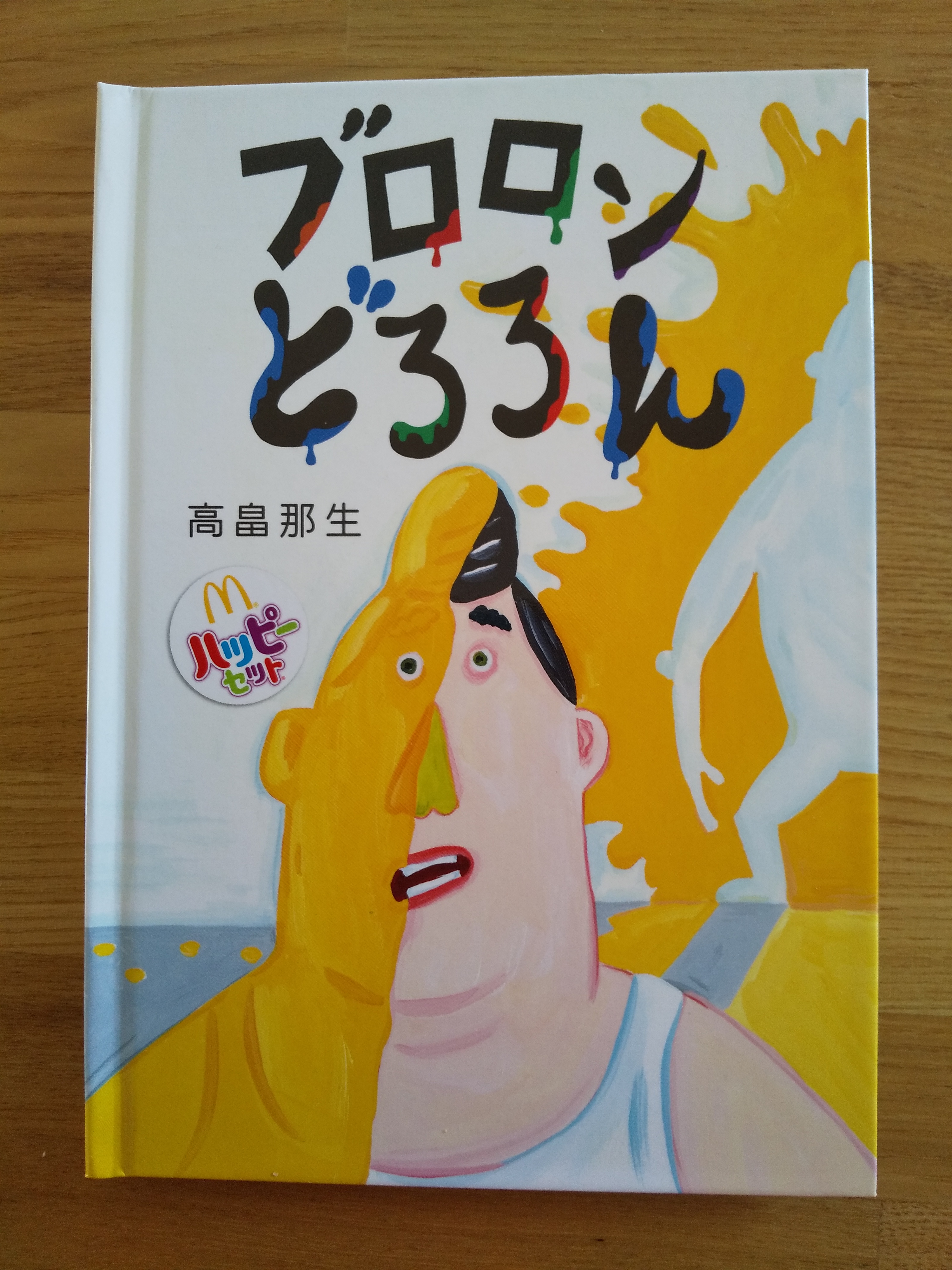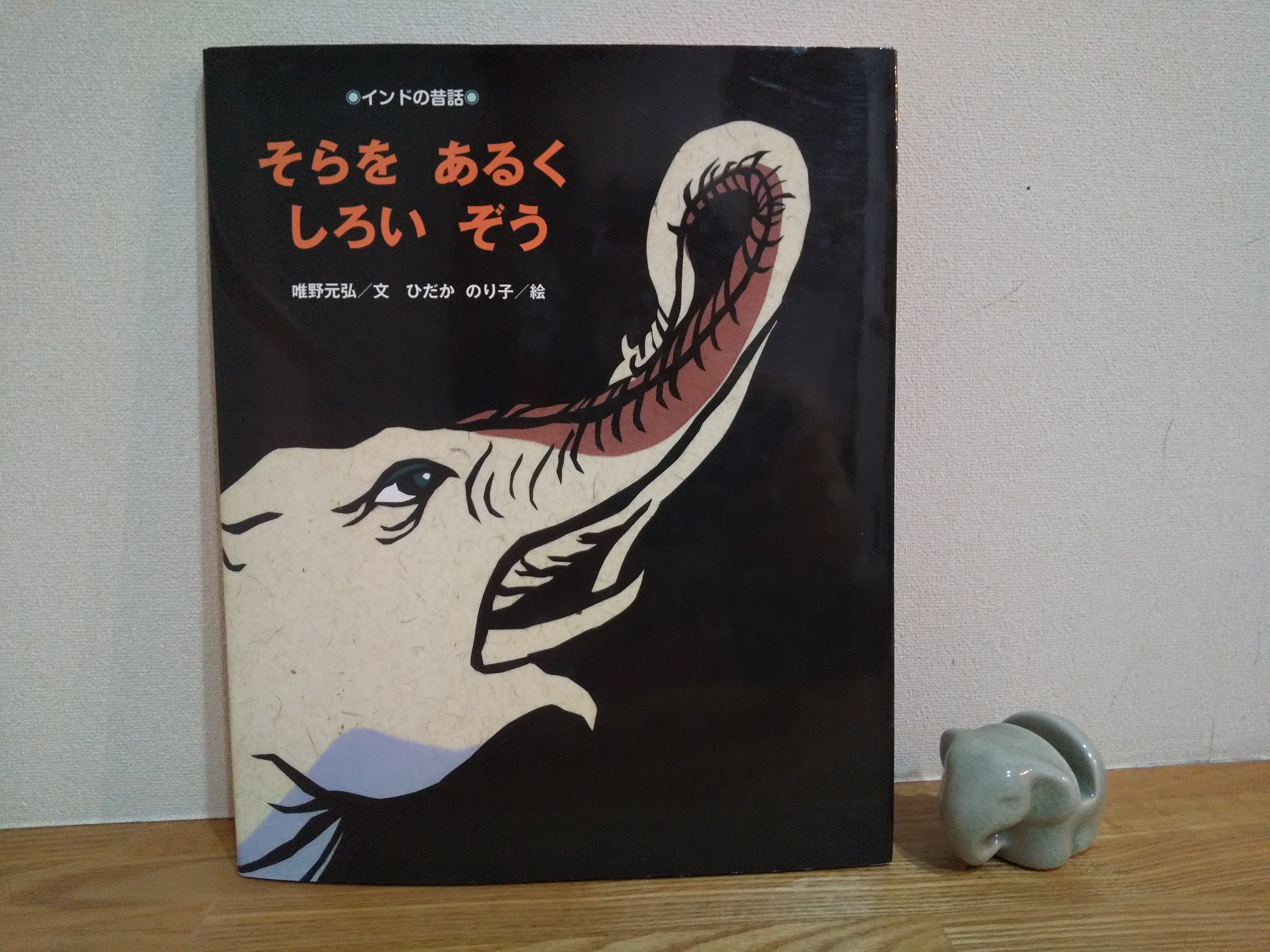「世界の子どもと本を考える」📖翻訳と絵本の限りない世界
11月12日、日本国際児童図書評議会(JBBY)が主催する、「世界の子どもと本を考える 『翻訳者が各国の作品を紹介するリレートーク』」に行ってきました。

JBBYは、最もすぐれた子どもの本の作り手を表彰する「国際アンデルセン賞」や、各国の優れた児童書の情報を世界に広める「IBBYオナーリスト」の選定などの活動を行っている国際児童図書評議会(IBBY)の日本支部です。
IBBYでは、2年に1度、各国から推薦された優れた児童書をまとめた「IBBYオナーリスト」を作成します。
今回、2018年のオナーリストの作品から、様々な言語の翻訳者の方が、おすすめの作品を解説してくださいました。

2回に分けて行われたうち、今回はスペイン語、チェコ語、ロシア語、フランス語、ペルシャ語の翻訳者の方が登壇。
まだ邦訳されていない貴重な作品を、歴史的、文化的バックグラウンド、国情、出版事情、翻訳の苦労話などを交えてお話しいただき、とても興味深かったです。
特に新鮮に感じたのは、スペイン語やフランス語などは、その国だけでなく、公用語としてその言語を使っている国がいくつもあるのだということ。
当たり前のことで、知識として知ってはいたのですが、翻訳者としての視点で考えると衝撃的なことでした。
私がたずさわっているタイ語は、基本的にタイの国でしか使われていません。
日本語もそうです。
しかし、スペイン語やフランス語は、ヨーロッパの中だけでなく、南米やアフリカでも公用語として使っている国があります。
それぞれ、歴史、民俗、文化が違い、移民、クーデター、奴隷貿易などの過去の出来事が伏線になっているものもあります。
翻訳をするときは、そういうことも熟知していないと、的確な訳出は難しいでしょう。
なんだか途方もなく、気が遠くなる思いがします。
また、今回、邦訳されていないすぐれた絵本にたくさん出会い、これも衝撃でした。
本当に美しいイラスト、毒のある引きずり込まれそうなストーリー、重いテーマ、力強い筆運びの絵・・・
どれも手元に置いてじっくり読みたいと思わせる作品でした。
日本国内で出版されている絵本、児童書だけでも、まだまだ全然読めていないのに、絵本の世界はこんなにも果てしないんだと知って、愕然としています。
翻訳の世界。絵本の世界。
とんでもない高みを見せつけられました。
私にはとても無理な領域?
今は、ね。
でも、大丈夫。人生100年時代ですから、まだまだ時間はあります。
今日もわくわくしながら、一歩を進めるだけ。
数年後には、あそこでタイ語の絵本を紹介する翻訳者になれるかな?
ブログランキング参加中です!クリックで応援よろしくお願いします♪