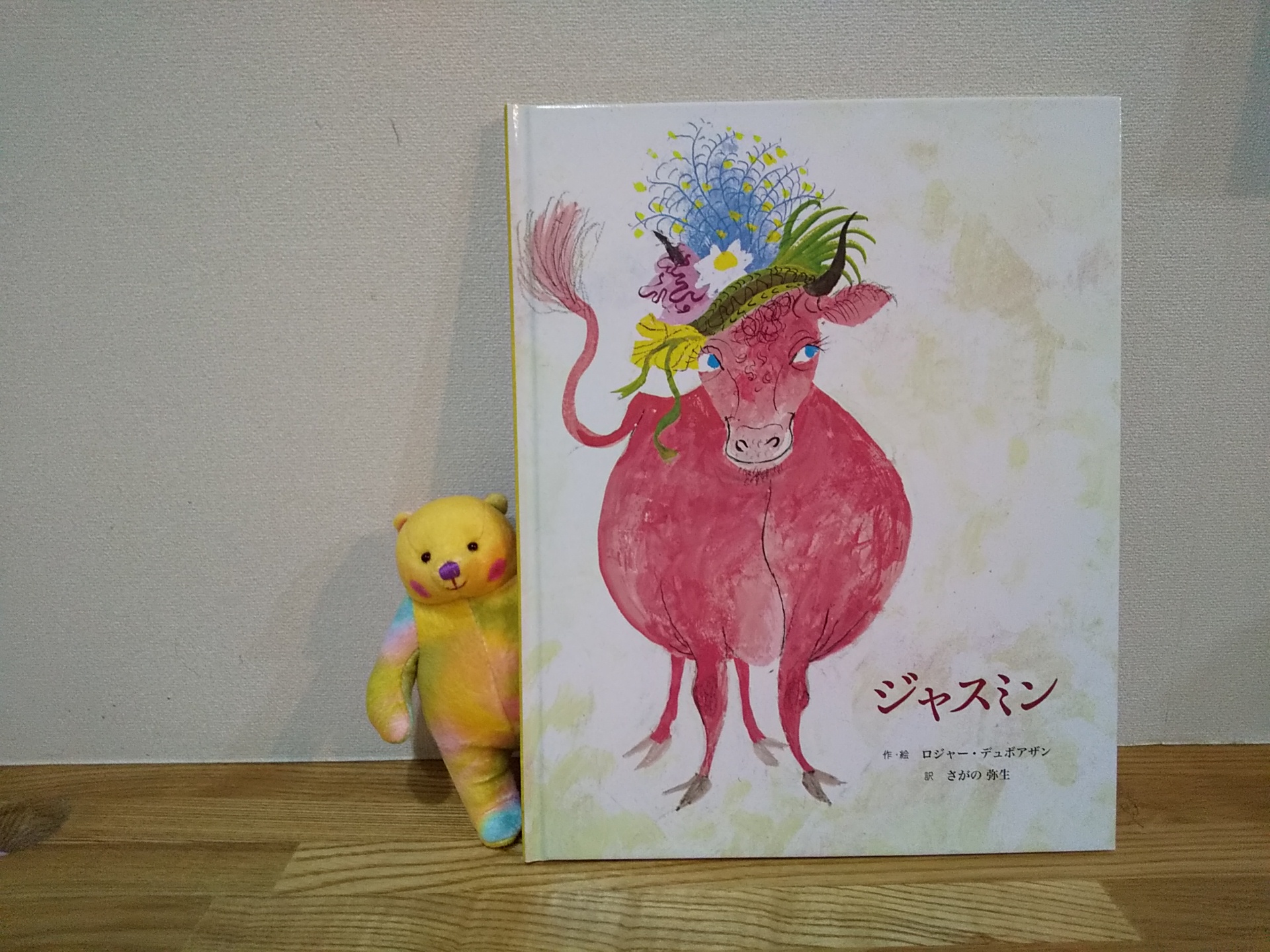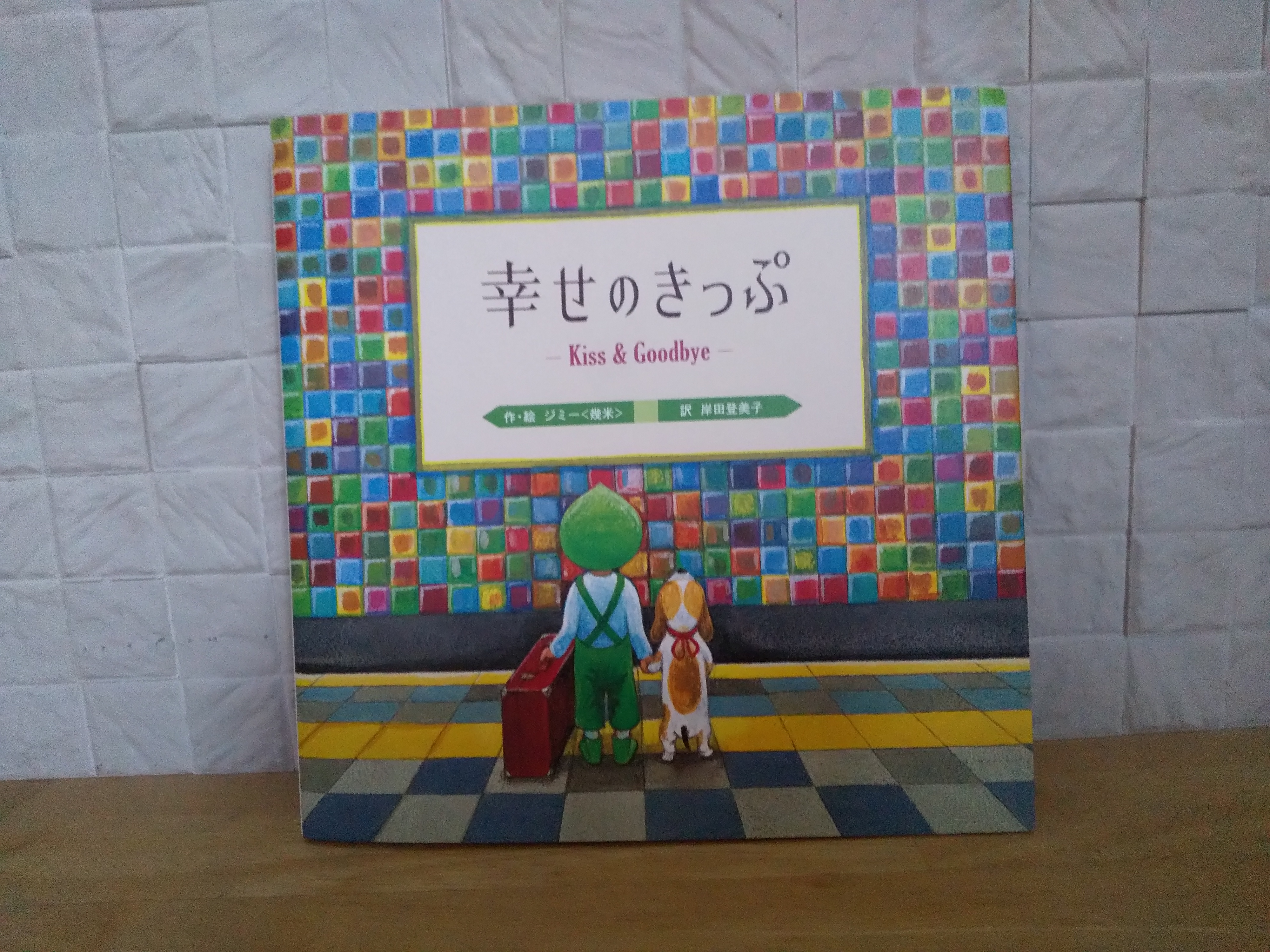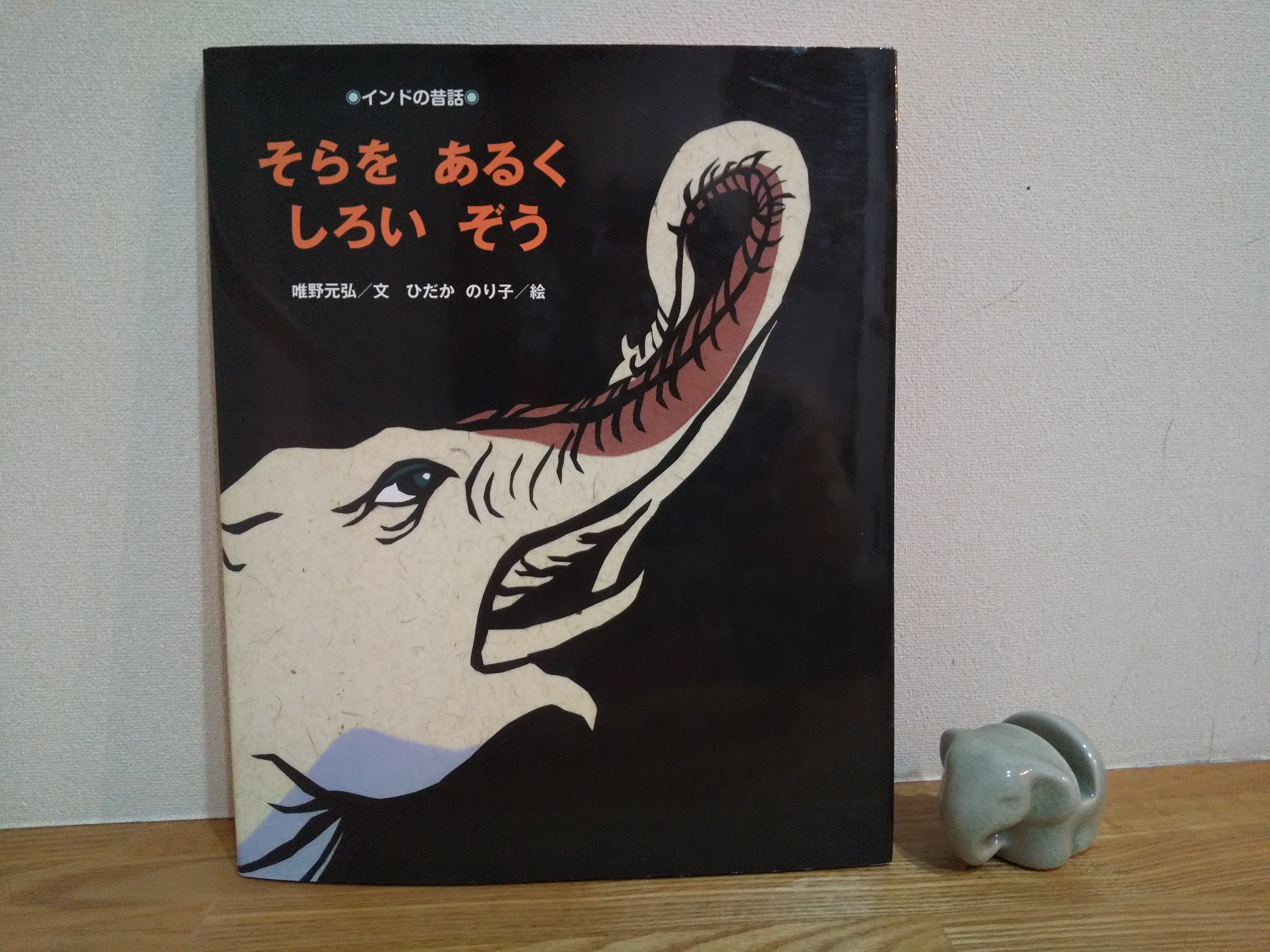「たべるたべるたべること」 絵本の中に見つけた懐かしいタイのもの
こんにちは!
大人に絵本を読んでいる、絵本セラピスト🄬らくちゃんです。
先月、オンラインで開催した絵本セラピー。
秋は実りの季節ということで、「たべるたべるたべること」(くすのきしげのり:作 小渕もも:絵 おむすび舎)という絵本を読みました。
日本の農村で育った女の子の成長を、「たべること」を通じて描いた作品。
「たべること」に、家族の豊かな時間や、命のつながりを感じます。
このしみじみと心にしみる絵本の中で、思いがけず「タイ」を見つけたので、ご紹介します。

どんなお話?
この表紙の女の子が、生まれ、成長し、母になるまでの、いろんなシーンの「たべること」が描かれています。
農村で生まれ育った女の子。
両親、祖父母とともに、「たべること」で祝い、ねぎらい、くつろぐ時を楽しみます。
幼稚園にやってきた新しいお友だちとも、「たべること」を通して仲良くなり、分かち合うことを知ります。
やがて成長し、実家を出て、会社勤めをするようになっても、「たべること」が彼女をささえています。
そして、愛をつたえ、絆を結び、新しい命をつなぐときにも、いつも「たべること」があるのです。
この絵本とタイ
嬉しそうにおむすびを口もとにはこぶ、男の子と女の子。
典型的な日本の農村、田んぼの景色、家族のだんらん、日本の食卓が描かれています。
ところが、この表紙の男の子は、タイからやってきた子らしいのです。
本文にはっきりとは書かれていませんが、インターネットの絵本紹介サイトに、出版社からの内容紹介として、「タイからやってきた友だち」とされています。
この絵を描かれたイラストレーターの小渕ももさんは、プロフィールを見ると「2004年から2008年までタイのチェンマイに住み、エイズの孤児施設で子どもたちと絵を描きながら創作活動をする。」と書かれていました。
この時期、ちょうど私もタイに住んでいました。
途端に、小渕ももさんに親近感がわいてきました。
きっと、現地で交流したタイの男の子たちのことを思って描いたんだろうなぁ・・・

表紙の男の子の髪型、タイの田舎の小学生によく見たスタイルです。
サイドと後頭部はごく短く刈り込んであって、頭頂部だけ微妙に長めのツーブロックみたいな。(画像が探せなかったのが残念)
絵の中のところどころに、懐かしいタイのものが見つけられます。
たとえば、幼稚園のお弁当や、運動会のシーンでみんなで囲むお弁当。
男の子が持っているのは、タイのもち米を入れる、竹で編んだ籠のような入れ物。
北タイや東北タイでよく使われています。

運動会のお弁当のシーンをよくよく見ると、男の子の両親とおぼしき人たち、日本のお弁当をわけてもらって、「ワイ」と言われる、手を胸の前で合わせたタイ式の挨拶をしています。

そして、成長して再会した二人。
黄色い僧衣を来たタイのお坊さんの前で、儀式を行うタイ式の結婚式の様子が描かれています。
物語には直接関係なく、文章にもタイということは書いてありませんが、描き手が込めた演出を見つけるのは、なかなか楽しいものです。
そんなところも、この絵本のもう一つの楽しみ方ではないでしょうか。
おむすび舎のこと
この絵本を出版しているのは、「おむすび舎」という、新潟県にある出版社です。
食育指導士として活動されていた霜鳥英梨さんが、絵本を使って食の大切さを伝えたい!と、2016年にお一人で立ち上げたそうです。
新潟といえば、米どころとして有名。

その地で生まれる食の絵本は、どれもまさに「心の栄養」となる素敵な作品ばかりです。
小学校の読み聞かせでも、時々読んでいますが、大人にも子どもにも、広く読んでもらいたいと思います。
この、「たべる たべる たべること」、私の持っている本に、作者のくすのきしげのり先生のサインをいただきました。

コロナ禍で、なかなかみんなで楽しく会食などができない状況になってしまいました。
しかし、せめてわが家の毎日の食卓は、「えがお」で心の栄養補給も忘れないようにしたいと思います。