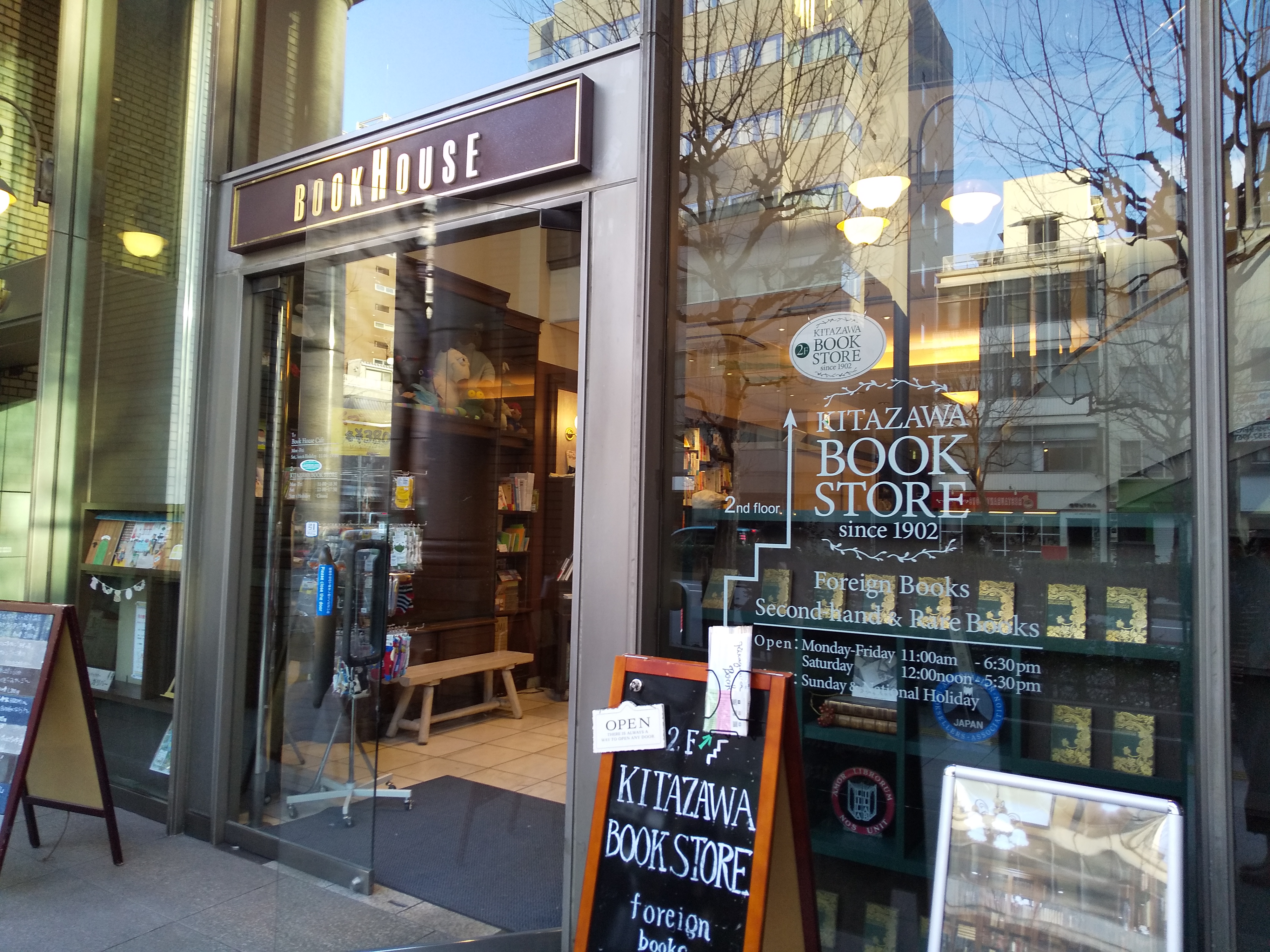一周忌のお墓参りは快晴でした
2018年12月14日、父が息を引き取りました。
奇しくも母の誕生日でした。
あれから1年。母と姉とオットと、お墓参りに行ってきました。
生前からの父の希望で、墓地も墓石も買わず、近所の霊園に永代供養にしています。
生まれ故郷ではないものの、終の棲家として愛したつくばの田舎の風景が広がる、こんなところに眠っています。
父は、数年前に心不全で救急車を呼び、一度心臓が停止したものの、お医者様や医療スタッフの方々の懸命な手当てで一命をとりとめました。
その後、心臓バイパス手術もし、糖尿病でもあったので、食事の前にインシュリン注射もし、何度もICUと普通病室を行ったり来たり、入退院も繰り返していました。
現代の医療技術のおかげで、寿命のろうそくを3~4年分継ぎ足してもらった感じですね。
戦中戦後の困難な時代を生きてきたとはいえ、思いきり仕事をし、家族を持ち、孫とも存分に遊ぶ時間もあり、80歳も過ぎていましたし、娘の目から見るとまずまず幸せな人生だったのではないかと思います。
父とはそれほど深い話をしたことはありませんが、不器用でありながら、善良で正直、勤勉な人でした。
その父の特長を、ある部分自分の中に受け継いでいるのかな、と思うことがふとあります。
そうやって、誰かに何らかの影響を与えていくことが、生きていくってことなのかな、なんて感じています。
最近、話題になっていた本をオーディオブックで聞きました。
「死」とは一体何か?を様々な視点から考察した本です。
といっても、脳死や生態反応などの医学的な死の定義ではなく、哲学的な考え方について、古今東西の哲学者や宗教の死の考え方から考察を加えています。
とても抽象的で、深遠な内容なのに、家事をしながら音声で聞いてしまったので、するりと耳から脳を上滑りしていった感じです。
つまらなかったとか、印象に残らなかったというのではなく、ところどころ立ち止まって考えてみたい概念があったので、今度ゆっくり紙の本で向き合ってみたいと思います。
ただ、いろいろと難しいことを考えたところで、この肉体をもってこの世界で活動できる時間には限りがあるということは確実。
本書の中でも、永遠の命があったら、という恐ろしい仮定をしていますがゾッとします。
限りがあるからこそ、面白いとも言えますね。
その制限時間をどう使うか?
制限時間内に何をしたか、自分をどこまで高めたか、周囲の人や社会、世界とどう関わったか、だと思うのです。
肉体が消えたあとも、すごい存在感をもって生き続ける人もいます。
生み出した作品や、業績、システムとして影響を与え続ける場合もあります。
さぁ、自分は持ち時間をどれだけ濃密に使えるか?何を残していけるのか?
墓碑の向こうに広がる青空を見ながら、そんなことをふと考えてしまいました。
ブログランキング参加中です!クリックで応援よろしくお願いします♪