初釜に思うこと
私は、裏千家の茶道を長年お稽古しています。
今日は、先生のお宅で初釜でした。
初釜というのは、先生と弟子がお正月を祝うお茶会です。

附下や訪問着などのお正月らしい華やかな着物を着て集まり、新年のご挨拶を交わしたら、炭手前から始まり、先生によるお濃茶、お食事、薄茶と楽しみます。
お食事は、お料理屋さんに初釜用のお弁当を頼む時もありますが、今年はみんなで持ち寄りました。
持ち寄りと言っても、一品一品心を込めて手作りしたり、この日のために探して求めてきたお料理を集めたご馳走です。

薄茶の干菓子には、干支のねずみが描かれています。

初釜では、例年同じ掛け軸、床飾りなどを使います。
通常、お茶席では季節やテーマに合わせて趣向を考え、それに沿った道具の組み合わせをします。
しかし、初釜だけは毎年変わらないことを良しとします。
今年も去年と変わらず元気に共に新年を祝えることを喜ぶ、という意味だと聞いてきました。
今まで、何年も「変わらないこと=無事」と捉えることに疑問を持たずにやってきました。
ところが、今年はこのことに自分自身やけに引っかかりました。
千利休が茶道を大成させたのは、戦国の世。
今日、ともにお茶をいただいた相手が、明日も生きているという保証はありませんでした。
だから、1年なんとか生きていて、また一緒にお正月を祝えることの意味、ありがたさは、現代とはくらべものにならないほど大きかったのだと思います。
また、変化を恐れる心理は、生物としてDNAに書き込まれたものという説もあります。
大昔、大きな体や鋭い牙も持たず、空を飛ぶ翼も速く走る足も持たない人間にとって、外の世界は危険に満ちていました。
とりあえず今生きているのだから、死なないためには「今までどおり」が一番安心。
いつもと違うことをしたら、知らない場所に行ったら、致死的な危険があるかもしれません。
だから、必要最低限しか動かないでおこう・・・と本能が設定されているらしいのです。
しかし、今はいつもと違うところに行っても、いきなり猛獣に出くわすことはありません。
現代は、変化が必ずしもマイナスではなくなりました。
それどころか、イノベーション、改革、成長等々、変化を求める動きが多くなっています。
そんな時代に、初釜の「毎年変わらないしつらえ」は、何を教えてくれているのでしょうか。
私は、変ってはいけない本質、変化の波に飲み込まれ、見失ってはいけない真理ではないかと思うのです。
昨今、イノベーションと並行して、SDGsという取り組みが注目されています。
Sustainable Development Goals 持続可能な開発目標ということです。

持続可能というと、環境問題やエネルギー問題を想起しますが、SDGsでは、飢餓や貧困、ジェンダー、差別、教育、保健衛生や都市開発、生産など多岐にわたるアジェンダで取り組みを行っているそうです。
時代は、変らないことを「無事でよかった」ということから、持続、継続を積極的な決意として取り組んでいくフェーズに入ったのではないでしょうか。
ブログランキング参加中です!クリックで応援よろしくお願いします♪



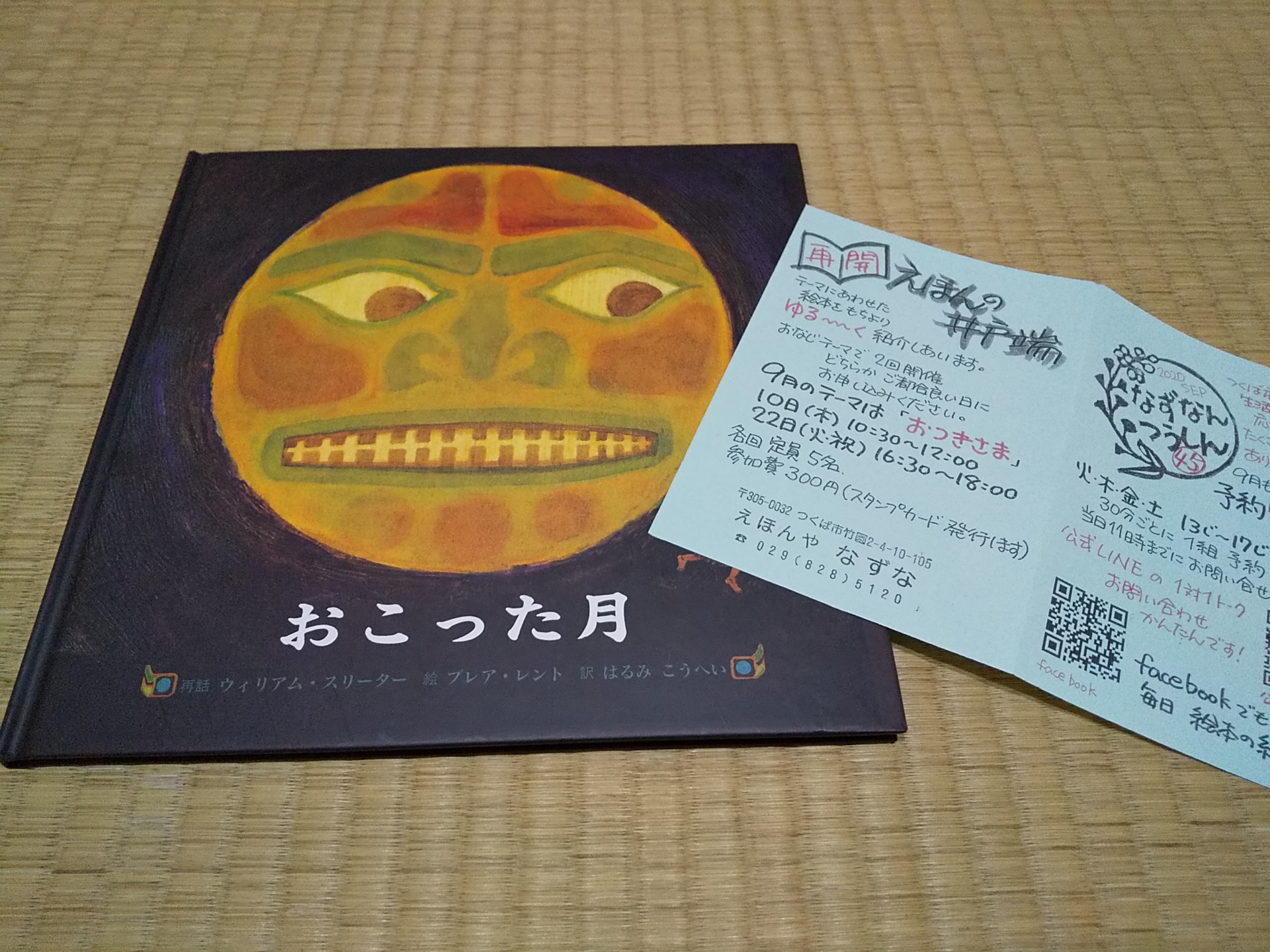
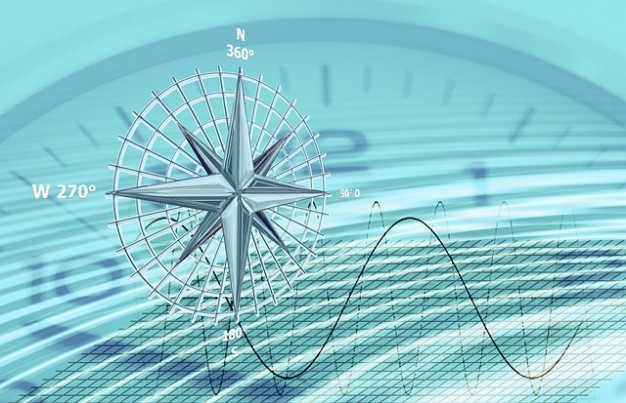
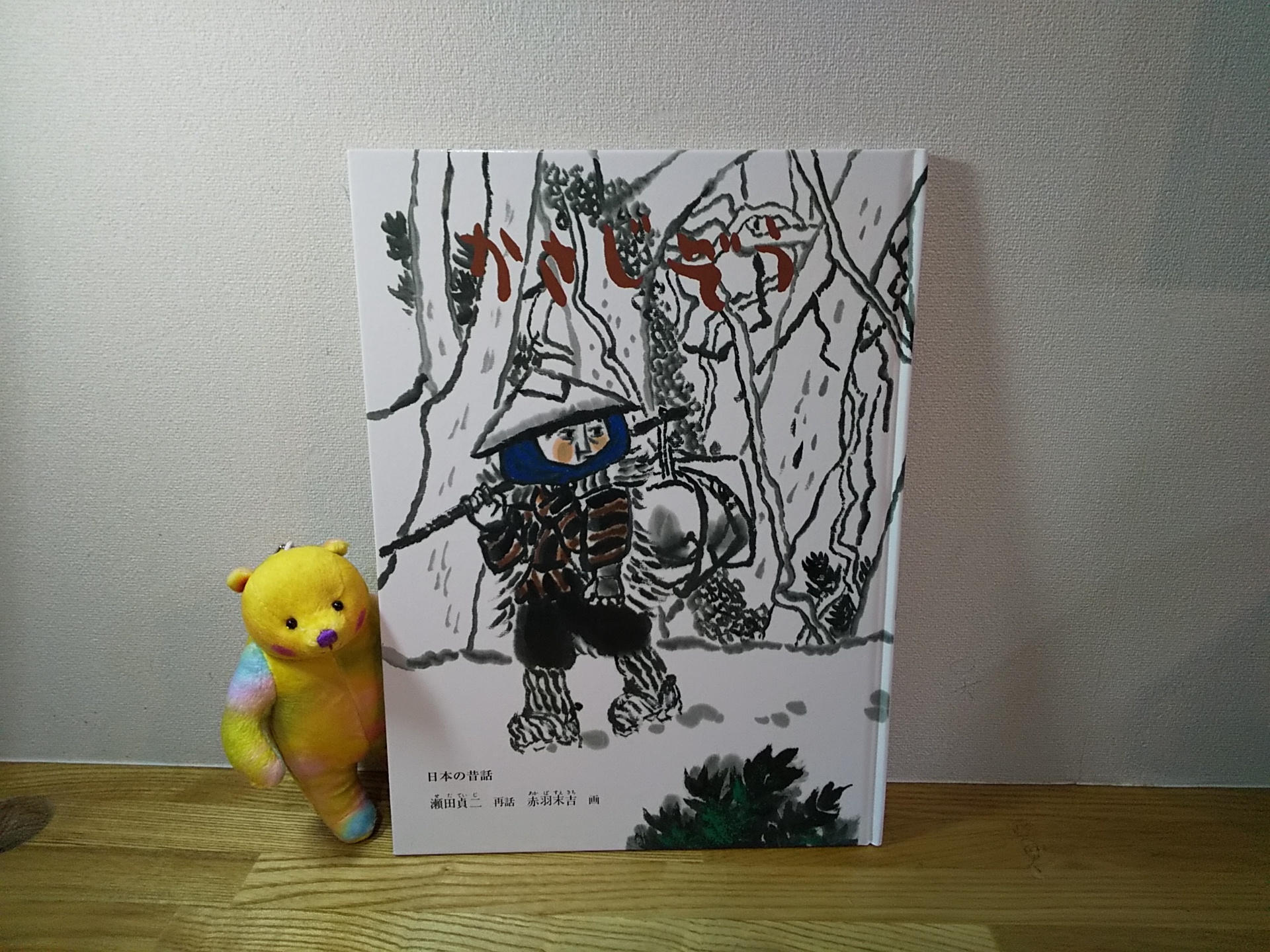
_190630_0047.jpg)
