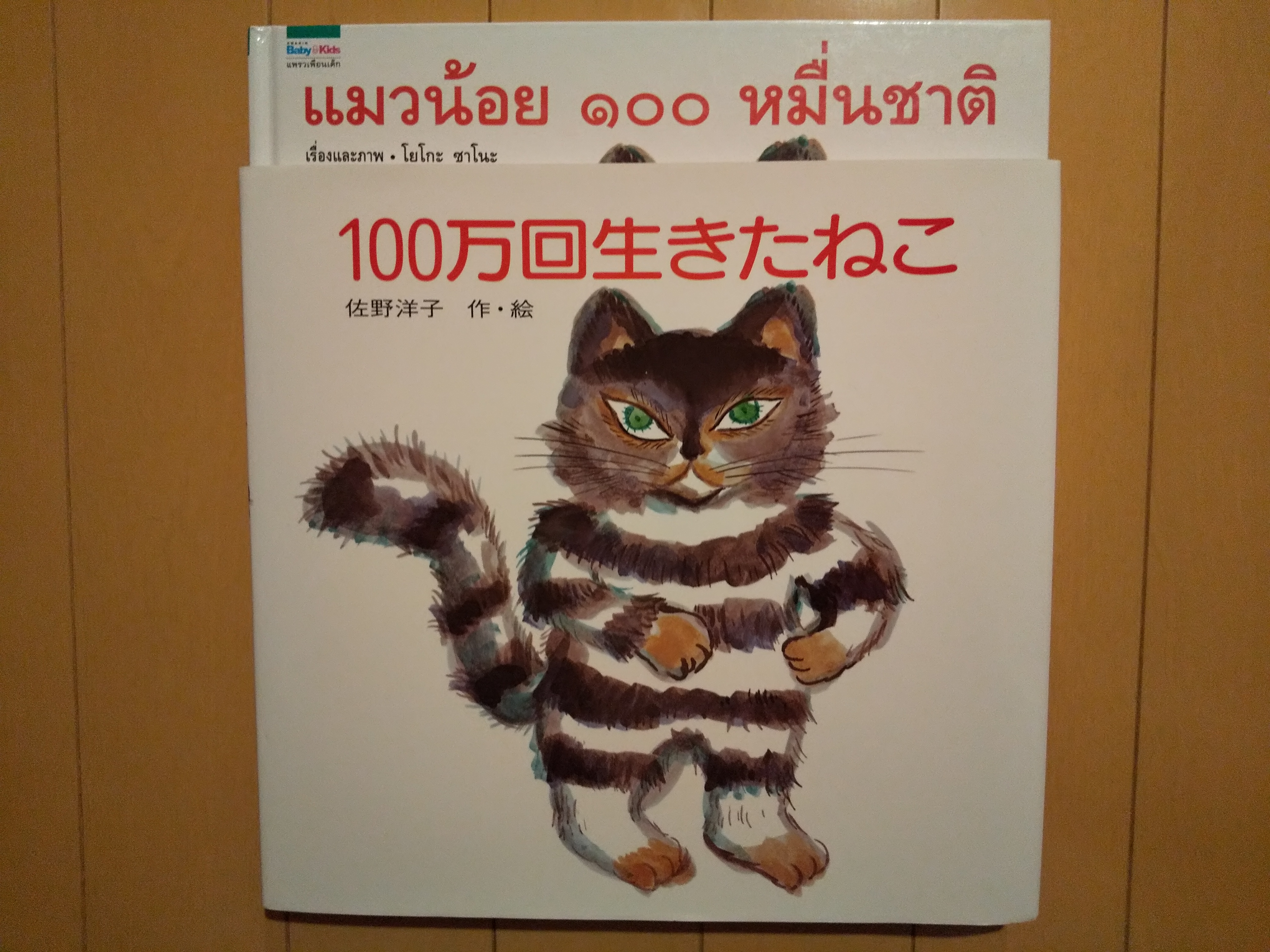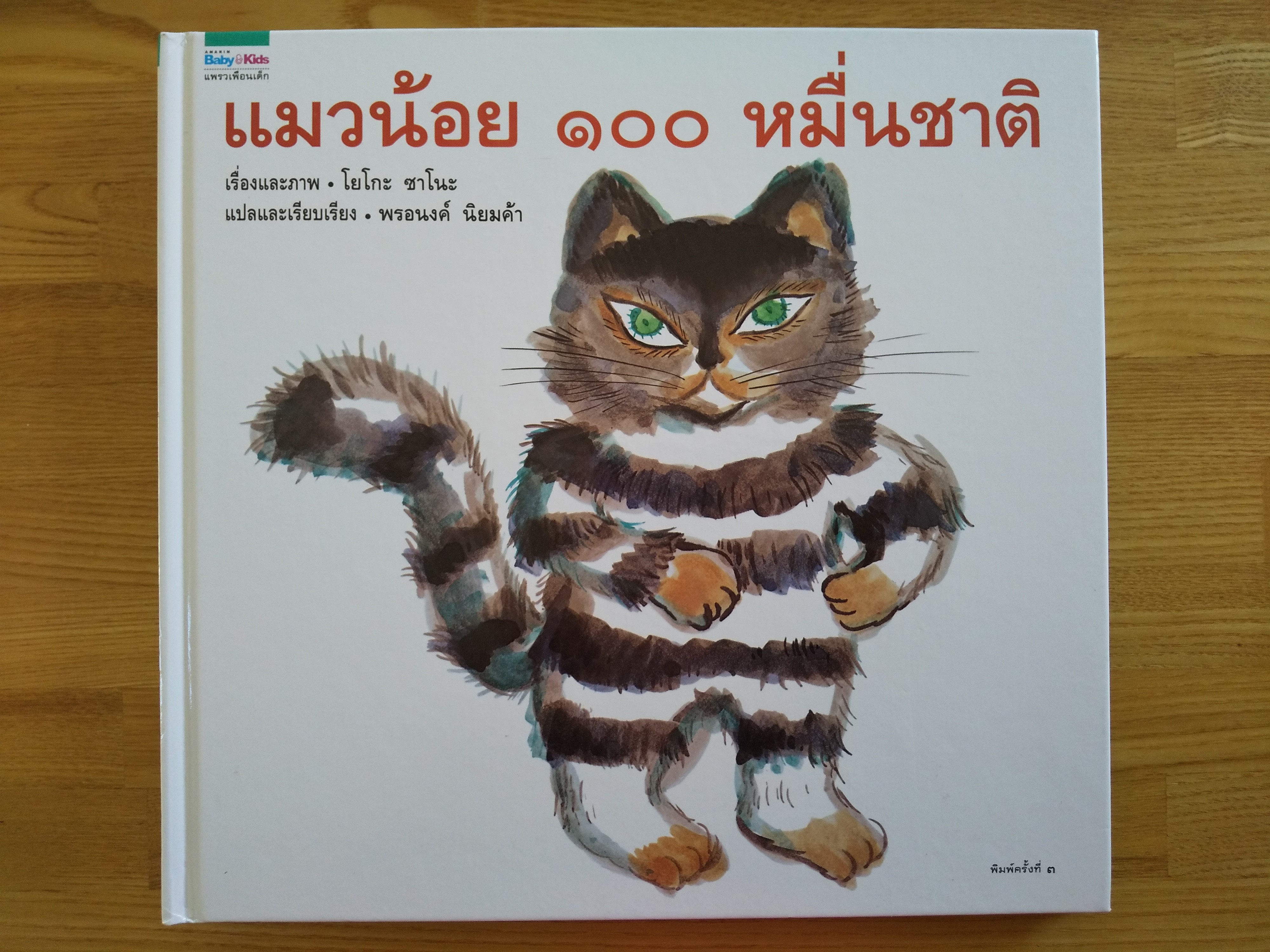タイトル翻訳の難しさ
先日参加した「旅する読書」という講座で、有名な絵本「かいじゅうたちのいるところ」(モーリス・センダック著、じんぐうてるお訳)が取り上げられました。
うちにもあって、息子たちも一時期はまって、何度も何度も読み聞かせてあげた作品ですが、今回初めて原作のタイトルが「Where the wild things are」だと知りました。
実は、この訳の出版の10年ほど前に、「いるいる おばけがすんでいる」という訳で出版されていたものがあったとか。
古い方は、何人かがチームで翻訳したもので、その中には三島由紀夫の名前も!訳文も七五調で時代を感じさせる趣があります。
新訳の方がなじみはありますが、人によってはこのタイトルはよくないと批判もあるとか。
wild thingsは、かいじゅう?おばけ?
ちなみに、気になってタイ語の訳語もネットで探してみました。
絵本の翻訳本は見つかりませんでしたが、映画の翻訳はあり、“ดินแดนแห่งเจ้าตัวร้าย” モンスターのようなニュアンス。
いよいよ原作から離れてしまったような気が・・・
主人公はマックスという男の子。wild things=野生のもの、これは子供の自由で、やんちゃで、まさにワイルドな本質を表したものではないでしょうか。
子育てをしたことがある人は覚えがあると思いますが、2~3歳の頃を「かいじゅう」と言うことがあります。
自己主張が激しくなり、気に入らないとひっくり返ってぎゃん泣きして、まったく手に負えない時期。
だから、子供の心、本性に潜む、手を焼く愛しい「かいじゅう」を知っていると、この訳には私は違和感がありません。
タイトルの翻訳ということが気になって、手元にある本をいくつか見てみました。
大好きな絵本、「おおきな木」(シェル・シルヴァスタイン作、村上春樹訳)の原作は、「The giving tree」。
内容はまさに「The giving tree」なのですが、「与える木」とはしなかったのですね。
この村上春樹訳の出る25年ほど前に、本田錦一郎氏の訳で出ていますが、その時もやはり「おおきな木」と訳されています。その訳を踏襲されたのでしょうか。
また、その村上春樹のエッセー、「走ることについて語るときに 僕のかたること」の英訳は「What I talk about when I talk about running」。
ただし、これは村上春樹が米国人の作家レイモンドカーヴァーの短編集のタイトルを原型としているので、英語にするのは原型に戻すだけみたいなもの。
そのタイ語訳が手元にあるのですが、これがちょっといただけない。
เกร็ดความคิดบนก้าววิ่ง 走る歩上の思考の断片、といったところか。
内容からはずれたものではないけれど、原作、英語版の言葉のリズムは失われてしまってますね。
それと、世界中でベストセラーになっているという、こんまりさんの「人生がときめく片づけの魔法」。
これは「たった一回の片づけで、あらゆる面で人生が上向きに」という訳。
間違いじゃないけど、「ときめく」「魔法」といった、こんまりちゃんならではの、乙女な感じが消えてしまった・・・
今まで、産業翻訳しかやってこなかったので、直訳でほぼよかったのですが、こういう文学や絵本などは、それが正解というのも言えないし、ニュアンスが難しいですね。
特にタイトルは、作品の第一印象を決めるだけに、悩みますよね。