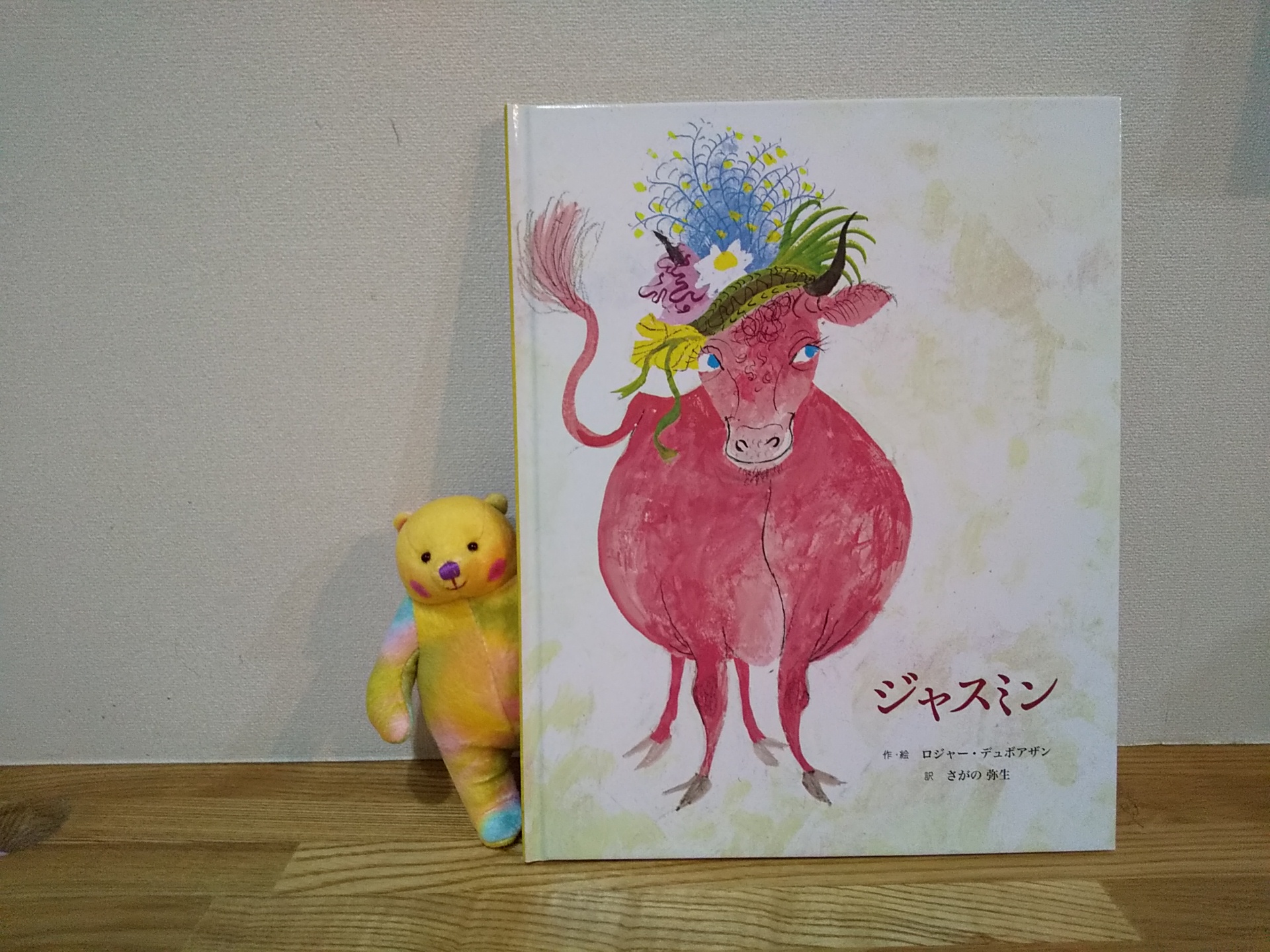「馬ぬすびと」と太田大八
「馬ぬすびと」という本を読みました。
1968年刊行の半世紀以上読み継がれてきた作品です。
鎌倉時代、九郎次という馬ぬすびとが、由比ガ浜で打ち首になったという古文書の記録から創作された歴史物語です。
児童書ですが、読者を子ども扱いしない、生き方や価値観を真正面から問いかけるような骨太の作品。
時代や政治の状況、立場によって全く変わってしまう不確かなものがあります。
その中で、揺るぎのない自分の信じる正義、幸せな暮らし、大切なものを追い求めた、壮絶な馬ぬすびとの生き様は、現代を生きる私たちにも考えさせられるものがあります。
ところでこの作品、物語もいいのですが、挿絵に目をうばわれます。
歴史絵巻のような迫力と味わいがあり、思わず見入ってしまいました。
この挿絵を描いたのが、太田大八氏。
絵本や本の挿絵で、多くの作品を残した大御所と言っていいでしょう。
と言いつつ、実は今まであまりよく知りませんでした。
子供に絵本を読み聞かせてきたものの、特に絵本作家や絵本画家に注目して作品を選んだり、勉強したりしたことはなかったのです。
昨年から絵本セラピーの勉強を始め、古典的な名作や有名な作家、画家のことを講座の中などで学ぶようになったばかり。
まだまだ知識はとぼしく、お恥ずかしい限り。
太田大八さんの名前も、「よく見る名前だから、有名な人だろうな~、うちにまだ何冊かあったよね~」という感じ。
この機会に、うちにある太田大八作品を集めてみて、プロフィールも調べてみました。
まっさきに思い浮かぶのは、昔話系の絵本です。

「天人女房」「炭焼長者」「はなたれこぞうさま」「はなさかじい」「がまどん さるどん」
これらも、読者を子ども扱いしない絵本です。
語りは方言だし、絵はしぶいのですが、なぜか子供たちは結構気に入っていました。
日本の昔ばなしは、もっとわかりやすい言葉で、挿絵もアニメのようなかわいい絵のシリーズも持っていましたし、図書館で借りてきて読んだりもしましたが、なぜか手元に残っているのはこれらでした。
そして、一番よく読んだのが「あおい玉 あかい玉 しろい玉」(稲田和子:再話 太田大八:絵 童話館出版)。
学校の読み聞かせでも、秋は必ずこれを読んでいます。
三枚のおふだと同じストーリー展開の昔話ですが、やまんばに追いかけられ、必死で小僧が逃げるところは、子供たちもハラハラドキドキするようです。
昔話絵本のしぶい絵を描いている人というイメージでしたが、こんな本も太田大八さんでした。

「ともだち」は、文、絵とも太田大八さん。
これも大好きな一冊で、高学年の進級前や卒業前の読み聞かせによく読んでいました。
昔話の絵とかなりタッチが違うので、気がつきませんでした。
もう一冊の「二分間の冒険」は、岡田淳:作の児童文学ですが、挿絵が太田大八さん。
こちらは細かいペン画のようなタッチで、また全然雰囲気が違います。
本当に、いろんな画風の絵が描ける人なんですね。
調べてみたら、太田さん、1949年のデビューから2016年に98歳で亡くなるまで、130冊以上の絵本と230冊以上の児童書などの挿絵を手がけられたとか。
創作に対するすごいパワーと情熱を感じます。
太田さんは、長崎県の出身で、広島で今一歩のところで原爆の被爆を逃れ、九死に一生を得ました。
戦争による修羅場を見た体験、生かされた自分の命を最大限燃焼させるような、90歳を過ぎてもなお枯れることを知らない創作への意欲と、生み出した多くの作品。
「だるまちゃんとてんぐちゃん」の加古里子さん、「アンパンマン」のやなせたかしさん、「ゲゲゲの鬼太郎」の水木しげるさんのことを思い出しました。
これらの素晴らしい作品を、私たちは大事に読み継いでいかないといけませんね。
ブログランキング参加中です!クリックで応援よろしくお願いします♪