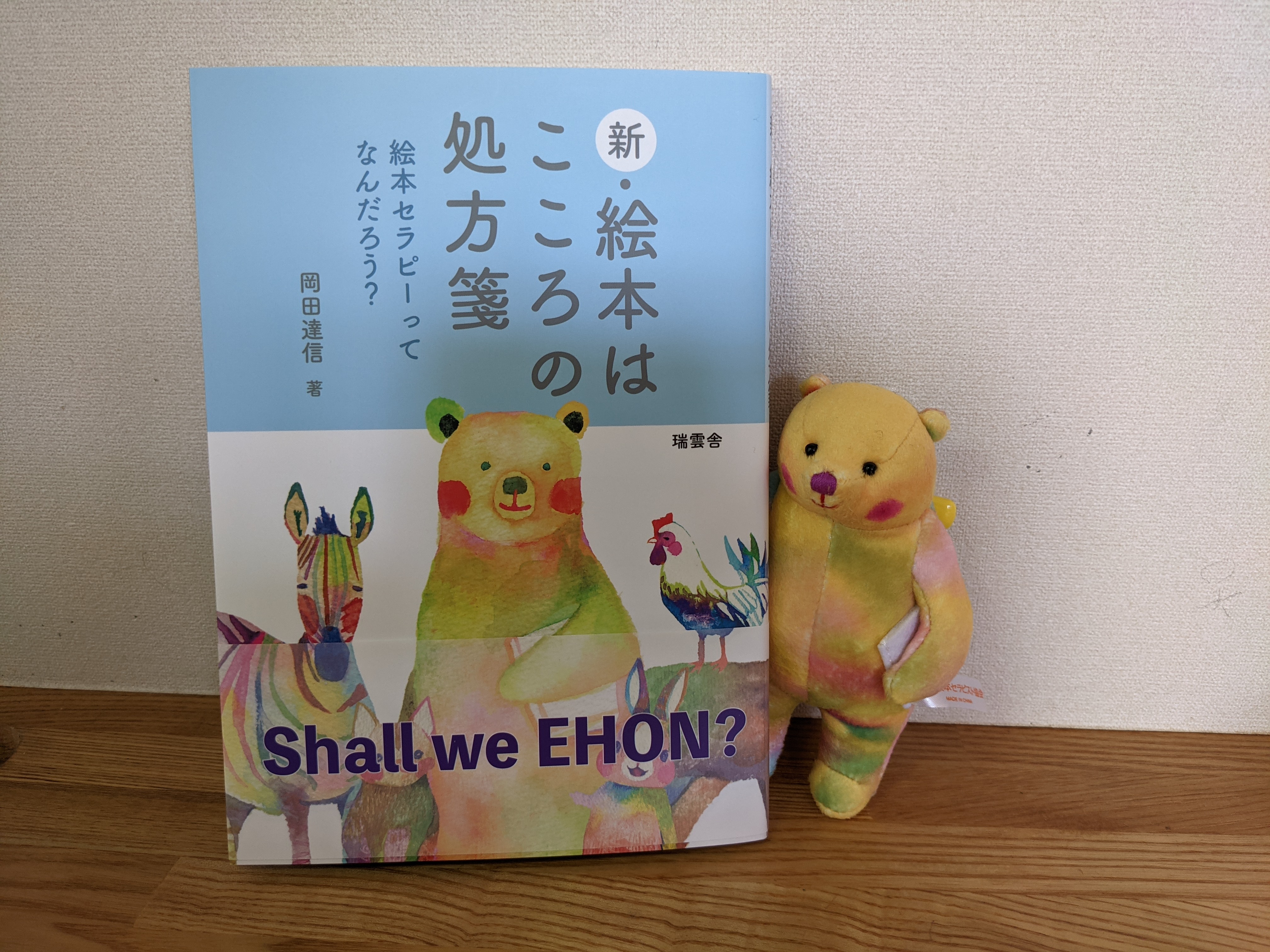石田勝紀著「同じ勉強をしていて、なぜ差がつくのか?」を読みました
オットがトヨタに車の相談に行くというので、くっついて行きました。
約束の時間よりかなり早く着きそうだったので、時間調整に立ち寄ったTSUTAYA BOOKSで、ついこんな本を衝動買い。
コロナ騒ぎで気もそぞろながら、この1ヶ月ほど長男の塾選びに頭を悩ませていたからでしょうか。
ただ、うちの息子は、勉強をしていないので、「なぜ差がつくのか?」なんて図々しいことは思っていませんけどね。
それに、私はそれほど偏差値とか、テストの点数とか、順位とか、偏差値の高い大学とかにはこだわっていません。
でも、本当に頭のいい人、パフォーマンスの高い人、結果を出す人、目標を達成できる人はどんな人なのか?ということには、とてもとても興味があります。
それで、この本をつい手に取ってしまったわけですが、本書を読んでわかった結論は、ひとことで言うと、
「OS(オペレーションシステム)が違う」ということです。
この言葉、原田隆史先生もよく言います。
教育には、A型教育とB型教育の2つのタイプがあり、昭和の高度経済成長期からインターネットが普及するまでは、人は主にA型の教育を受けてきました。
いわゆる暗記中心で、努力と根性で参考書を暗記して、テストでいい点を取り、いい大学、いい会社に入れば安泰。
工業製品のように、平均してクオリティを揃えた人材を育てることを目指した教育でした。
一方、B型教育は、学びあい、教え合い、答えの一つではない問題に取り組んだり、膨大なインターネットの情報から意味あるものを抽出し、編集したり、価値を創造したりする能力を育成するもの。
求められる能力、教育のあり方が全く変わってしまったのだから、OSチェンジしなければ、と。
誰もがスマホを持ち、常時インターネットに接続し、AIが身近なものにも組み込まれている現代、暗記中心の学習で点数を取ることに意味はありません。
だからB型の教育をし、B型の考え方で学ばなければいけないのに、A型の教育しか知らない教師や親に育てられた子は、当然その旧式OSをインストールされ、努力と根性でがんばっても、新しいOSの子には太刀打ちできないというわけです。
ただ、本書では、その残念な旧式OSの子も、周囲の声かけで、少しずつOSをアップグレードしていけるとのことなのです。
OSの正体とは、「考える力」のことだと著者は言います。
暗記したものを必死で穴埋めしたり、選択問題から選んだりするのではなく、全体をつかんでから細部に下りてこられる視点、逆に細部から全体を編集できる能力。
なぜ?と問いを立てる力。
どうしたらいい?と考える問題解決力。
要するに、とまとめられる能力。
何のために?という目的意識。
こういう問いかけを、根気よく続けていくことで、次第に考える習慣、くせづけができてくるそうです。
とはいえ、やみくもに「よく考えなさい」と言っても、考える習慣がない古いOSの子には、考え方がわからずフリーズしてしまうもの。
その子の段階に応じた問いかけも必要です。
本書の中には、その問いかけを「10のマジックワード」として紹介しています。
嬉しいのは、子供に問いかける場合と、会社で部下に問いかける場合の例が書いてあることです。
教育は、いまや子供だけに施されるものではありません。
旧式のOSをインストールしてしまっているおとなこそ、OSのアップグレードが急務です。
私も、自分の受けてきた教育、今までの思考回路や態度は、まったく旧式OSだと痛感します。
そこに気がついたら、「今すぐアップグレードする」をクリック。
上記のマジックワードは、子供に対して問いかけるために書かれていますが、自分自身に問いかけることで、自分の思考訓練にもなります。
日常の中で、ニュースを見たとき、本を読んだとき、誰かと会話したとき、問いを立てる習慣を持つことで、ずいぶん頭の働き、見える世界が変わってきます。
ところで、この本の要点は、できる子とそうでない子の違いは、頭のOSのスペックが違うということと、そのスペックをあげるためのマジックワードの紹介でした。
しかし、私は「おわりに」に書かれていた著者の言葉にハッとしました。
「頭のOSのスペックを上げることで、どのような世界が生まれるのか?」ということに、3つのベネフィットを挙げています。
その中の一つに、「争いやいじめがなくなる」というものがありました。
いささか唐突なような気がしますが、頭のOSのスペックが高い人=抽象度の高い考え方ができる人は、高い次元からものごとを見るため、個々の違いは認識してもその差を差別したり排除したりしない、ということなのです。
抽象度のことについては、本書に詳しく書かれていますが、イヌを例にとると、
具体的・低次元=チワワ、柴犬、プードル、ダックスフント、ゴールデンリトリバーなど
抽象的・高次元=犬、ほ乳類、動物、生き物など
具体的な次元では、とかく違いを比較して、争いやねたみ、いじめ、仲間外れに走りやすいものです。
しかし、抽象的な視点で見ると、どれもイヌであり、違いはただの特徴や個性でしかありません。
この「違いを認めて、対立しない」というのは、絵本セラピーを学ぶ講座では、いつも言われることです。
同じ絵本を、同じ人から同じ時間に同じ場所で聞いたのに、感じることは人それぞれ。
それって、面白いよね。
そんなふうに絵本セラピーは、「絵本で世界平和」を目指します。
へぇ~、時間調整で立ち寄った本屋で衝動買いした本が、ここにつながったか、という感じです。
これも、意味のある引き寄せだったのかもしれません。
ブログランキング参加中です!クリックで応援よろしくお願いします♪