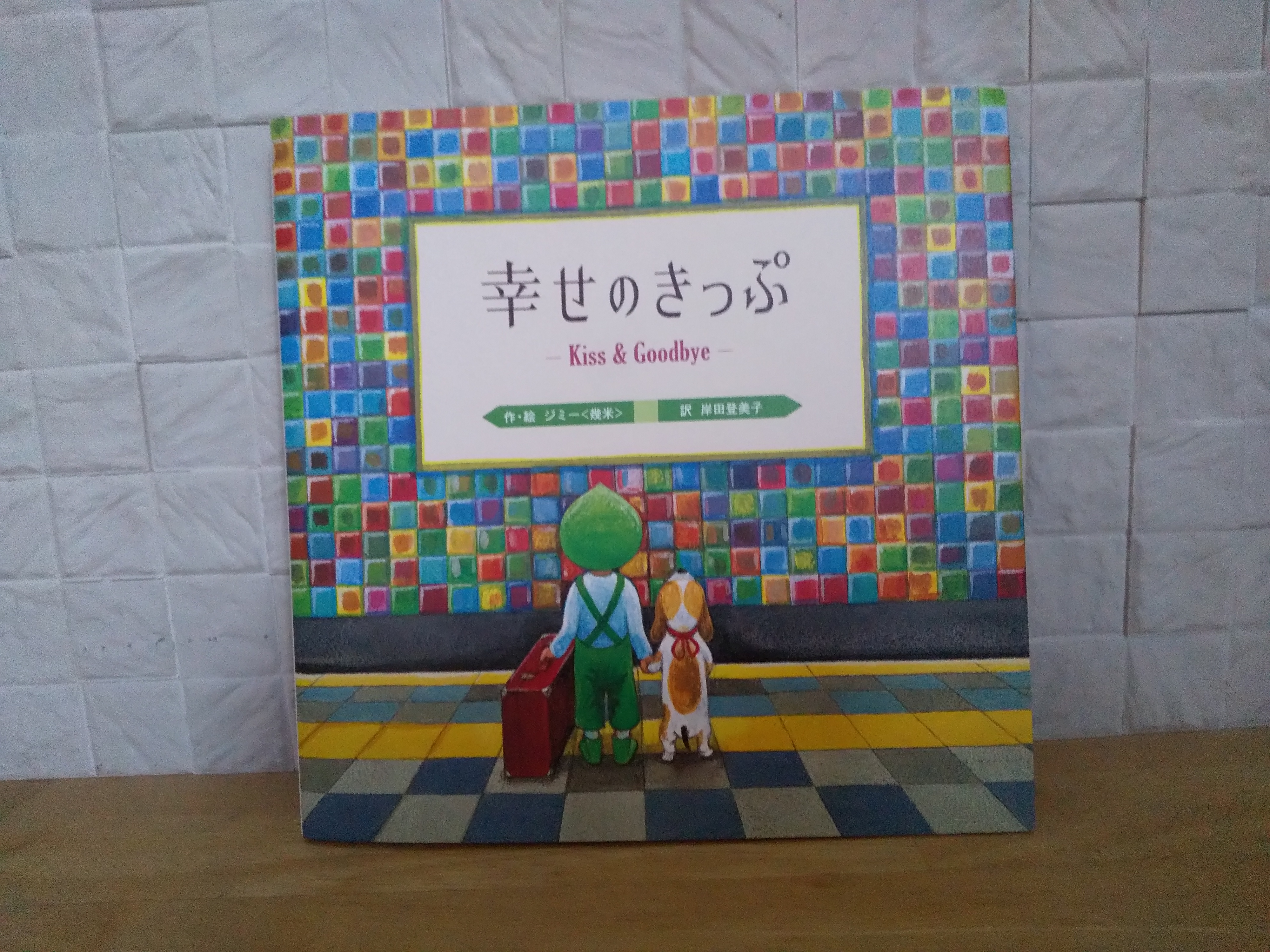これから必要なもの、「生きる力、絵本の力」
こんにちは!絵本セラピスト🄬のらくちゃんです。
「積読(つんどく)本」の山が結構高くなっているのに、ついついAmazonの森をふらふらしては、ポチっとしてしまいます。
今回届いたのは、ノンフィクション作家柳田邦男氏のこの本です。
「絵本はどのように人生を豊かにし、いのちを育む力を与えてくれるのか。
読み手の年齢や状況によって、受け取るものは異なり、人生経験を経るほど、深い意味を発見することができるというところに絵本の秘められた可能性がある。
その可能性について、心の危機、人生の危機に直面した時、絵本によって生き直す力を取り戻した人々のエピソードに寄り添いながら語ろうと思う。」(本文より引用)
この言葉のとおり、本書には、絵本を介して人々が受け取ったものや気づいたことなどにまつわる、珠玉のエピソードが散りばめられています。
絵本というものは、物語を通じて、何かを受け取るばかりではありません。
2011年の東日本大震災の後、被災者の方が自ら絵本を描くことで、事実を受け止め、傷をいやし、再生していくエピソードがありました。
心が揺さぶられました。
物語を介することで、人の心にはいったいどのような作用が起きるのでしょう。
私自身、絵本を読む中で、確かなことをつかんでいるわけではありませんが、絵本をきっかけに人の心に化学反応のようなものが起きる場面に立ち合うことがありました。
特に、大人の場合に、その化学反応は顕著です。
子どもは、物語をそのまま体験すると言います。
しかし、大人はそうではないんですよね。
柳田氏は、このように言っています。
「絵本は、生きることや人生や対人関係やいのちについて、基本的に大事なことを忍ばせている表現ジャンルなのだ。
人生経験を積むほどに、絵本が秘めている深いかたりかけに気づいていくものだ。
人生で大事なことは、すべて絵本から学べると言ってよい。」(本書あとがきより)
まさにそうだなぁと、思います。
さらに言うと、「絵本が秘めている深いかたりかけ」は、その人の経験した人生、価値観、観念、思い込み、親の価値観、生育環境などによって、全く違ったりするということを、絵本セラピーの中で学びました。
同じ絵本を読んでもらっても、受け取るメッセージが人によって違う。
そこに良いも悪いも、正解、不正解もありません。
たとえば、今まで何度か読んできた「おおきな木」という絵本があります。
英語の原題は「THE GIVING TREE」。
その名のごとく、表紙の絵にある少年に、すべてを与え続ける木のお話です。
「木」は、少年のことが大好きでした。
少年も「木」が大好きで、いつも木のぼりをしたり、葉っぱを集めてかんむりを作ったり、りんごをとって食べたり、木陰で眠ったりしました。
しかし、少年は成長するにしたがって、要求するものが変わってきます。
そのたびに、「木」は枝を切らせ、幹を切らせます。
最後に古い切り株となった「木」は、すでに老人となった「少年」を座らせ、休ませます。
それで「木」は幸せでした・・・

最初に、小学校の読み聞かせで読んだ時、教室の後ろで聞いていた先生が、目を潤ませながら「すごくよかったです。僕、この本買います!」と言ってくださいました。
まだ結婚されて間もない、若い男の先生でした。
ひたすら無償でつくす「木」の、愛の深さに感動されたとおっしゃっていました。
その後、絵本セラピーで、子育て中のお母さんに読みました。
あるお母さんは、「私は、わが子にもここまではできないなぁ、と思っちゃった」と。
また別のお母さんは、「この本は大好きな本だったけど、読むたびに印象が変わる。読んでもらうと、また感じが違っておもしろかった」とおっしゃっていました。
要求するばかりのこの「少年」に、腹を立てる方もいらっしゃいました。
どんな姿になっても、できることってあるもんだな、という気づきを得られた方も。
一冊の絵本から受け取ることって、本当に千差万別。それでいいのです。
ところで、今回注文していた本書が届いて、封を開けてハッとしました。
本についていた帯に、こんな言葉が。

「このたいへんな時代に 大人も子どもも 絵本で心に潤いを!」
2014年1月発行の本ですから、当然新型コロナウィルスによるこの状況は予想もされていない時に、書かれた帯です。
東日本大震災で受けた傷も生々しく、復興もまだ始まったばかりの「たいへんな時代」ではありました。
柳田氏が本書の中で言及している「たいへんな時代」とは、経済的危機、格差社会、地方のまち・むらの崩壊、貧困層の拡大、高い失業率、行き詰る高齢者医療・福祉、等々の社会全体が直面している問題。
加えて、DV、子どもに対する虐待・ネグレクト、介護疲れ、家庭崩壊、学校におけるいじめ、親の自己中心主義の傾向などの、子どもが日常生活で直面する困難をあげています。
今、コロナ禍の中で、経済危機や貧困の問題は、世界的に広がり、さらに拍車がかかっています。
未知のウィルスとの闘いの中で感じる不安や、医療崩壊などの問題は、今まであまり感じていなかった新たな問題です。
長引く学校の休校で、すぐにオンライン教育に切り替えた私立学校や、教育熱心な家庭と、放り出されたままの子との学力格差も広がります。
受験や就職も、不公平や混乱は避けられないでしょう。
それでも、「このたいへんな時代」に、私たちは生きていきます。
明るい未来を思い描いて。
そのヒントは、絵本の中に探せます。
そのきっかけ作りとして、私は子供にも、大人にも、もっと絵本を読んでいきたいと思うのです。
このタイミングで、私のところにやってきたこの本が、「それがミッション」だと教えてくれたような気がします。
ブログランキング参加中です!クリックで応援よろしくお願いします♪