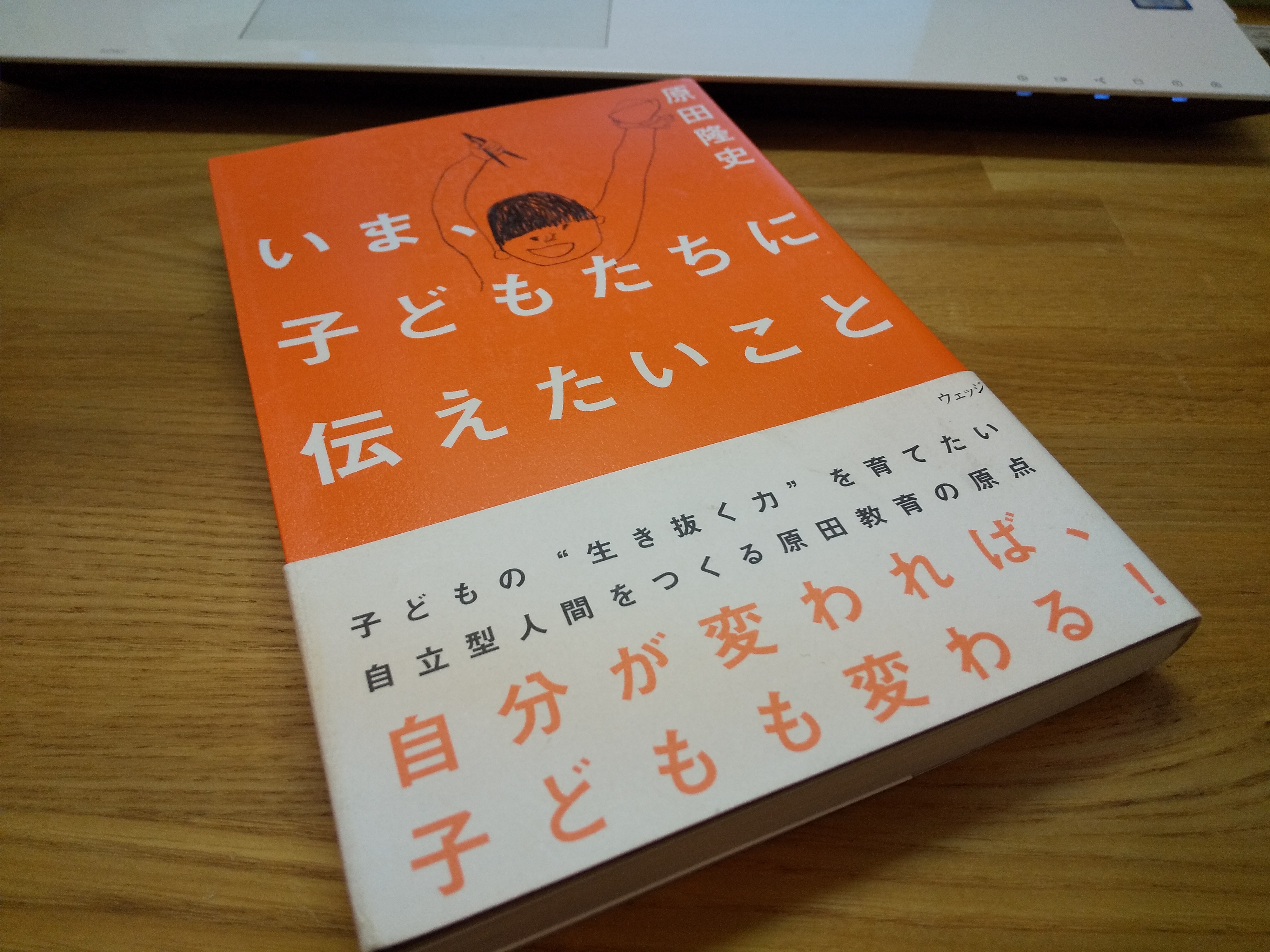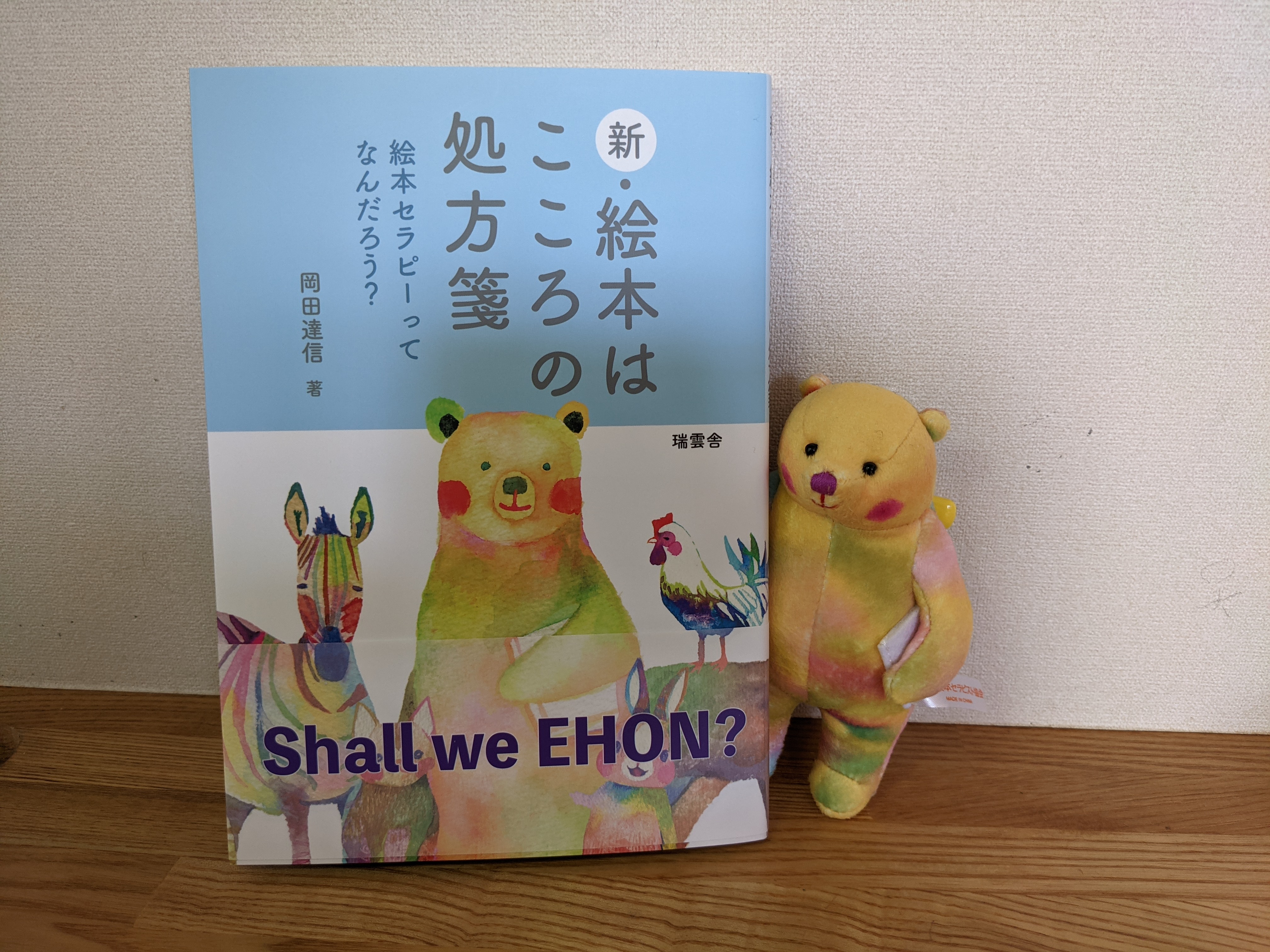【おすすめ本】「ネバーギブアップ」でわかる、子供の力の伸ばし方
こんにちは!
絵本と児童書が大好きな、絵本セラピスト🄬らくちゃんです。(プロフィールはこちら)
今日は、元気の出る児童書を読んだので、ご紹介します。
「ネバーギブアップ!」(くすのきしげのり:作 山本孝:絵 小学館)

本書と出会ったのは、偶然でした。
絵本セラピーに使える絵本を探そうと、キーワードで検索し、気になる絵本を図書館に予約して取り寄せていました。
その中の一冊が、この本でした。
「あら、絵本じゃなかったんだ。これじゃ、絵本セラピーには使えないなぁ・・・」と思いつつ、せっかく借りてきたので、読んでみたというわけです。
小学校中学年くらいを読者に想定した児童書ですが、実は目標設定や、達成までの行動の仕方、応援の極意など、大切なことが散りばめられた名作でした。
あらすじ
主人公ジュンは、何事にも自信のない、弱虫で泣き虫の少年でした。
ジュンのクラス、4年3組では、うでずもうが大人気。
大学で柔道部だったという担任の山下先生が、自慢の腕を披露し、うでずもうの技を子供たちにおしえてからというもの、休み時間は男子も女子も、うでずもうをするようになったのです。
ある日、クラスで「うでずもう大会」をすることになりました。
ところが、ジュンはうでずもうが大の苦手。一度も勝ったことがありません。
そんなジュンを見て、担任の先生が「毎朝特訓をしよう」と提案します。
お姉ちゃんは、最初は続くわけないと馬鹿にしましたが、一緒に付き合ってくれることになりました。
来る日も来る日も、たとえ土砂降りの雨の日も、公園で特訓を続けた三人。
さて、ジュンは、最後まで特訓を続けることができるのでしょうか。そして、本当に強くなれるのでしょうか?
物語に秘められた、目標達成の極意
力が弱く、自分に自信が持てなかったジュンの、挑戦と葛藤と成長の物語に、思わず引き込まれます。
うでずもうの対戦シーンは、思わず手に汗にぎる緊張感。
「鉄腕」「ジャイアント」「トルネード」「マンモス」なんて技が、うでずもうにあるなんて、知りませんでした。
特訓の中で、山下先生は、伝説の技「ツバメ返し」をジュンに伝授します。
この臨場感あふれる成長物語の中には、目標達成の極意が秘められていることに気がつきました。
継続で心が強くなる
ジュンは、山下先生と約束した「毎朝の公園での特訓」を続けました。
それこそ、朝から土砂降りの日も。
「雨だから休みだろう」と勝手に決めてさぼろうとしたところ、お姉ちゃんにハッパをかけられ、公園に行ってみました。
すると、やはり先生は約束どおり、公園に来ていました。
傘をさして立っていた先生は、ジュンを見ると親指を立てて「ネバーギブアップ」と。
作品の紹介には、このように書かれています。
「あきらめなければ、きっとかなう」という、こどもたちへの熱いメッセージのこめられた作品です。
Amazon 編集担当からのおすすめ情報より
「継続は力なり」
確かに、トレーニングを継続していくことで、体力、筋力がつき、技も磨かれるでしょう。
しかし「あきらめない」というのは、一種の心の強さです。
「目標達成の技術、原田メソッド」の創始者、原田隆史先生は、「自分で決めたことをしっかり継続することで、心は強くなる」と言います。
試合で追い詰められた局面。
あきらめずに、反撃のチャンスを待って粘った心の強さは、毎日の特訓を「継続した」ことで養われたと言えるのです。

心の栄養、ストローク
交流分析という心理療法の中に、「ストローク」という考え方があります。
ストロークは、「心の栄養」とも言われています。
人は、食事から摂る体の栄養とともに、心にも栄養を与えないと生きてはいけません。
主に、プラスのストロークして、褒める、応援する、認める、好意を伝える、励ます、スキンシップ、共感する、話を聞く、などがあります。
この物語の中で、山下先生は、頻繁に惜しみなく、ジュンにストロークを与えています。
「ジュン、いいぞ」
「その調子だ」
「よくがんばった」
「強くなってるぞ」
山下先生から、心の栄養を毎日注がれて、ジュンは次第に自信を持ち、やる気が高まっていきました。
人が難しいことにチャレンジしたり、前向きに物事に取り組むためには、心が元気じゃないといけません。
体力づくりや技術の指導の前に、このストロークシャワーが、効いたのかなと思います。
えこひいき
「えこひいき」という言葉は、あまりいいイメージがないかもしれません。
でも、山下先生がジュン一人だけに、毎朝「秘密の特訓」をしたのは、特別扱い、「えこひいき」じゃないでしょうか。
これ、子供のやる気を高めたり、自己肯定感をはぐくむのに、実はとっても大事なことなのです。
そして、この山下先生のすごいところは、「えこひいき」をみんなにしていたところ。
物語の最後、後日談があります。
あれから20年後、山下先生が退職されるというので、当時の4年3組の仲間で「先生の退職をお祝いする会」を開きました。
ジュンは、あの時自分だけが先生に秘密の特訓を受けていたことを、誰も「ずるい!」と言わなかったことを、ずっと不思議に思っていました。
その謎が、ここで解けたのです。
「だってさ、あのころオレは、毎日放課後、山下先生に、にがてだった割り算を教えてもらってたんだぜ」
「ぼくは、漢字の練習を」
「わたしは、なわとびの二重とびを」
「ぼくは、ピッチング練習を」
なんと、みんな「えこひいき」されていたのです。
このお話と、そっくり同じエピソードを聞いたことがあります。
うちの息子たちが、小学生の頃6年間ずっとお世話になった学習塾、「花まる学習会」の代表高濱正伸先生の実話です。
6年生の時、当時内気だった高濱少年。
算数は得意で、ひそかに自信を持っていました。
ある時、担任の先生に呼ばれて、算数が得意なことを見抜かれ、もっとやれば一流大学にも行けるからと、特別に勉強を見てもらうことになったというのです。
その「えこひいき」が嬉しくて、自尊心がくすぐられ、難しい中学入試の問題集にも自主的に取り組むようになったそうです。
その結果、東大に進学、今では算数オリンピック委員会の理事を務めたり、算数脳やパズルなどの本も多数出版しています。
ところが、高濱先生が偶然、埼玉のとある小学校の校長先生になっている当時の級友に再会、実は先生にえこひいきされていたという話をしたところ、なんとその級友もそうだったというのです。
「なんだ、オレだけじゃなかったのか・・・」と思ったそうですが、先生は平等に「えこひいき」していた、まさに物語の中の「山下先生」ではないですか。
このエピソードは、高濱先生の講演会などでもよく話されますが、花まる学習会のHP掲載の「高濱コラム」にも書かれています。↓
まとめ
この物語の作者のくすのきしげのり先生は、もと公立小学校の先生です。
教育の現場で、実際に多くの子供たちと真摯に向き合ってきた中から生まれたお話。
私の師匠、原田メソッドの原田隆史先生も、花まる学習会の高濱正伸先生も、それぞれ公立中学校の先生と、塾の先生として、子供たちと誠心誠意付き合い、教育に情熱を燃やしてきた人たちです。
その人たちの教え、主張は、言葉は違っても、同じ本質を語っています。
この物語で言うと、継続することで心が強くなること、心の栄養ストローク、そして平等にえこひいきすること。
こういうことを、心にちょっと留めておくだけで、子供への声かけやサポートの仕方が変わってきます。
絵本も児童書も、「子供が読むもの」と思うなかれ。
大人でも、ハッとすること、学ぶことがたくさんあります。
特に、子供の挑戦や成長を見守り、サポートする立場の人には、ぜひ読んでもらいたい作品です。
心づくりやストロークなどについての参考図書はこちら。