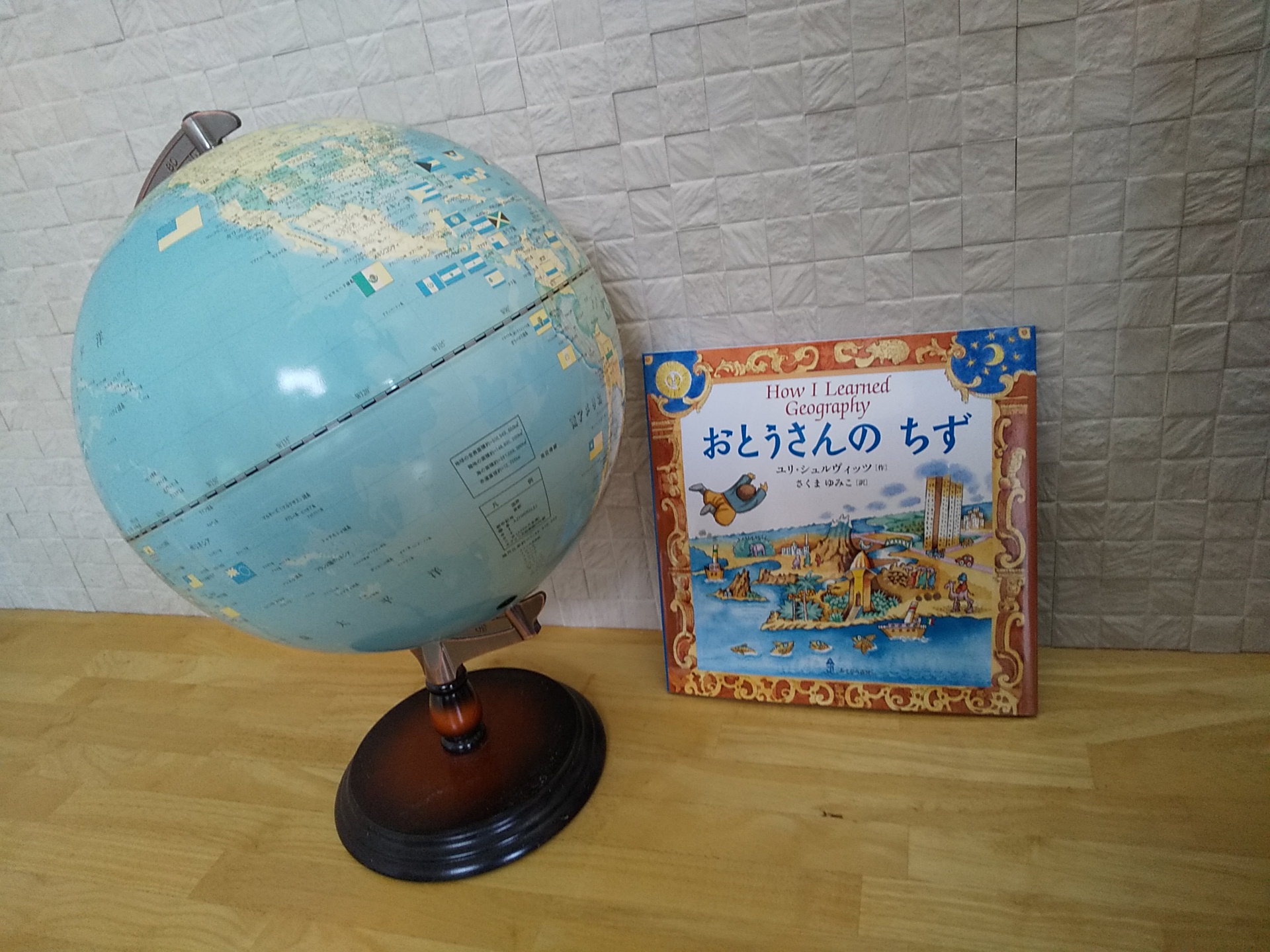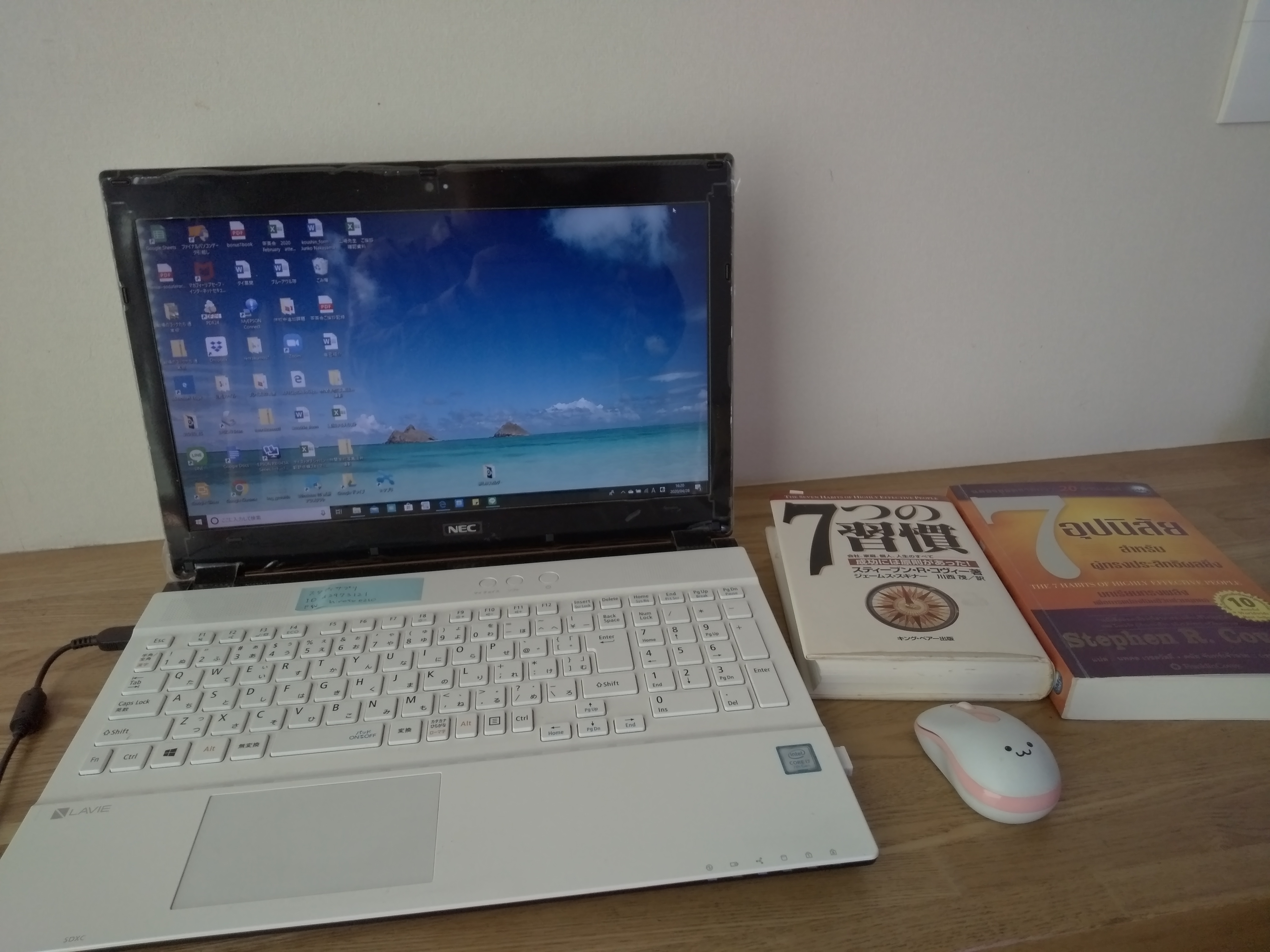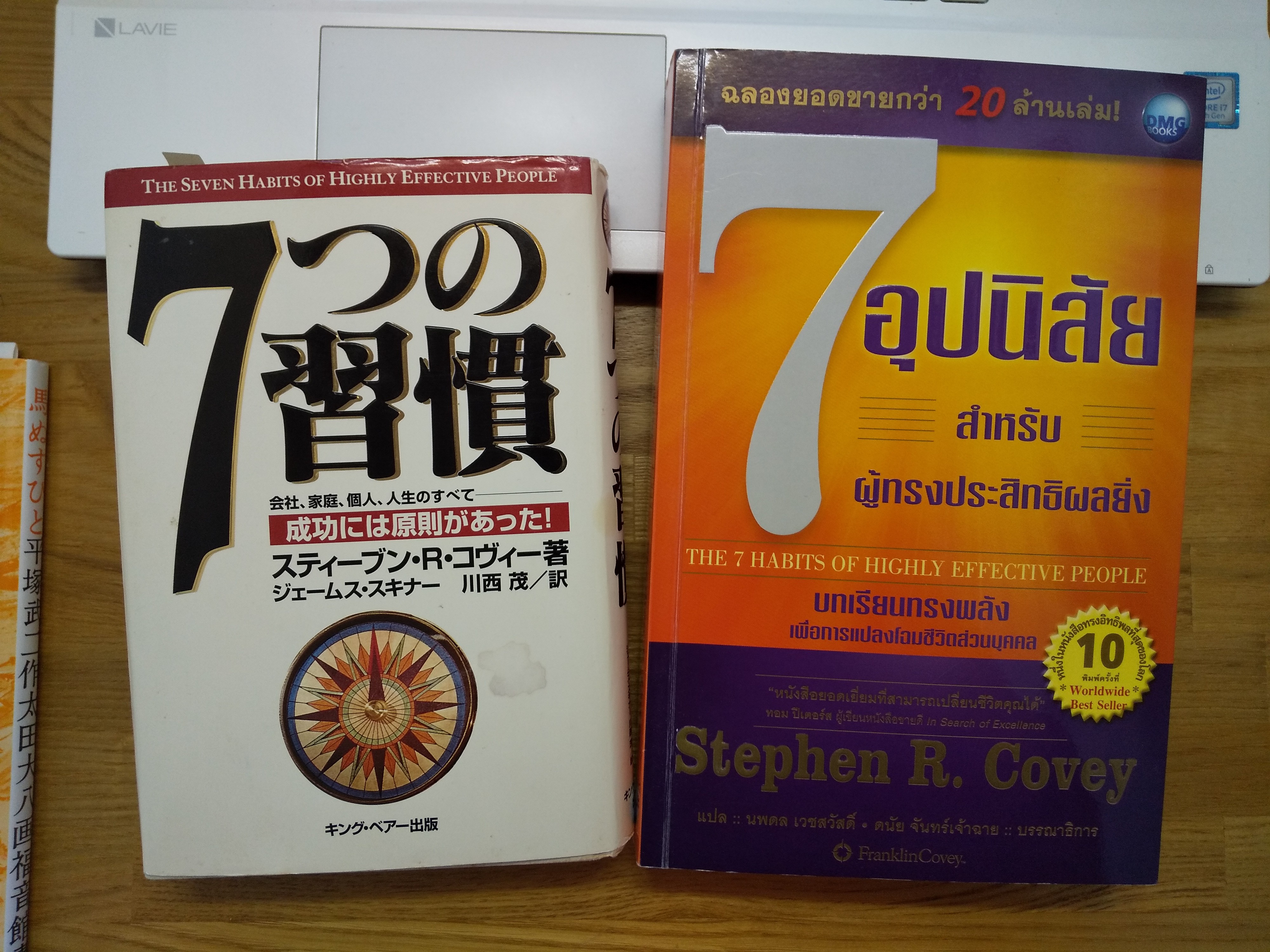リモートワークに思うこと
オットが、3月中頃から都内出勤と在宅勤務を半々でするようになり、3月の三連休明けから完全に在宅勤務になりました。
もともと早寝早起きで、勤勉なオット。
在宅期間中も、通勤時間分だけゆっくり起きてくるものの、いつもどおりに朝食をしっかり食べ、朝のルーティンをして、仕事に入っていました。
ただ、「休みじゃないよ、あくまで勤務中」という意識が強く、ちょっとした家のことも頼みづらい雰囲気。
その上、「○○時から、会議だから静かにしてね」ということが度々あり、子供たちもきゅうくつな思いをしています。
もともと家は、安心してくつろげる場所であったはずです。
それぞれ仕事や学校に行き、一日がんばってきて帰宅する。
家族でリラックスして、夕食を囲みながら会話をしたり、テレビを見たり、お風呂に入って一日の疲れをいやしたり。
そんなイメージがあります。(できているかどうかは別にして)
なので、家のリビングで「オレは仕事をしているんだ」というのに、とても違和感があります。
コロナ感染拡大、外出自粛の状況で、世の中ではリモートワークが急速に推進されています。
ZOOMなどのオンライン会議システムも発達し、多くのオフィスワークは自宅でやることが可能になりました。
新聞によると、テレワークの管理をするサービスを提供する会社もあり、着席、離席ボタンで勤務時間を管理したり、パソコンの画面を10分おきにセーブして、上司が進捗管理をすることも可能だとか。
技術的に可能なことは増えても、まだまだ感情的に、習慣的に違和感、不便、不快、不都合は多そうな気がします。
私自身、いろんな働き方をしてきました。
独身の時は、普通に会社員としてお勤めしていましたので、今のオットの生活スタイルは理解できます。
その後、子どもが幼稚園くらいの時から昨年まで、都内に週二日だけ出勤する仕事と、在宅で翻訳をする仕事をしていました。
どちらも、一長一短でした。
小さい子どもがいて、仕事に出るのは、本当に大変です。
子どもたちの朝の準備もあり、洗濯を干して、大急ぎで家を出てしまえば、後は家のことはできませんから、片付け、掃除は常に行き渡っていない状態。
でも、家のことは強制終了して家を出てしまえるのは、それはそれでよかったのです。
仕事モードに切り替えられますから。
家のことができてないのも、理解してもらいやすいし、自分でも納得しやすいのです。
そこが、在宅だとメリハリがつきません。
家にいるのに掃除ができていなければ気になりますし、宅配便や訪問セールスは来るし、PTAだ自治会だと対応しないといけないこともあります。
子どもが低学年だと、親子行事やPTAボランティアに召集されることもあり、つい時間を調整して参加してしまいます。
一つ一つは本当に些細な雑用なのですが、常に集中力が分断されるのです。
結局、落ち着いて仕事ができるのは、家族が寝静まった深夜、寝不足になりながら・・・ということが少なくありませんでした。
精神科医でビジネス書作家の樺沢紫苑氏の著書「神時間術」(大和書房)によると、「集中力が高まっているときに、電話や声がけによって集中力が途切れてしまった場合、その状態(集中力が高まった状態)に戻るのに約15分かかる」という研究結果があるそうです。
だから、樺沢先生は執筆中は声をかけないように奥さんに言っているそうですが、そんなことが許されるご家庭、環境ばかりじゃないですよね。
うちは、もう子供が聞き分けられる年齢ですが、泣くのが仕事の乳幼児がいるご家庭もあるでしょう。
日本の住宅事情では、パパが個室を持っていることが当たり前ではありません。
家庭の空間に、在宅勤務をしている夫、父親が、「仕事中」と言って静かな環境を要求すれば、摩擦が起きるのは当然でしょう。
場所をオフィスから自宅にただ移すだけ、という単純な問題ではないのです。
いまやコロナ離婚なんて言葉も生まれています。
感染症の蔓延による健康不安や経済的な不安、普通の活動やレジャーができないストレスもあるかと思いますが、家庭に仕事を持ち込むリモートワークのやり方も、試行錯誤しながら考えていかなきゃいけない課題だと思います。
ブログランキング参加中です!クリックで応援よろしくお願いします♪