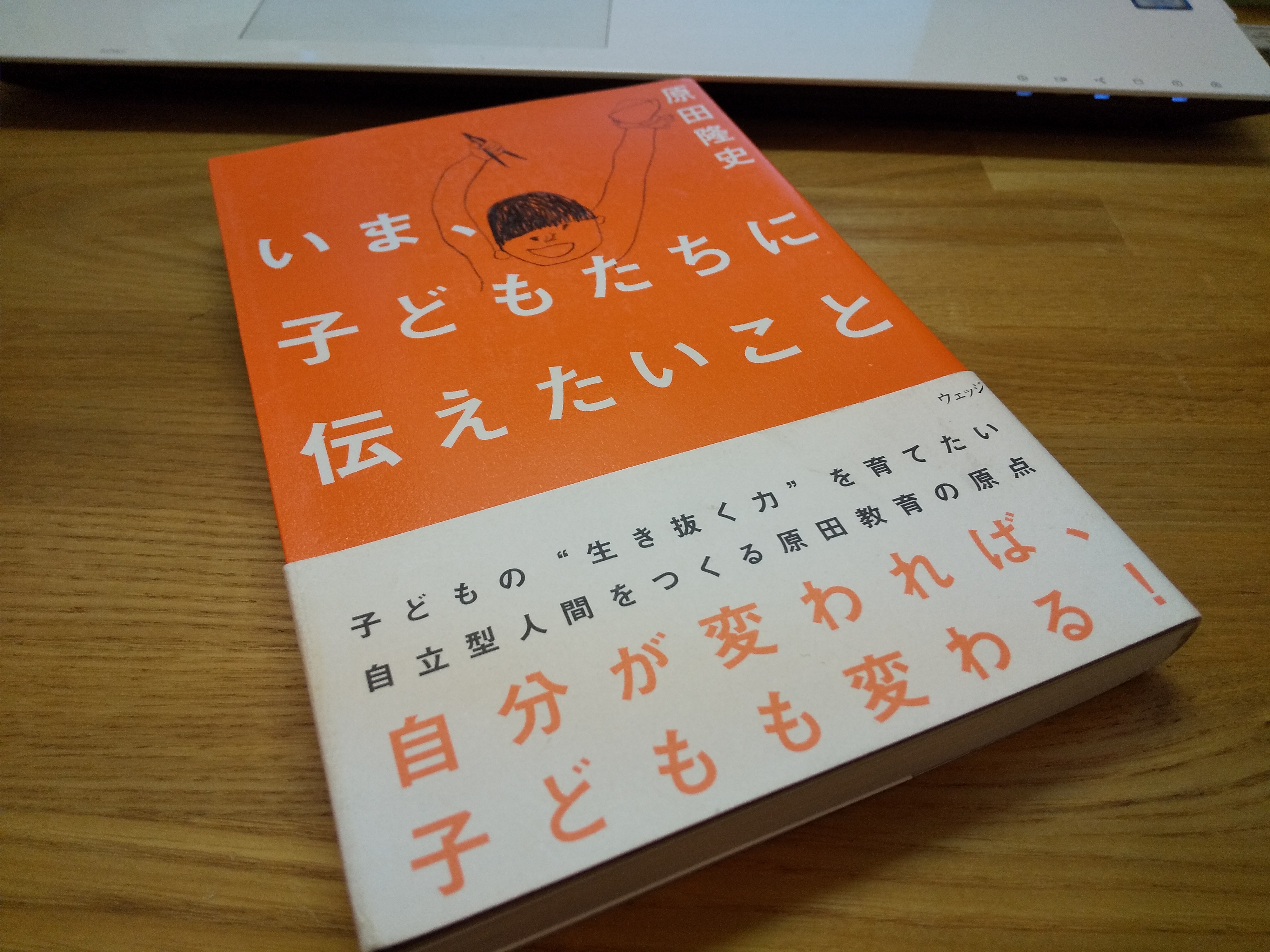「嫌い」の正体をつかもう
こんにちは!らくちゃんです。
今日は珍しくネガティブな感情に目を向けてみたいと思います。
どんなに「心のコップ」を上に向け、ポジティブに、ごきげんにしていようと思っても、ネガティブな感情が出てしまうこともありますよね。
人間ですから。
そのネガティブな感情の中に、「嫌い」というものがあります。
自分が「嫌い」と思ってしまう原因、その正体をもっと詳しく、具体的につかむことで、そこを適切に対処できれば、結果的にごきげんにもっていけるのではないか、と考えたのです。
その「嫌い」は勘違い?
そんなことを考えたのは、あるブロガーさんのメルマガを読んだことがきっかけでした。
その方は、以前は会社員をしていましたが、今は海辺の街でブログやYouTubeで情報発信をして暮らしています。
以前は、「長い間、夏が嫌いだと思っていた」と言います。
なぜ夏が嫌いだったかというと、
- 暑いのに、スーツを着なきゃいけないこと
- 暑いのに、汗だくで外回りをして、オフィスの冷房で体が冷えること
- 猛暑と冷房の温度のアップダウンで体調が悪くなり、倦怠感がひどくなること
これらのことが嫌いだったということに気がついたそうです。
海辺の街に住み、これらの「嫌い」がなくなった今、夏が大好きだったことに気づいたどころか、「最高の季節」「夏こそ自分の季節」とまで書いていました。

こういうこと、ありますよね。
実際、私にも「嫌い」と思っていたことが、具体的に「嫌い」の正体を見つめ直したことで、見方が変わったものがあります。
私は体育が嫌いだった
村上春樹のエッセイを読んでいて、思ったことがあります。
村上春樹と言えば、マラソンを走る作家として有名です。
彼のエッセイ「走ることについて語るときに僕の語ること」(文春文庫)を読んで、妙に心に残っていた部分があります。

「学校の体育の時間は好きになれなかったし、運動会みたいなものにはつくづくうんざりさせられた」
でも彼は、長距離を走ったり泳いだりすることは性に合っていたらしく、小説家になってから、走ることが日課になっているようです。
私も、学校の体育が苦手で嫌い、運動会が憂鬱な子供でした。
自分でも、「運動神経が悪い」「運動が嫌い」と思って、劣等感を持っていました。
しかし、5~6年くらい前から、実は体を動かすことが嫌いじゃないんじゃないか?と思うようになりました。
健康維持とダイエットのため、近所の公園をウォーキングしたり、ゆっくり走ったりするようになったのですが、これが結構楽しいと感じているのです。
本当にゆっくりの「ゆるラン」で、時にウォーキングの人に追い抜かされるようなペースですが、木々の緑や季節の花、鳥の声などをめでながら、ゆっくり走っていると6kmくらいは平気で走っていたりします。
スポーツをする人にとっては、大した距離ではないですが、今まで何も運動をしてこなかった中年女性が走るには、まずまずの距離ですよね。
それがまったく苦しいと感じません。

村上春樹は、体育や運動会が好きになれなかった理由として、「上から『さあ、やれ』と強要された運動だったから」と書いています。
「自分のやりたくないことを、自分のやりたくないときにやらされることに、昔から我慢できない」のだそうです。
私の場合、そうではありませんでした。
体育や運動会が嫌いだったのは、速い遅いや勝ち負けなどの評価をつけられるのが嫌だったから。
まじめにやっていても、足は速くならないし、鉄棒や球技が上手にできないのもどうにもなりません。
それに、スポーツの得意な姉と比べられるのも、不愉快でした。
だから、誰でもできる形をまじめに真似るだけのお遊戯、ダンス系には苦手意識はありませんでした。(楽しいとも思わなかったけど)
結局、順位や勝ち負けをつけられる「体育」は、下位のレッテルを貼られるので、「嫌い」「苦手」「下手」「運動神経が悪い」と自分で思いこんだまま生きてきました。
そして、この歳になり、順位もタイムも勝ち負けもなくなって初めて、「嫌いじゃなかったかも」と気がついたわけです。
一言で「体育が嫌いだった」と言っても、その正体は違いますよね。

「料理が苦痛」も正体をつかんでラクになった
以前、このブログで、「料理が苦痛、面倒でたまらない」という問題を、ちょっとした工夫で改善できたことを書きました。

その頃、こんな本を読んでいました。

これは、もともと料理ができない人向けではなく、「『ちゃんとした料理』を『作り続ける』ことに疲れてしまった、すべての人に」というキャッチコピーがついています。
頑張ってきたけど、つらくなってしまった人に向けて、様々な提案や簡単で豪華に見えるレシピの提示などがされています。
しかし、何よりも、本書の中で一章まるまる費やしている「料理にまつわる『呪縛』」には、はっとさせられました。
- 「時間があるからできるはず」の呪縛
- 「健康のために」という呪縛
- 「毎日違うものを食べる」という呪縛
- 「インスタ映え」という呪縛
- 「誰からも評価されていない」という呪縛
- 「自分はちゃんとできていない」という呪縛
なんとも多くの呪縛にがんじがらめにされていることか・・・
家族のために食事を作り続けてきた人なら、深く共感されることと思います。
どれもいわれのない「呪縛」であり、手放してもいいものなのですが、人によってどの呪縛が強いかは違うと思います。
私もあらためて、料理の何が「苦痛」なのかを考えてみました。
調理の作業自体はそんなに嫌いではないし、健康や栄養のことを考えるのも苦痛ではありません。
私は、「常に献立を考え続けていること」と、料理にもれなくついてくる「洗い物」が嫌いということでした。
そこに目を向けて、対策を考えたり、家族に理解と協力を求めることで、ずいぶんと「苦痛」はやわらいでくると思います。
まとめ
「嫌い」「苦手」と一言で切り捨ててしまうことは簡単ですが、何が嫌いなのか、どこが苦痛なのか、よくよく突き止めていくと、できることが見えてきます。
自分と向き合い、丁寧に話を聞くように、感情の正体を見極めていくことは、自分を大事にすることだったり、人生を豊かにすることになるんじゃないかと思います。
「嫌い」に限らず、「怒り」や「イライラ」「悲しみ」も、人によってその正体は違ったりします。
自分の感情に目を向ける。
その正体を探ってみる。
そんな習慣を持つことを、おすすめします。
ブログランキング参加中です!クリックで応援よろしくお願いします♪