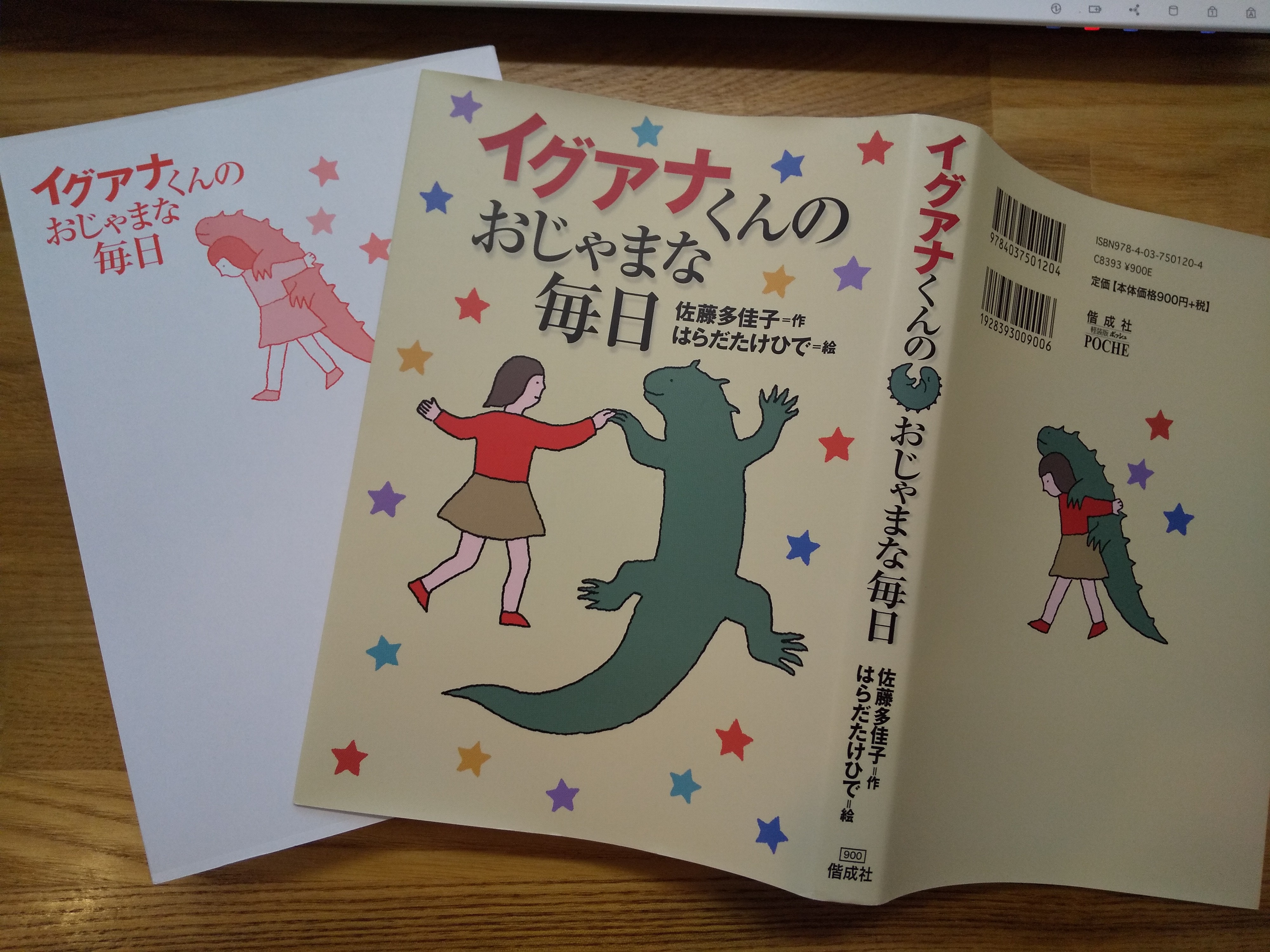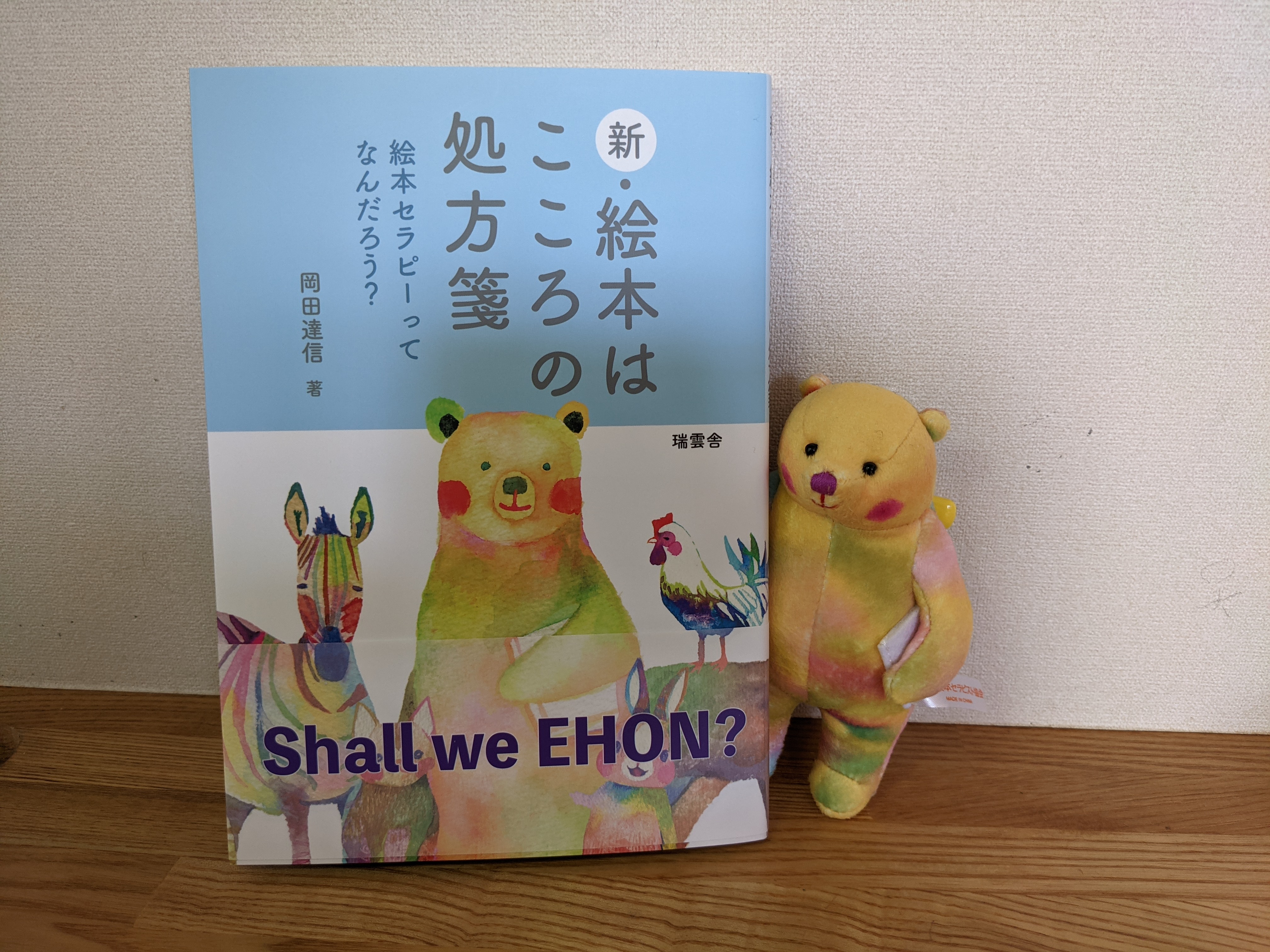「知らなかった、ぼくらの戦争」から気づいたこと 後編
昨日に引き続き、アーサー・ビナード著「知らなかった、ぼくらの戦争」を読んで、気づいたことを書いていこうと思います。
昨日は、「戦後」や「玉砕」などの言葉について気づいたことを書きました。
今日は、「別のアングルから見たあの戦争」について、思ったことを書き留めておきたいと思います。
私はもちろん、戦争を体験していません。
知っているのは、学校の歴史の授業で習ったこと、戦争を扱った文学、映画、テレビのドキュメンタリー番組、観光地で訪れた戦争博物館の展示などから得たものです。
とにかく悲惨で、つらく苦しい体験。とんでもない数の命が失われたこと。空襲でなにもかも焼かれ、遺体の山の中を逃げ惑った恐怖。戦場で戦う兵士の極限状態。片道だけの燃料で飛び立っていった若き特攻兵たち。
アーサーさんがインタビューした23人から聞いた話も、悲惨な体験談ばかり。
しかし、それは単なる悲劇なだけではない、私の浅はかな戦争の認識を大きく揺さぶるものでした。
まずは、広島と長崎に落とされた原爆について。
長引く戦争を早く終結させるため、やむを得ず原爆を投下したという大義名分があります。
しかし、長崎に投下されたプルトニウム型原爆と同じ形、重量の模擬原爆が、日本各地に投下されていたというのです。
最後の投下は、8月14日。終戦宣言の前日です。
これは、原爆投下練習に使われたと思われます。
アメリカにとっては、もうほとんど「死に体」だった日本など眼中になく、次の戦争、ひいては核で世界に絶対的な影響力を持つための準備に入っていたのです。
実験と練習のための原爆投下だったのかもしれない・・・そう思うとやりきれない怒りを感じます。
アーサーさんは、2016年8月に広島を訪れたオバマ大統領の演説を同時通訳したそうです。
その時の違和感と怒りを、辛口の文章にしたためています。
被爆地の平和公園で、核なき世界を訴える大統領の側に控えるおつきの人が抱えるかばんは、「核のフットボール」と呼ばれるもの。
大統領だけが発射権限を持つ、核のボタンが入ったかばんです。
岩国基地で米兵たちをねぎらい、新型戦闘機オスプレイのPRのために来日し、ついでに広島を舞台に上手にパフォーマンスをしていったノーベル平和賞受賞者。核のボタンを手に持ったまま。
まるで人ごとのような、流ちょうなスピーチも、実に空虚に響きます。
そこには、核廃絶の決意も、被爆地や被爆者への誠意もまるで感じられません。
が見える-300x237.jpg)
私は、あの戦争を、軍国主義と一部の上級軍人の暴走により、罪のない国民たちが辛酸をなめ、南国の戦場に送った兵隊にこの世の地獄を体験させ、勝ち目のない戦いに「一億玉砕」とけしかけて、多くの貴い命を失ったものと思っていました。
つまり、ほとんどの国民は「被害者」だった、と。
しかし、日本を代表するアニメーション演出家でジブリ作品のプロデュースや「火垂るの墓」などの作品で知られる高畑勲さんは言います。
「当時の国民は、戦争にはみな『のっていった』んです」と。
高畑さん自身も戦争体験者で、子供の頃住んでいた岡山で空襲に遭い、九死に一生を得ています。
その当事者が感じる違和感。
あとになって、テレビドラマなどで描かれる日本人は、「不本意ながら戦争に突入してしまった」という具合に、途方に暮れてオロオロし、「半分反対だった」という態度だったりします。
まさに、私が理解していた構図です。
しかし、戦争の高揚感に国が盛り上がり、大きな流れに「のっていって」しまったのです。
「始まってしまったからには、もう、国に勝ってもらうしかない。
冷静に客観的な判断なんかしないんです。
そんなことをしても無駄だから、負けるなんてもう一切考えない。
現実に、太平洋戦争の時はそうでしたよね。」
「軍隊に行ったということは、加害者の立場で行ったわけですよね。
(中略)
原爆も含めてですが、『甚大な被害を受けた』と話し、引き揚げも含めてですが『とても大変だった』という体験が多く語られる。でも本当は、被害と加害は量的にいえば同等くらい、あるいは加害のほうが同等以上なんですよね。
土壇場になって『ひどい目に遭った』ことだけを話しても、『反戦』にはならないと思います。」
(本書から引用)
この見方は、衝撃的でした。
いや、言われてみれば、どこか無意識でそんな気もしていたようにも思いますが、戦後の高度経済成長を遂げた豊かな時代を享受してきた自分が、そんなことを言ってはいけない気がして、「被害者説」を採用していたのかもしれません。
大きな流れに「のって」しまうのは、日本人だけのことではありません。
ナチスのやったことも、他の戦争でおきたことも、民族間の大虐殺も、そういう側面があったと思います。
この本でインタビューに答えている23人の方のうち、もう何人かの方は鬼籍に入られています。
上述の高畑勲さんも、2018年に亡くなられました。
話が聞けたぎりぎり最後のタイミングで、このような本を書いてくれたことに心から感謝です。
今、世界は「戦争」と言われる事態に陥っています。
75年前と違い、敵はウィルスという目に見えないものです。
そして、アメリカが周到に配備した核兵器もまったく役に立ちません。
しかし、人はあの時と同じように、情報に洗脳され、恐怖と不安と焦りで思考停止し、冷静で客観的な判断ができず、流れに流されていきかねません。
この本を読んで、思い込みに疑問を持つこと、正しく情報を理解すること、そして自分で考えて行動することを、今だからこそもう一度しっかり考えたいと思いました。
ちなみに、アーサー・ビナードさんは、原爆を扱った絵本や紙芝居も書いています。
こちらもおススメ。
ブログランキング参加中です!クリックで応援よろしくお願いします♪