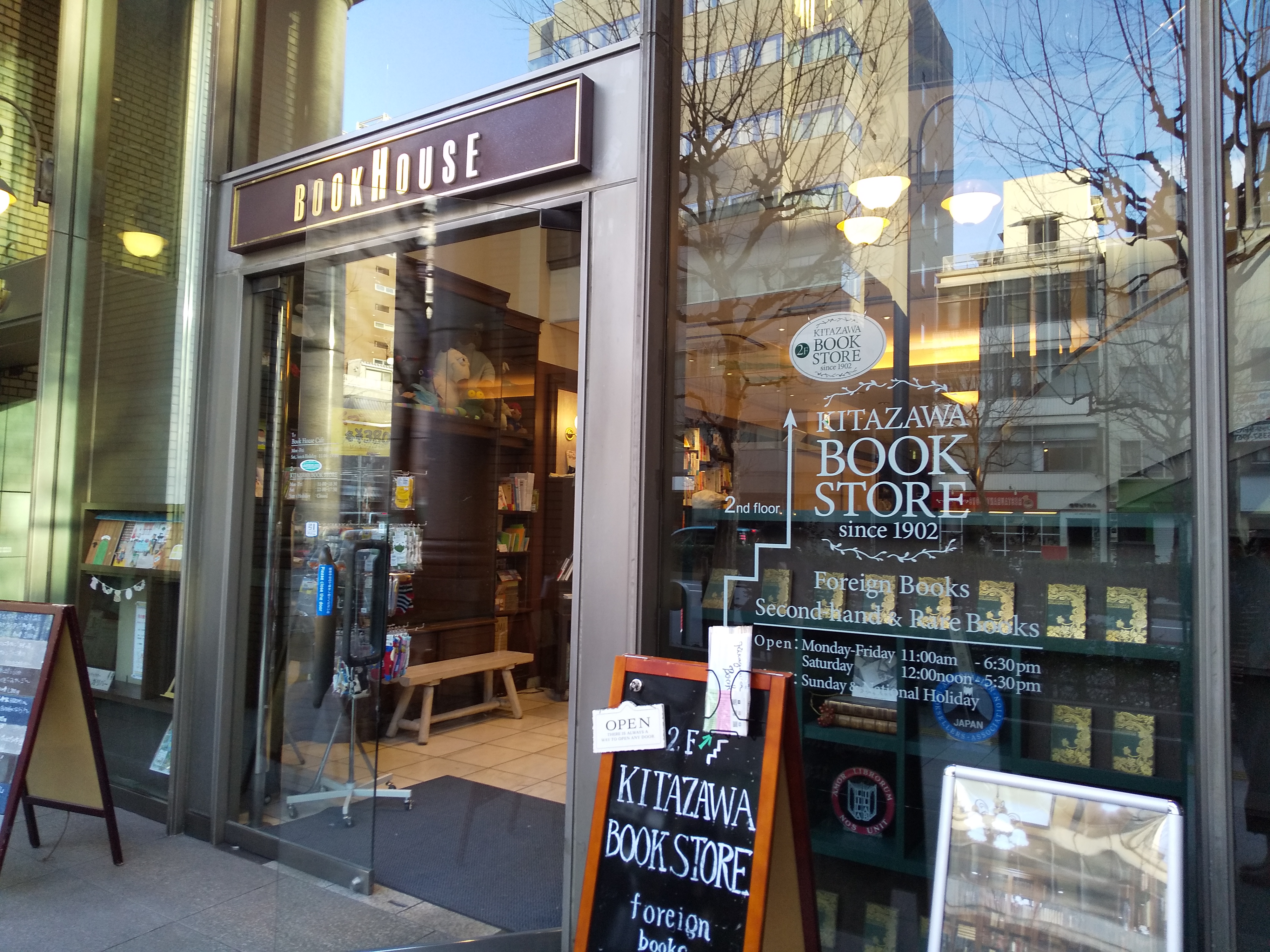「ランドセルの日」に、役目を終えたランドセルについて考えました
こんにちは!
大人に絵本を読んでいる、絵本セラピスト🄬のらくちゃんです。(プロフィールはこちら)
今日、3月21日は「ランドセルの日」なのだそうです。
ちょうど卒業シーズン。わが家の次男のランドセルも、数日前に役目を終えたばかりでもあり、ランドセルについていろいろ考える日になりました。
ランドセルの日とは?
3月21日は、「ランドセルの日」に制定されています。
いい夫婦の日(11月22日)のような語呂合わせや、目の愛護デー(10月10日)のような形から連想されるものではないですね。
では、なぜ3月21日がランドセルの日なのでしょう?
答えは、3+2+1=6で、小学校の6年間を表すからだそうです。
「じゃ、3月3日でも、4月2日でも、12月3日でもよくね?」と、息子は言っていましたが、卒業シーズンに一番近いからなのでしょうね。
この日を決めたのは、ランドセルをミニサイズに加工する店「スキップ」の革細工職人・増田利正さんだと言われています。
役目を終えたランドセル、どうする?
ランドセルって、それなりにお値段するし、丈夫で、6年使っても、まだ結構使えそうだったりします。
思い出もあるし、なんとなく捨てがたいのですが、普段のお出かけかばんに使えるわけでもなく・・・
結局、わが家では長男のランドセルはクローゼットに押し込めたまま、2年が経過しました。
この、卒業後のランドセルをどうしたらいいか、いくつか選択肢があることがわかりました。
自宅で保管する
思い出の品として、自宅で保管しておいてもいいでしょう。
大人になり、結婚するときなど、いい記念になるかもしれません。
ただし、きちんと手入れをして、乾燥剤などを入れて保管しましょう。
わが家の長男のランドセルは、ただクローゼットに放り込んでおいただけなので、表面にカビが生えていました。
家庭ごみとして処分する
とはいえ、ランドセルは結構な大きさがあり、場所をとるものです。
もう使わないことが明らかなら、思い切って「処分」というのもありです。
中学生になれば、また中学用のかばんや部活グッズも増えてきますから。
処分の際は、自治体によって分別のカテゴリーが違うので、確認しましょう。
「ミニランドセル」にリメイクして、思い出をとっておく
大きなランドセルでは、保管が難しくても、小さな「ミニランドセル」にしたら、かわいく思い出の品をとっておけます。
いくつか、リメイクサービスをしているところがありますので、費用などを比べて検討してみてもいいかもしれません。

小銭入れや定期入れにリメイク
実用的な小銭入れや定期入れ、ペンケースなどにリメイクして使う方法もあります。
ただし、リメイクはミニランドセルにしても、実用品にしても、一つずつ解体して手作りになりますので、それなりの費用はかかります。
アフガニスタンなど海外に送る
紛争の続くアフガニスタンで、日本から届くランドセルを待っている子供たちがいます。
学校の校舎はなく、青空教室で学ぶ子供たち。
日本で役目を終えたランドセルに、新しい文房具を詰めて届ける活動をしている団体があります。
寄付して(送料負担の場合もあり)、海の向こうで、また子供たちの相棒として、活躍してもらってもいいかもしれません。

「7年目のランドセル」を読んで
くしくも「ランドセルの日」に、「7年目のランドセル」という写真絵本を読みました。
3月20日の国際幸福デーに合わせたイベント「しあわせ2021シンポジウム」に、ワークショップ出展し、絵本セラピーを開催したのです。
「しあわせ」「ウェルビーイングってなんだろう?」というキーワードで絵本を選び、作ったプログラム。
一緒に今回の絵本セラピーをやってくれた、絵本セラピスト仲間が読んでくれた一冊が「7年目のランドセル ランドセルは海を越えて、アフガニスタンで始まる新学期」(内堀タケシ:写真・文 国土社)でした。
日本で役目を終えたランドセルに、文房具を入れてアフガニスタンに送る活動をしている団体があります。
紛争の続くアフガニスタンでは、学校の校舎はなく、青空教室で勉強している子供たちがたくさんいます。
通学路には、壊れた戦車や機関銃の薬きょうが落ちているのが当たり前の風景。
お古のランドセルを、満面の笑みで嬉しそうに背中に背負うアフガニスタンの子供たち。
平和について、豊かさについて、しあわせについて、絵本セラピー参加者の皆さんと、思いを語り合いました。
ちなみに、使用済みランドセルの送り先情報は、こちらのサイトが参考になります。
まとめ
6年間の小学生生活の相棒だったランドセル。
誰しも思い入れがあることと思います。
入学式の小さな背中に、大きすぎるピカピカのランドセルが印象的でした。
大きくて、重くて、後ろにひっくり返らないかと、ヒヤヒヤしたものです。
最初は、学校の準備も、時間割を見ながら一緒に持ち物をそろえてあげたものでした。
いつの間にか手出しをしなくなり、ランドセルの底からいつのかわからないプリントがくしゃくしゃにつぶされているのを、引っ張りだすようになりました。(わが家の場合)
6年生ともなれば、なんだかランドセルが不似合いなほど、大人びた大きい子もいますよね。
親にとっても、いつも見送っていたランドセル、愛着があります。
今回、役目を終えたランドセルをどうする?ということを考えてみて、私はうちにある二つのランドセルを、紛争地の子供たちに送ることにしました。
実は、使い古されたものを、途上国の人に送ることに、心理的な抵抗がありました。
まるで上から施してあげるような、傲慢な感じがしていたのです。
でも、まだまだきれいで、どこも傷んでいない息子たちのランドセルを見て、捨ててしまうのはしのびない・・・
クローゼットにしまっておいても、何の役にも立たず、ただカビていくばかり・・・
そこに、写真絵本の中で目を輝かせる子供たちの笑顔がありました。
年を重ねて、「物を所有する」という意味が自分の中で変わってきたのかもしれません。
確かに、うちのランドセルは、対価を払って買ってきたものです。
どう使って、どう捨てようが自由なのかもしれません。
でも、そんな考えこそ傲慢。
役目を帯びてこの世に生まれたものは、最後まで役目を全うしてもらいたい。
わが家での6年間の役目は全うしても、まだ働ける、喜んでくれる人がいるのなら、そこで第二の人生(?)で活躍するのも、ランドセルにとっては幸せなのではないか?
そんなことを考えました。
息子の卒、入学のバタバタが落ち着いたら、二つのランドセルを旅立たせる準備を始めます。


![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1f6af44b.8291616d.1f6af44c.fd89f276/?me_id=1273789&item_id=10000006&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fsugataki%2Fcabinet%2F2020%2Fmini01-shiori-case.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1f6af2c0.f7c03b82.1f6af2c1.b1632a4a/?me_id=1272257&item_id=10000188&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkabankoubouaskal%2Fcabinet%2Frandoseru%2F9007wt%2Fimgrc0086075984.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)