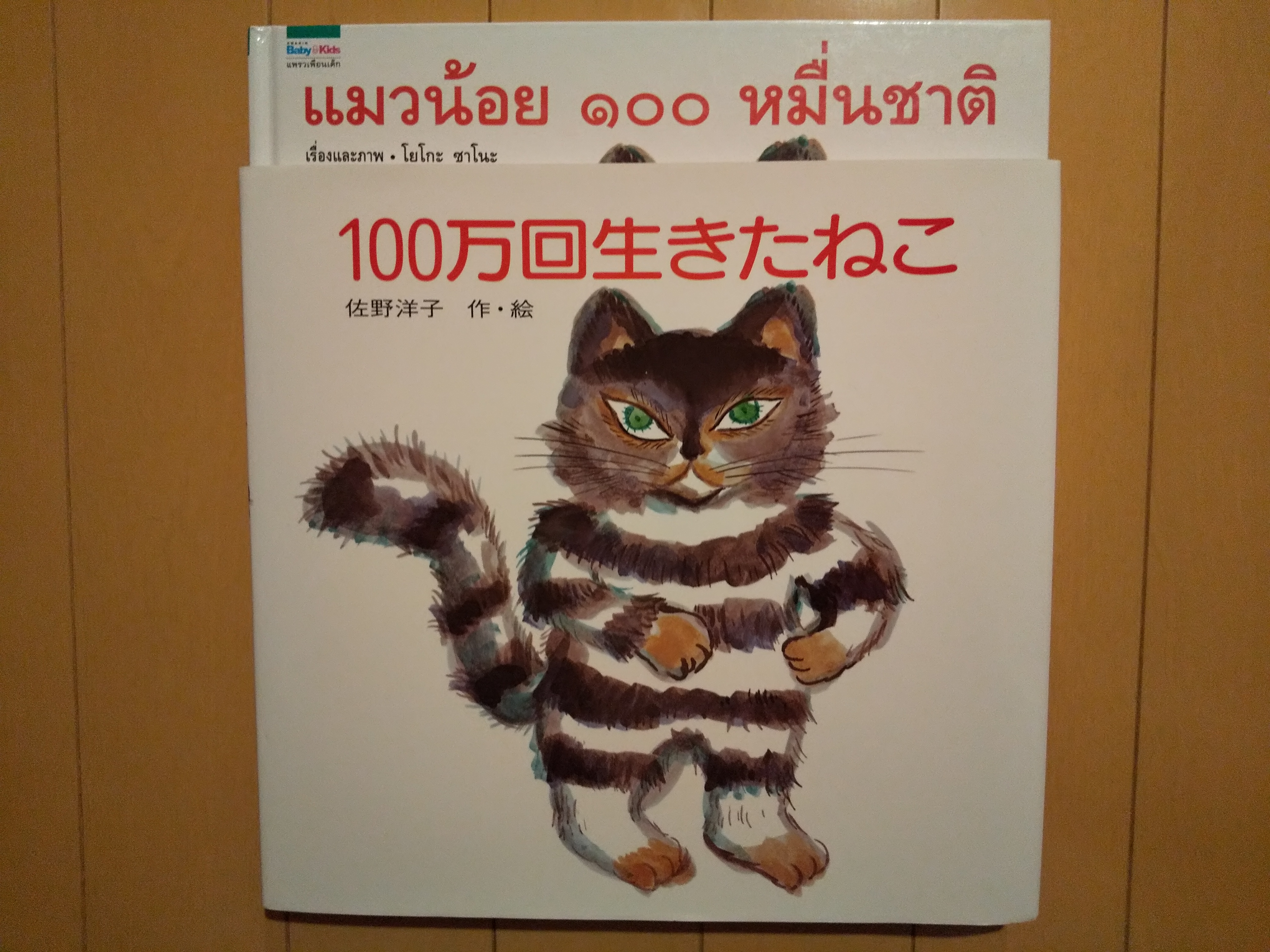「手塚治虫展」茨城県近代美術館に行ってきました
8月15日、終戦の日。
子供たちと茨城県近代美術館で開催されている「手塚治虫展」を観に行ってきました。


今年は、手塚治虫没後30年。
うちの子供たち、中学1年生と小学5年生ですから、当然手塚作品に親しんだ世代ではありません。
それどころか、国語の教科書に「伝記」として載っている、「歴史上の偉人」扱い。
それでも、親の影響で、手塚作品はかなり読んでいます。ブラックジャックなんか、家に全巻揃ってますから。
なので、今回の展覧会も子供たちもかなり喜んで、親子で楽しんできました。

今回あらためて手塚治虫の残した数々の作品を見て、思いました。天才だったな、と。
大好きな作品の直筆原画を見ると、今は亡き巨匠手塚治虫の手が、思いが、ペン先を通じて繋がっていて、ここに発露したのだとしみじみと感じ、心がふるえました。
彼の残したメッセージ。
没後30年経っても色あせないどころか、ますます鮮やかに私たちに問いかけてきます。
自然の偉大さと環境破壊の危機、人間の傲慢さ。
いかに生きるか、医学や医者の意味。生と死の問題。
戦争の悲劇、二度と繰り返してはいけない人間の愚かな行為。
どれも深くて大事なテーマ。
しかし、今回一番はっとしたのは、1989年に発行された「ガラスの地球を救え~二十一世紀の君たちへ~」に書かれていた文章。
引用します。
「『鉄腕アトムで描きたかったのは、一言で言えば、科学と人間のディスコミュニケーションということです。アトムは、自分で考えることもでき、感情もあるロボットです。アトムが人間らしくなりたいと、学校に通うところを描きましたが、計算問題は瞬時にしてできてしまうし、運動能力では比べようもありません。そこで、アトムは非常に疎外感を味わうわけです。
そういう疎外感、哀しみといったものをビルの上に腰かけているアトムで表したつもりなんですが、そういうところは全然注目されず、科学の力という点だけ強調されてしまった。たいへん残念でなりません。ディスコミュニケーションという点では、科学と人間もそうですが、いまの地球と人類にそれが起きている。もっと地球の声に耳を傾けるべきだと思うのです。」

確かに、私も鉄腕アトムはただのロボットヒーローもののかわいい版くらいの認識しかありませんでした。
しかし、どうでしょう。
AIについていろいろ取沙汰される現代、この文章を読んではっとするところがないでしょうか。
AIの機能が進化し、人間を超えるシンギュラリティの問題。
AIに人間の仕事が奪われていくのでは、という不安。
高度な知能、性能を持ったAIや化学技術と、感情、想像・創造力をもった人間、すでに危機的状況にある地球環境。
これらのバランス、融合、協調をどうしていくか、人間はどうしていかなきゃいけないのか、そんな問題を30年前に手塚治虫は提示していたのではないでしょうか。
今だからこそ、子供たちに読んでもらいたい。そう思いました。

手塚治虫展 図録
観賞後は、お約束のミュージアムショップでお買い物。
いつもはポストカードを買うのですが、今回気に入ったものがなかったので、A4判の原画コピーを購入。
早速、「おうちギャラリー」を作りました。

我が家はしばらく手塚治虫ブームが続きそうです。