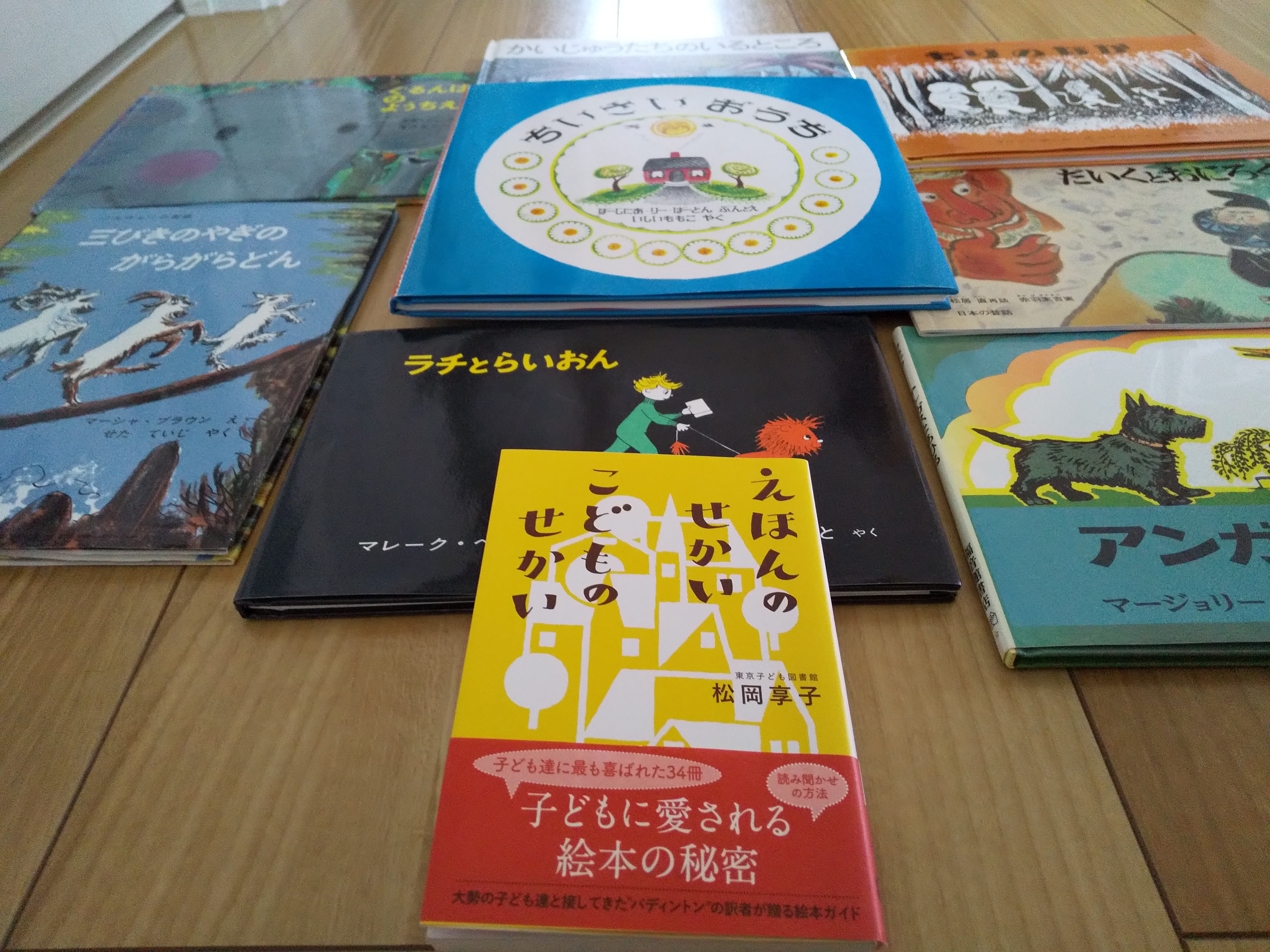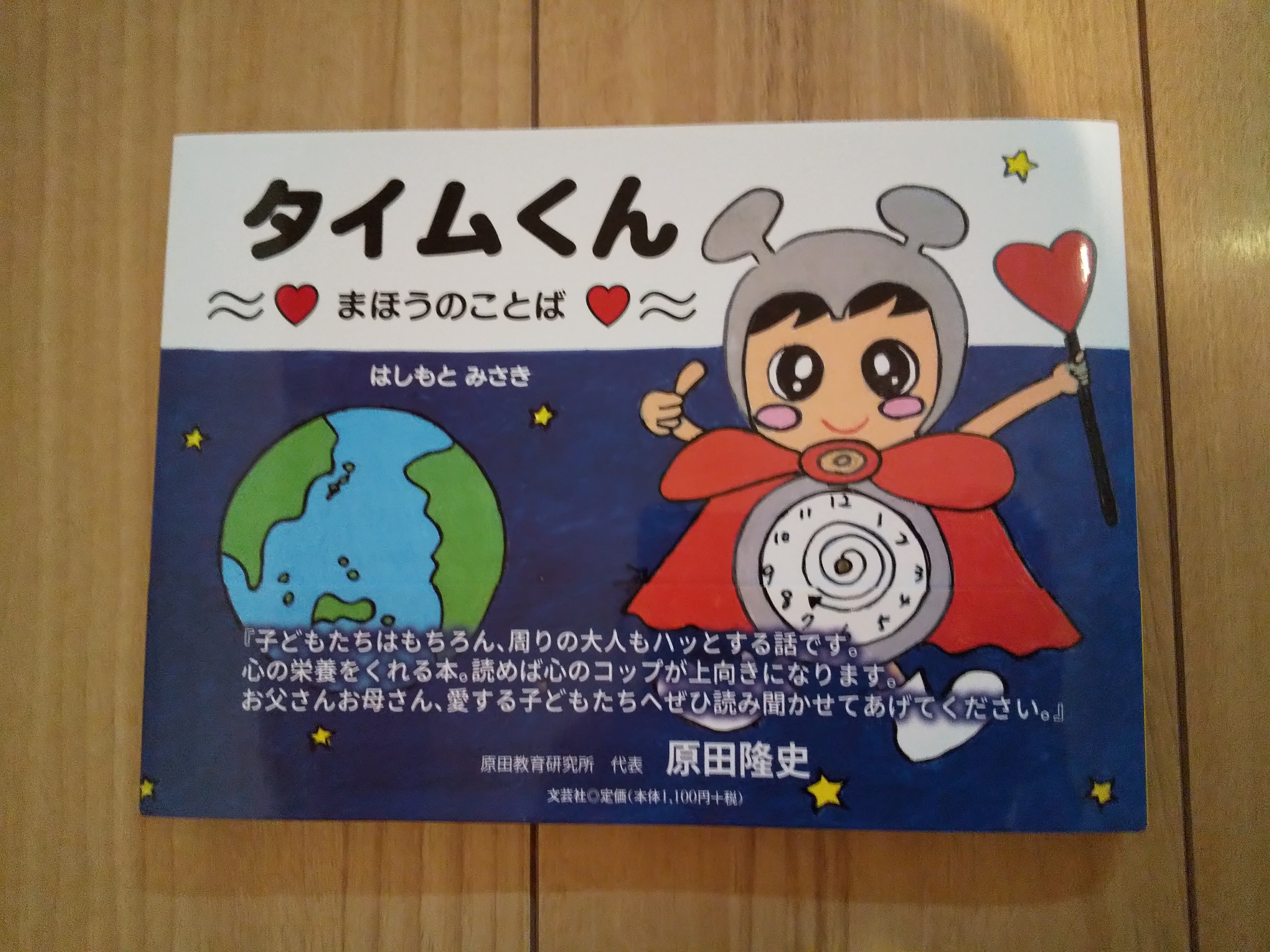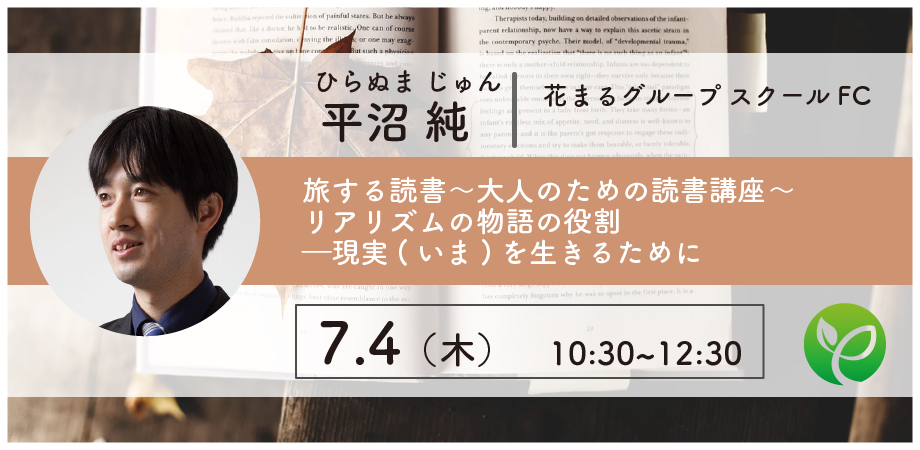字幕なしの映画と絵本の読み聞かせ
精神科医で、ビジネス書作家の樺沢紫苑先生という方がいます。
仕事術や健康について、精神医学や心理学、脳科学などの知見や臨床での経験をもとに、わかりやすく解説されています。
この先生、YouTubeでも毎日情報発信していて、私も時々家事をしながら音声を聞いて、参考にしています。
先日、たまたま映画の見方についての質問に答えている動画を見ていて、気付いたことがありました。
樺沢先生は、無類の映画好きで知られていて、映画評などもよく書いています。
今回の質問は、「洋画は字幕で見るか、吹き替えで見るか、どちらがいいですか?」というもの。
樺沢先生の回答は、映画は娯楽として見るのだから、好きなように見ればいいのだけど、先生ご自身は、断然字幕で、吹き替えは見ないとのことでした。
この回答の中で語られていたエピソードが、印象的でした。
樺沢先生、以前アメリカのシカゴに留学していたのですが、その時は映画を見まくっていたそうです。
そこでは、もちろん字幕はありません。
字幕なしで集中して映画を見ていたら、役者の表情や背景などの細かいところがよく見ることができたというのです。
特に、役者の表情の細かいところまで観察でき、「今まで、字幕ばかり見ていた!役者の表情を全然見ていなかった!!」と、アメリカに行って初めて気づいたそうです。
だから、本当なら字幕なしで原語だけで映画を観られればベストですけどね、とのこと。
この話を聞いて、絵本の読み聞かせのことを思い出しました。
絵本セラピーを学ぶ中で、何度も言われてきたことです。
「大人は字を読んでしまって、絵本の絵が読めていない。」
「絵本は絵が語りかけてくることがあります。今日は、私(セラピスト)が字を読みますので、皆さんはぜひ絵をじっくり見て味わってくださいね。」
これ、映画の字幕ばかり見ていて、映像を見ていないのと似ています。
絵本の絵は、単なる物語の挿絵ではなく、絵が物語をはこんでいく側面もあります。
絵の中には、周到なしかけがかくされていたり、心にくいこだわりがあったりして、そこに気がつくと感動的な面白さがあります。
たとえば、「かいじゅうたちのいるところ」。
主人公のマックスが、ファンタジーの世界に入っていくにつれ、次第に絵の周囲の余白が広がっています。
現実の時点を描いたページは、紙の隅々まで絵が描かれているのに・・・ということに、大人は大抵気がつきません。

また、富安陽子作、降矢ななが絵を描いている「やまんばむすめ、まゆ」のシリーズには、物語とは関係ないけど、必ずまゆと一緒にいるキツネがいます。
このキツネ、降矢さんが自分を物語に中に紛れ込ませているのだそうです。
なんとも素敵な遊び心!
富安さんの講演会で、「まゆとかっぱ」の解説を聞いたことがありますが、大勢の河童の「その他大勢」「エキストラ」的な河童たちにも、一匹(?)ずつちゃんとキャラクター設定がされていて、物語の進行に合わせてそれらの河童も、ちゃんと表情や立ち位置を変えています。
よく見ると、キツネと河童の友情が生まれているシーンがあったりもします。

また、多くの絵本で、裏表紙に登場人物のその後を示唆するような絵があったりして、余韻を持たせています。
そんなところも、つい見過ごしがちですよね。
あらためて、大人に絵本を読んであげることの価値を見直しました。
ブログランキング参加中です!クリックで応援よろしくお願いします♪