2020年、らくちゃんがやってみたこと、始めたこと
こんにちは!
大人に絵本を読んでいる、絵本セラピスト🄬らくちゃんです。(プロフィールはこちら)
激動の2020年も、あとわずかとなりました。
新型コロナで、大きく世界は変り、多くの国でロックダウン。
「ステイホーム」「巣ごもり」「おうちで過ごそう」を合言葉に、いろんな活動が動きを止めざるを得ませんでした。
わが家も、毎日都内に通勤していた夫は、完全在宅ワークになり、子供たちも長い長い休校期間を家で過ごしました。
学校行事も、ほとんど中止か大幅縮小、無観客で開催。
異例づくめの1年となりましたが、私の中ではそれなりに前進、ジャンプ、チャレンジもありました。
そこで、2020年に「らくちゃんがやってみたこと、始めたこと」を振り返ってみました
[rtoc_mokuji title="" title_display="" heading="h3" list_h2_type="" list_h3_type="" display="" frame_design="" animation=""]
大人に絵本、絵本セラピーに関すること
8月から、毎月オンラインで絵本セラピー🄬を開催するようになりました
私が、絵本セラピスト協会から絵本セラピスト🄬の認定をもらったのが、2019年12月でした。
本来だったら、学んだことを生かして、絵本セラピー🄬の実践を積み重ねていこうとしていたところでした。
ところが、ご存知のとおりの新型コロナウィルスの蔓延で、人が集まって何かをすることが難しくなり、当然絵本セラピーも、当分できそうにはありませんでした。
しかし、この状況は長引きそう・・・と思っていた頃、少しずつZoomを使った絵本の活動をする人が現れてきました。
想定外の事態に、業界も試行錯誤だったようですが、オンラインでの絵本の読み聞かせや、著作権の考え方についても、情報発信や注意喚起がなされるようになりました。
少しずつ、アレンジしながらもチャレンジする人が出てきて、著作権の考え方や許可の申請方法なども定まってきました。
そこで、私もチャレンジ!
8月頃から、1月に1プログラムを2~3回、Zoomを使ったオンライン絵本セラピーを開催することにしました。
せっかく学んだことも、実践しなければ忘れるばかり。
使用する絵本は、出版社や作者の許可を得なければならず、制限がある中でのプログラム作りと実践は、私にとっては簡単なことではありませんでしたが、確かにいい勉強になっています。
オンライン絵本セラピーの実践については、こちらの記事もどうぞ。↓




絵本セラピスト🄬として、電子書籍にコラムを書きました
友人が、11月に電子書籍を出版することになりました。
現在、木のおもちゃ屋さんの店長をしている友人は、元保育園の園長さんでした。
彼は、保育の現場が激務であることは、よくよく知っています。
そして、この上もなく尊い仕事だということも。
そんな現場で働く保育士さんたちに、エールを送るような内容の本です。
そこに、絵本セラピスト🄬として絵本の紹介を入れたコラムを書いてくれないか、というオファーをいただきました。
私は、絵本セラピスト🄬としても駆け出しで、絵本や児童書を専門に勉強したわけでもありません。
毎日子供に絵本を読んでいるプロの方に、何が語れるだろう・・・
そう正直にお伝えしたら、「ずっとわが子に絵本を読んできて、その後、大人に絵本を読んでいる、今のらくちゃんの視点で書いてもらいたい」と。
何も背伸びをすることなく、今の私に価値を見てくれたお言葉。
嬉しいじゃないですか。
そこで、今の等身大の私の知識と経験から、大人にも子供にもおすすめの絵本の紹介と、自分の体験を少し書かせてもらいました。
その時の記事は、こちらからどうぞ。↓

タイ語に関すること
東京外語大のオープンアカデミーで、タイ語のクラスを受講し始めました
結婚前は、タイのアユタヤにある日系の会社の工場で、通訳として働いていました。
帰国してからも、次男が幼稚園に入るくらいの頃から、都内の生命保険会社にタイ語翻訳者として、7年ほど勤務しました。
夫の仕事の都合で、翻訳の仕事を辞めてしまい、今はタイ語を使うことがほとんどなくなってしまいました。
タイ語を忘れたくないと思いつつ、新しく始めた絵本の勉強が忙しくなり、なかなかタイ語に手が回りません。
そういう時は、強制力と仲間がいることが大きな推進力になるということを、経験上知っています。
そこで、東京外語大のオープンアカデミーで、学んでみることにしました。

さすが、東京外大ですね。
珍しい言語のコースもいろいろあり、その中でもレベルやテーマごとにクラスがあります。
私が受講することにしたのは、
- タイ語中級Ⅰ:現代タイ語とタイ社会を学ぶ
- タイ語上級Ⅰ ―読解力向上を目指して―
いつかは、タイの絵本の翻訳などもしてみたいですからね~。
実は、これらの講座、本来は4月から東京外語大のキャンパス内で開講される予定でした。
受講料も払い込み、楽しみにしていたのですが、もちろん中止に・・・
11月から、オンラインで開講されることになったのです。
久しぶりのタイ語を学ぶ場です。
果たして勉強になっているかどうかはともかくとして、定期的にタイ語にアクセスできて幸せです。
初めての体験、新たな挑戦
絵本と原田メソッドのコラボ講座開催
私は、目標達成のためのセルフコーチングやメンタルトレーニングの手法「原田メソッド」を学び、2019年、認定パートナーになりました。
自分の生き方や生活をマネジメントするため、また息子たちのサポートをするために、メソッドを活用していますが、コーチングの要素は、いろんな方に提供できるものです。
地道で誠実、そして確実に成果の出る手法に惚れ込み、興味のある方、必要とされる方には、ぜひご紹介したいと思っていました。
ある時、絵本を読んでいる時に、ふと原田メソッドの理念や目指すところにシンクロするものがあることに気がつきました。
原田メソッドも、小手先のテクニックではありません。
とことん自分と向き合い、本当に自分が価値を置く目標を見つけていきます。
そこの段階が、絵本で自分の本心やこだわりに気づいたり、行動への勇気づけになったりすることに、通じる部分があると思ったのです。
「絵本と原田メソッドをコラボした講座を開催したい!」
ふとそんな思いがわいてきて、ほんの導入部分だけでしたが、開催することができ、セミナー講師としてデビューすることになりました。
その時の記事は、こちら。↓
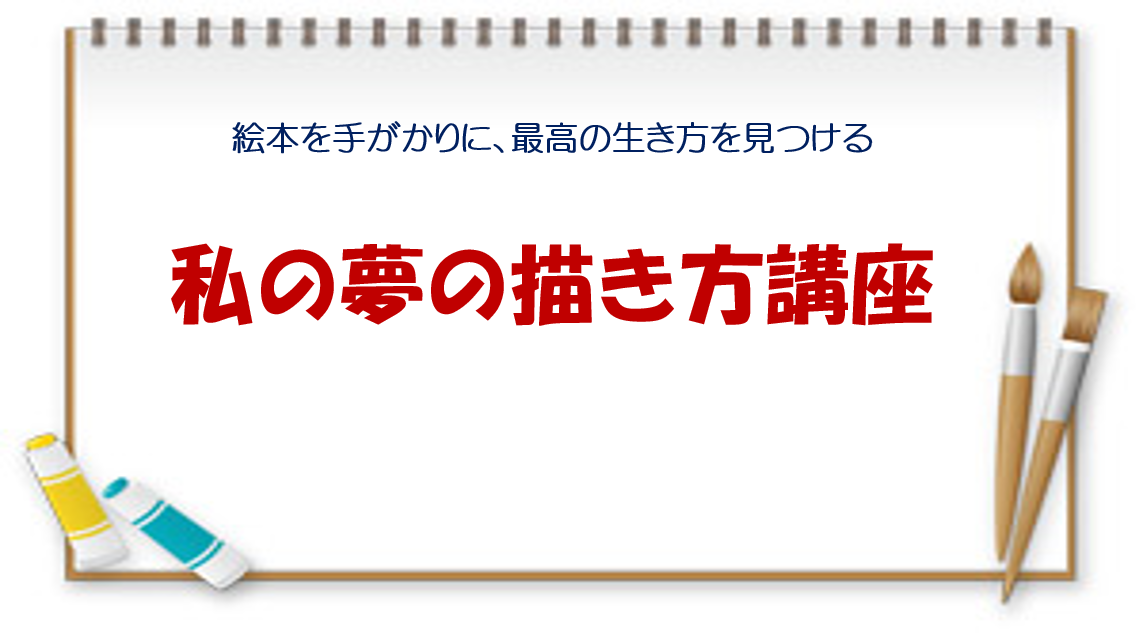
YouTubeライブに出演
11月28日、YouTubeライブに出演しました。
まったく想定外のことでした。
原田メソッドを共に学んだお仲間で、愛媛でエアライン塾をやっているお姉さまからのお誘いでした。
本気の人のがんばりを、広く発信していきたい、それで世の中を少しでも明るく、元気にしたい、との思いがあるとのことでした。
私の話にどれだけの力があるのかわかりませんが、思いには共感します。
とにかく話が来たからには、乗ってみる。
思い切ってやってみました。
その時の記事は、こちら。↓

日々の生活や子どものこと
長い長い休校中に、子どもへのサポートでがんばったこと
今年は、3月に入って早々に一斉休校になり、5月の下旬に分散登校が始まるまで、今まで親も経験したことのない、長い長い春休み。
桜が咲き、散ってしまって、チューリップやつつじが咲いても、進級した実感もなければ、新しい学級活動も始まらない、なんとも不思議な時間が流れました。

学校側も、前例のない事態に、どう対応していいのかわからなかったのでしょう。
やみくもに課題を出して、あとは放置。家庭にお任せ状態でした。
勉強も、不安がないわけじゃないですが、まずは心身の健康第一。
私が取り組んだのは、「給食チャレンジ」と息子のトレーニングのサポート。
ほとんど休校になった3月、手元には幻となった3月分の給食の献立表がありました。
それを再現していったのが、「給食チャレンジ」。
栄養士が作った献立ですから、栄養価、バランスもばっちりです。
海外の食文化の勉強にもなりました。


給食チャレンジの記事は、こちら。↓


もう一つ、息子のトレーニングのサポートは、ただの運動不足解消ではありません。
長男の所属する部活のバスケ部は、夏の総体に高い目標を立てて、盛り上がっていました。
そんな時の活動停止。
様々な不安やフラストレーションを、なんとかしてやらないと、と感じていました。
うちの中をジム化したり、部活のメンバーとZoomをつないで、トレーニング動画を共有しながら毎日トレーニングさせたり。
市営の体育館が閉鎖されるまでは、毎日空きをチェックして予約を入れ、部活の親しい仲間のごく少数で練習させてあげたりしていました。

今思うと、 熱血母ちゃんだったなと思います。
なぜあんなに、息子のためにせっせと走り回ったのだろう・・・
きっと、私自身、何か前向きな、希望が持てることで動いていたかったのじゃないかと、今になって思います。
その時の記事は、こちら。↓



朝散歩瞑想を習慣化
ステイホームになり、夫は在宅勤務、子供たちは休校で、毎日家族4人が家の中にこもることになりました。
その頃から、一人で近所の田んぼや田舎道を、20~30分ほどウォーキングするようになりました。
もちろん、運動不足対策の目的もあります。
でも、本当は一人になれる時間が欲しかったのです。
家族の仲が悪いわけじゃないのですが、私は一人の時間がないと頭と気持ちが整わない気がします。
そこで、一人でお散歩。
考え事をしたり、ブログのネタを考えたり。
読んだ本のことを反芻したり、オーディオブックを聞きながら歩いたり。
ただ、ただ、季節を感じ、花や鳥や虫を見つけて無心に歩いたりする日もあります。
これって、マインドフルネスや瞑想に近い境地じゃないかと、思うようになってきました。
なんとなく気持ちよく、ずっと周りにあったはずの景色の中に、季節ごとの美しいものを見つける感度が上がり、ひらめきや気づきも下りてきやすくなったような気がします。
何より、この時間を取ることで、気持ちが整うのを感じて、いつしか習慣になりました。
春



夏



秋



冬



まとめ
とにかく、いろんな常識がひっくり返った1年でした。
絵本の原画展や講演会、勉強会、イベントなど、興味があればサクッと東京に出かけていた私が、3月以降ほとんど電車に乗っていないことが、自分でも驚きです。
また、以前は週末ガッツリ入っていた息子たちの試合、大会、遠征練習。
長男と次男で、試合がかぶって、体育館と野球場をはしごして走り回るのも日常茶飯事だったのが、自粛期間は夢のような静かな週末を過ごしました。
動きを止めたこの1年。
確かに、物理的な移動範囲はかなり縮小しました。
その分、身の回りに目を向け、深く思考したり、思いを巡らすことを楽しむようになりました。
もちろん、Zoomを使うようになったことも、大きな変革となりました。
距離の壁をやすやすと超え、遠距離の方と、ときに海外にいる方とも瞬時に集まってお話できるということを何度も経験しました。
そう思うと、コロナがもたらした変化は、マイナスや制限ばかりではありません。
地に足をつけて、朝の清々しい空気の中を毎日歩き、自分と対話しながら、これから何をしたいか、どう生きたいか、ずいぶん考えてきました。
そうして迎える風の時代。
今年立ち止まって思考したことを、風に乗せて高く、遠くへ。
どんなことが起こるか、起こせるか、わくわくしています。
この記事は、私が参加しているブログのオンラインサロン「ヨッセンスクール」の「アドベントカレンダー」という企画で書きました。
12月1日~25日までの間、サロンのメンバーが毎日リレー形式で記事を公開していくという企画です。
私は12月17日の担当でした。
他のメンバーの記事も、おもしろいものばかりです。
ぜひ読んでみてくださいね!







